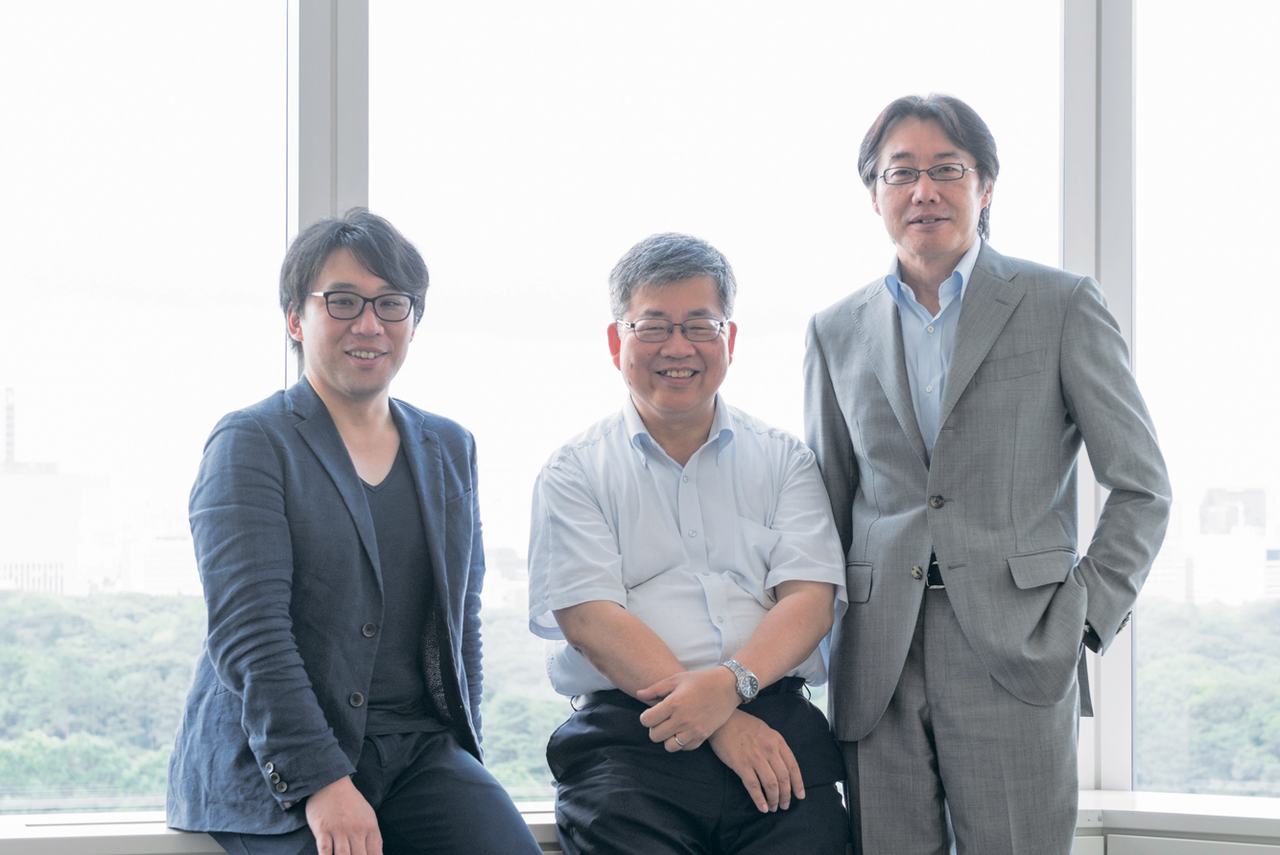ニュートラルな立場でプレーヤーたちを巻き込む
― いま、さまざまな分野でビジネスのサービス化が起きています。JR東日本グループは近年の流れをどのように受け止められていますか。
高橋 鉄道事業はお客様に交通サービスを提供するという意味で、もともと「as a Service」です。ただ、その維持には危機感を持っています。JR東日本のお客様は75%が首都圏で、25%が本州の右半分。それぞれに分けて説明しましょう。
東京への一極集中がしばらく続くため、首都圏はしばらく安泰のように見えます。しかし、定期券の利用に注目すると、すでに団塊の世代がリタイアした影響が出ています。今後も少子高齢化で定期券を手放す方が増え、将来大きく減っていくでしょう。鉄道は固定費が顧客の数に比例しないので、お客様が減れば減るほど苦しい。このままでは将来が安心とはいえません。
さらに厳しいのが地方です。まず首都圏と同じように少子高齢化が進み、地域にお住まいの生活者としてのお客様が減っています。将来そこに加わるのが、旅行者の減少です。例えば特急に乗って東京から伊豆に行ったとしましょう。なかにはタクシーが何台も並んでいる駅がありますが、タクシーやバスなど二次交通の働き手も減っていて、そもそも二次交通を気軽に利用できない駅も多い。そういった場所には旅行者も足を向けなくなります。
人口減少のスピードだけでなく、デジタル化のスピードも脅威です。中国人が日本に来て最初にダウンロードするアプリはGoogleマップ。この話に象徴されるように、いまや観光客はスマホですべてを済ませるモードになっています。
ところが特急に乗って伊豆まで行っても、駅の先にタクシーがあるのかバスがあるのか、スマホからは、まだよくわからない。地域や社会が現在のトレンドに合わせないといけないのに、その変化に対応できなければ、旅行者に敬遠されるだけです。生活者も減り、さらに旅行者も減るようになれば、いずれ地域そのものがなくなるおそれがあります。そうなるとJR東日本が担っている一次交通の維持も危うくなる。
そういったことを踏まえると、地方が変わることが最優先で望まれます。地域課題を解決するには、デジタル技術を活用して、従来の「as a Service」を、お客様にさらに利用しやすくする必要があるのです。私たちが取り組むMaaSも、そうした文脈の中のソリューションとして位置づけています。
― MaaSは地方活性化のソリューションというお話ですが、都市部ではいかがですか。
高橋 私の個人的な意見ですが、日本の都市圏では適合が難しいのではないでしょうか。MaaSはフィンランドで始まりましたが、そもそもの目的はクルマを手放して公共交通にシフトさせることでした。一方、日本の大都市のほとんどは公共交通の依存度が80%を超えています。よって、都市部では「クルマを手放すためにMaaSを活用しましょう」という話にはなりにくい。既にモバイルSuicaのような便利なものもありますし。
例えば恵比寿から六本木に移動するシーンを想像してみてください。公共交通が充実していない都市なら、シェアサイクルか、バスか、タクシーか、あるいはそれらを組み合わせて移動をします。海外では電車と自転車の組み合わせは珍しくなく、電車の中に自転車を持ち込む姿もよく見かけます。しかし、東京ならほぼ地下鉄一択。電車に自転車を積む人もいません。
もちろんワンアプリですべて検索できてサブスクリプションになっているサービスは便利であり、追求していくべきでしょう。ただ、地方の抱える課題に比べると、切迫性は低いといわざるを得ません。日本の都市圏でMaaSが普及するとしたら、クルマの利用率が高い中部圏くらい。その他の地域では、ドラスティックな変化は起きないかもしれません。
― 地域創生の一環としてのMaaSに、鉄道会社がイニシアチブを持って取り組むのはなぜでしょうか。
高橋 地域独自、あるいは外部のどなたかが取り組むとしても、時間やお金がかかるし、うまくいってもまばらになるおそれがあります。だとすると、一次交通事業者であるJR東日本を含むJR東日本グループが地域の課題を先に網羅して解決したほうがいい。
もちろんMaaSに取り組む背景に、事業を存続させる目的があることは間違いありません。そのあたりは、将来クルマを所有する人が減ることに危機感を抱いてMaaSに取り組んでいるトヨタさんと同じです。ただ、クルマは場所を選ばないのに対して、鉄道は「この地域がダメだから、ほかに線路を移す」といったことができません。エリアは固定で、自分たちの未来はエリアの未来と一体。地域創生のためのMaaSを誰かがやらなければいけないのなら、それは地域に深くコミットしているJR東日本グループなのだろうと思います。
なかでもグループのハウスエージェンシーである私たちjeki(ジェイアール東日本企画)は、地方に旅行するムーブメントをつくることで、長年、地域活性化に貢献してきました。2011年以降は、そこに地域創生ビジネス、ソーシャルビジネスの流れも加わりました。例えば福島県の相双地域12市町村にはまだ避難解除されていないところがありますが、解除されても仕事がなければ人は戻りません。そこで、経産省の事業で仕事をマッチングするお手伝いをしたりもしています。そうした流れがあるので、MaaSに取り組むのはごく自然なことでした。
元来、広告代理店はさまざまなプレーヤーを束ねてプラットフォーム化して何かをつくっていく仕事であり、これまでもjekiはさまざまなプレーヤーがいるプロジェクトでグループのフロントに立ってきました。今回のMaaSもまさに多くのプレーヤーが関わってくるので、その役割を果たしていくつもりです。
― プラットフォームをつくるにあたって、どのようなことを意識していますか。
高橋 MaaSの世界は技術オリエンテッドなところがあるので、メディアでも「どこの技術がプラットフォームを取るか」という形で取り上げられがちです。しかし、デファクトスタンダードを技術で押さえて覇権を握るというところに、必ずしも私たちの主眼はありません。まず先にあるのは、エリアをきちんと維持するというミッション。そういう意味では、本当にピュアですよ。
幸い、私たちはそのことをご理解いただきやすいポジションにいます。どこかの企業が「この指止まれ」というと、競合その他の関係があってA組とB組に分かれたりしますが、私たちは民間でありながら社会性を帯びた企業で、ニュートラルな立場。呼びかけ人として最適です。
地域の方々からも、比較的信頼は厚いと感じています。従来デスティネーションキャンペーンなどを展開してきましたが、鉄道会社ができるのは、地域にお客様を連れてくることだけ。その先を担うのは地域の方々です。ですから、上から目線ではいけないし、これまでも一人も脱落者が出ないようにやってきました。そうした姿勢を知っていただいてるので、「どうしてJRがやるんだ」「どうしてjekiがやるんだ」とはあまり言われないです。
― JR東日本は2017年9月5日に、オープンイノベーションによりモビリティ変革を創出する場として「モビリティ変革コンソーシアム」を設立しました。コンソーシアムには、120を超える企業や団体が参加しています。
高橋 技術アプローチの場合、単一の技術を持つA社が自治体に行っても、提供できるソリューションは一つだけです。例えばキャッシュレスの「〇〇ペイ」を持つ会社が提供できるのは、「〇〇ペイ」だけなわけです。しかし、自治体はキャッシュレスだけをやりたいのではなく、インバウンドで多くの人に来てほしいとか、人の流れを円滑にしたいといったニーズの中でキャッシュレスをやりたいのです。それには複数のプレーヤーの協業が欠かせないし、旗幟に関係なく組める培地が必要です。コンソーシアムは、その培地の役割を担う場になればいいと考えており、いまjekiではこの事務局を運営しています。
「伊豆をデジタル観光地に」が地域の人たちに響いた
― 今回、伊豆エリアで行った日本初の観光型MaaSの実証実験についてうかがいます。この実験が目指すものは何でしょうか。
高橋 マーケティングの世界では、お客様の課題から出発するのが当たり前です。ところが技術オリエンテッドの世界だと、「こんなアプリをつくったので、どうですか」と、技術をどこに当てるかという話になってしまう。それは正しくなく、MaaSも課題を解決することから考えなくてはいけません。
では、今回、解決すべき課題は何か。それは地域の課題です。いまはまだ訪日外国人が増えているので、どの観光地も総数としては旅行客が増えています。しかし、その一方でバスの運転手や旅館で布団の上げ下ろしをする人は減っています。今回の実証実験は、あくまでもそういった問題を解決するためのものです。
MaaSを使えば、観光客は便利になります。ただ、観光客の課題解決を目的にすると、地方の方は「自分たちの知ったことではない」となる。ですから、実証実験でも、何人がダウンロードして使ってくれたかということより、伊豆がどのように変わるのかを見る必要があります。もちろん3カ月では変わるわけはないので、変わる芽が出てきたのかどうかを見ていきます。
― 実証実験には、地域の方々の協力が必要不可欠です。地域の方々と、MaaSが提供する「価値」をどのように共有していったのでしょうか。
高橋 伊豆半島には13市町村あって、足並みを揃えるのは簡単ではありません。そこで伊豆の観光を束ねる「美しい伊豆創造センター」を通じて多くの皆さんに参画いただく形にしました。
第1回の実行委員会で最初に申し上げたのは、「伊豆をデジタル観光の先進地にする」ということ。実は当時、下田市にはクレジットカードが使えるお店が3軒しかありませんでした。別のシンポジウムで、「カードはコンビニで使えるから」という声もありましたが、観光客がコンビニの弁当を楽しみにしているとは考えにくい。こうした問題も含め、デジタルで魅力ある地域にするためのMaaSだと説明したのです。
例えば観光施設に直接「クレジットカードを入れましょう」と言っても、「手数料3.5%は高い」という話になってなかなか進みません。しかし、MaaSで伊豆を観光デジタルの先進地にするとアプローチしたことで、「Izuko(イズコ)のフリーパスなら手数料を払ってもいいか」と徐々に考え始めてくれました。また、デジタル観光のところから話を始めたので、「MaaSって電車やバスだけの話じゃないのか」とわかってもらうこともできました。
こうした取り組みに全国からいろいろな方が視察に見えることも、いい刺激になっています。実証実験前は、「自分たちは関係ない」という方も大勢いました。しかし、伊豆が日本初の観光型MaaSの実験場として注目されたことで、「自分たちが変えられる気がする」とおっしゃる地元の方が増えてきました。
― 一方、実証実験で見えてきた課題についてはいかがですか。
高橋 今回のフェーズ1はマーケティングコミュニケーションにも力を入れました。地域にはそもそもスマホを持っていない方も多く、キャリアさんと組んで説明会を開いたり、スマホを貸し出すといったところから始めました。その結果、アプリをダウンロードしてくださる方は想定以上に多く、一定の浸透はしたと考えています。
しかし、実際に使っていただくという意味では、まだまだ。年末に予定しているフェーズ2に向けては、使い勝手をもっと良くすること。そしてオール伊豆と言いつつ今回は伊豆半島の東半分しかカバーしていないので、西伊豆や静岡空港まで広げていくことが課題になるでしょう。
また、実験を通して痛感したのは、地域の既存の事業者と折り合いをつけてサービスを入れていくことの難しさです。今回、下田の大型バスが入れない旧市街で、オンデマンド乗合交通を実験しました。オペレーターは地域のタクシー会社。下田には3社あって、全社にご協力いただけました。
ただ、最初はあまりいい反応を頂けませんでした。いま、各地でオンデマンド交通が実証実験段階にとどまっているのは、既存の二次交通事業者が抵抗勢力になっているから。本当はそのような方々こそ、オンデマンド型の交通サービスに移行して当事者になっていただくのが理想なのですが、ハードルがとても高い。下田の場合は運よくクリアできましたが、他地域で展開するときはやはり課題になってくるでしょう。
また二次交通オペレーターとの協力体制には、規制も関係しています。タクシーは市町村ごとのライセンスなので、原則市町村をまたいで営業することができません。例えば河津の桜の時期は河津駅のタクシー需要が高まりますが、ほかの地域から河津駅に来て客待ちすることはできないことになっています。伊豆13市町村で、タクシー会社は25社。ユーザーは「みんな一緒にやれば便利になるのに」と思いますが、いろいろなハードルがあって難しいのです。
ほかにも交通領域には規制が多く、便利なサービスにしようと思うとさまざまな規制が立ちはだかってきます。MaaSの実証実験をトリガーにして、なんとか規制緩和の流れをつくりたいですね。
― 二次交通のオペレーターや観光施設以外に、今後、巻き込んでいきたいプレーヤーはいますか。
高橋 旅館とホテルです。日本の観光は1泊2日が平均値で、旅館に泊まって次の日に同じ道を引き返す2地点往復直行が主流。特に伊豆はそうで、ほとんど周遊されません。となると、周遊が基本である外国人観光客には選ばれない観光地になってしまう。
周遊される観光地に変わるためには、旅館にも変わっていただかないといけません。例えば館ごとの送迎バスをやめてオンデマンド交通にしたり、観光地を周遊しながら旅館まで送るサービスがあってもいい。また、旅館に観光施設の割引券が置いてあるように、それをデジタル版で配布するといった方法も可能なはずです。
今回は旅館に対して「宿泊される方々にアプリのダウンロードをお勧めしてください」というレベルのお願いをしました。しかし、それ以上のアプローチはできていないので、これから頑張っていかなければいけないですね。
― 実証実験の先は、どのような展望を描いていますか。
高橋 マーケティングの視点から正直に申しますと、年に1回観光地に行くためにアプリをダウンロードする必要があるのかどうかは疑問です。だからこそ実証実験で終わらずに根づかせるには、地域の方々がサービスを使いこなして、生活の一部に組み込んでいる状態に近づけていかなければいけません。そのためには「JR東日本グループや東急グループがやっている」ではなく、地域の方々に「MaaSは自分たちのものだ」という意識を持っていただく必要があるでしょう。
必ずしも「Izuko」という名前でなくてもいいのですが、今回の実験を通じてサービスが何らかの形で地域のインフラとして残ること。それが一つのゴールになると考えています。