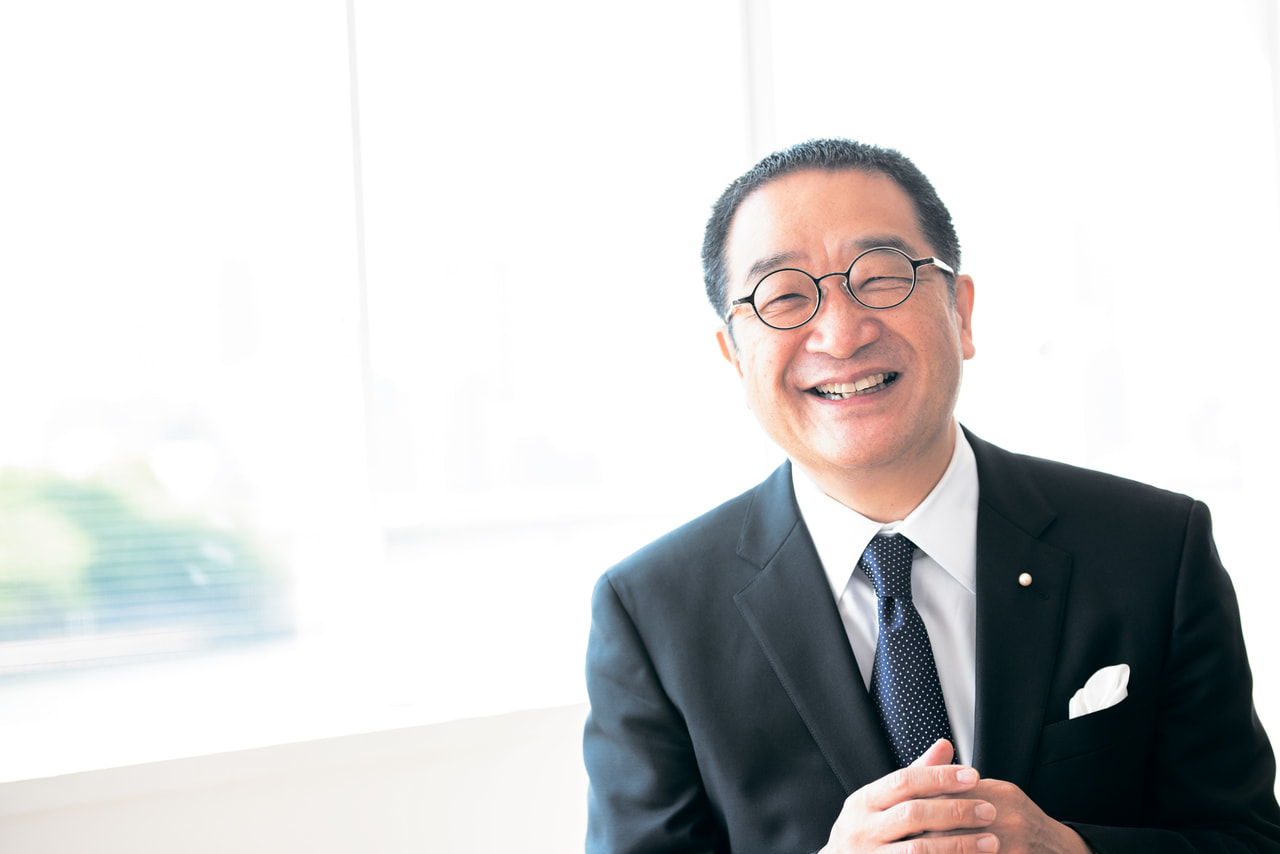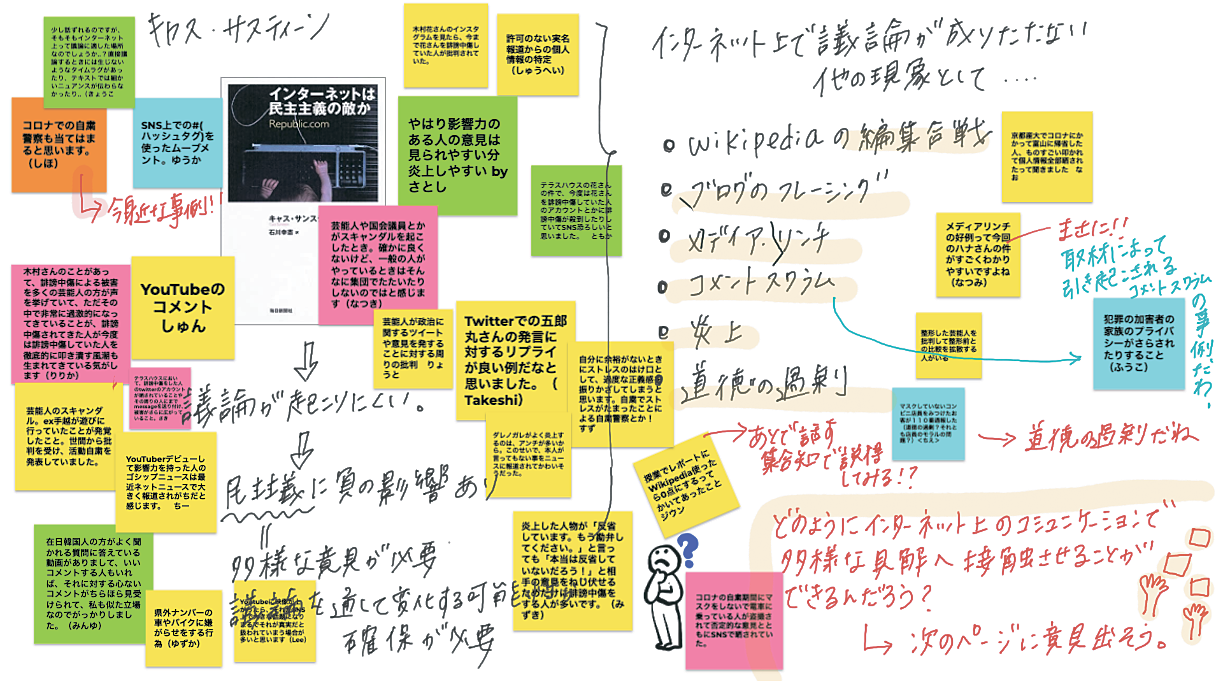企業から大学へ戻り、産学連携の道へ
私は1982年に京都大学の大学院を出て、当時の松下電器産業、現在のパナソニック株式会社に入社しました。会社では中央研究所に配属され、コンピュータ・シミュレーションの研究開発を担当。ビデオテープレコーダーのテープとヘッドの間で起きるトライボロジーや電磁場のメカニズムや抗原抗体反応など、肉眼では捉えきれない物理現象を方程式で表し、その挙動を数値解析を用いて可視化する研究とソフトウェア開発をしていました。在籍中はシミュレーション用のプログラムを書く一方で、解析理論を研究し、論文として発表もしていました。
コンピュータ・シミュレーションは最先端の技術なので、常に勉強し続けなくてはなりません。しかし入社して10年ほど経つと管理職という立場になり、仕事が忙しくて勉強の時間が取れなくなっていきました。さらにバブル崩壊の影響で、多くの企業で基礎研究所が閉鎖されるなど、企業内で基礎的な研究を続ける環境が、徐々に厳しくなっていた。そんなとき、母校から「帰ってこないか」という誘いがあり、1993年に工学部機械工学科助教授として大学に戻りました。
大学に戻ってからは、電磁場や金属粉体の挙動の解析などを研究テーマとしました。さらに、生体内の分子の行動は複雑ですが、数千の連立方程式を解くことでシミュレーションが可能になり、細胞内の現象が見えてきます。2000年代には医学部の先生と共同で、細胞生体シミュレーターの開発プロジェクトに参加してきました。細胞のシミュレーションをするには、細胞特有の特性データを計測する必要があり、そのために細胞への刺激応答を計測するためのμ-TAS(マイクロタス)と呼ばれる、マイクロデバイスとそれを用いた細胞実験の研究をしてきました。その中では、hiPS細胞の特性の研究や分化した臓器細胞を立体にして刺激応答や組織の特性を計測するOrgan-on-a-chipの研究をしてきました。これらの私の研究では、医学部や生命科学等の医工連携研究だけでなく、企業や他大学、海外など、多くの研究機関との連携が必要で、私は2000年代を通じて、産学連携の共同研究にも取り組むようになったのです。大学以外でもNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクトマネジャーやJST(国立研究開発法人科学技術振興機構)のCOI(センター・オブ・イノベーション)プロジェクトの研究リーダーとして産学連携の共同研究に参加。気がつくといつの間にか、学際連携・産学連携等を担当するようになりました。
2015年、私が京都大学で総長室長を務めていた時期に総長であった松本紘先生が、理化学研究所(以下、理研)の理事長に就任され、私は大学に籍を置いたまま、理研の理事長特別補佐を拝命します。2018年には京都大学教授を退官し、理研の産学連携担当理事兼科技ハブ産連本部の本部長となりました。
振り返ると私はコンピュータ解析に始まり、医工連携、バイオエンジニアリングからマイクロデバイス開発まで、多くの分野に関わってきました。誰も手をつけていない新しい研究を続けようとすると、いろいろなことを自分の手でやらなければいけなくなり、結果として扱う領域の幅が広がっていったといえるでしょう。「何かを生み出したい」という熱と、未知なるものへの尽きない興味が、私の研究のエンジンでした。
産学連携のDNAを持つ理研
理研は、現在は文部科学省所轄の国立研究開発法人となっていますが、元々は大正時代に実業家の渋沢栄一により財団法人として設立された、自然科学の総合研究所です。設立当初から積極的に産学連携を行っており、理研の研究成果をもとに誕生した多くの関連会社は「理研コンツェルン」と呼ばれ、日本の財閥の一つとみなされたほどでした。
産学連携をどのように進めるかは、今や日本だけでなく世界各国の課題となっています。その中にあって理研の「基礎研究から事業化までを一貫して扱う」という伝統は、とても貴重なものです。基礎研究が成果を挙げて応用研究に進んだとしても、何かしら壁にぶつかって「また基礎研究をやって調べ直さないと」となる状況は、必ず出てきます。事業化が成功してからも、より省エネにしたり効率化したりといった新たな目的のために、また基礎研究が必要になってきます。研究のバトンは基礎から事業までの間をくるくる回っており、そのサイクルを完結させられる環境が必要なのです。
理研では普段、基礎研究をしている研究者でも、フェイズによっては応用研究、開発研究に関わります。基礎研究中も頭のどこかで応用を考えていて、企業の研究者と連携することもよくあります。
基礎研究とプロダクト開発では、同じ研究者でも立場は大きく異なります。研究機関や大学にいる研究者は論文を書かなければ評価されません。一方、企業のプロダクト開発では製品ができなければ評価されませんし、できたプロダクトが事業化されなかったり、利益が出ないまま終わってしまったりしても評価されません。それぞれの立場でそれぞれのミッションがあるのです。
このように異なる立場にある組織同士、研究者同士を仲介し、役割分担、費用分担、権利関係の調整をして、お互いにWin-Winの関係を作ることこそ、産学連携です。
戦後の日本の産業の歴史を俯瞰すると、日本企業は1960年代の高度成長期から80年代まで、材料開発から製品づくりまでを自社で完結させ、そこにサービスまでつけて販売する、垂直統合型のビジネスモデルで大きな成功を収めました。
しかしバブル崩壊後の「失われた20年」を経て、日本でも各社の分業による水平統合型のビジネスモデルが主流になると、企業では各部門の選択と集中が進み、基礎研究の部隊を抱えている企業もどんどん減っていきました。開発部門においても外部との連携が必須となり、特に基礎研究部門を持たない企業は、大学や国立研究所と連携することでそこをカバーしていく必要があります。
その連携をどう滑らかに回していくか。これを理研の立場からマネジメントしていくことが、現在の私の仕事です。
バトンゾーン制度と株式会社理研鼎業
現在の理研の産学連携の中心は、基礎研究から実用化研究までを企業と共同で進めていくための場である「バトンゾーン」です。
バトンゾーンには大きく2つの枠組みがあります。
1つは「産業界との融合的連携研究制度」で、理研の持つシーズによって、企業のニーズを解決していくことが目的です。理研が協力企業を募集し、企業からの提案を受けて理研内に研究チームを作り、企業と理研がリソースを出し合って共同研究を実施します。1つのテーマに依存して産学が共同研究を行うスキームです。
そしてもう1つ、より広い範囲で産学連携を行うためのスキームが、「連携センター制度」です。理研内部に企業名を冠した連携センターを設置し、複数の研究テーマを含む中・長期的な課題に共同で取り組んでいきます。研究テーマは企業側と、理研側の担当となるセンター長との議論によって決めます。理研と企業が共同で新しい研究領域を創出する「共創」を行うとともに、理研と企業双方の文化を吸収した人材の育成を図ることが目的であり、2020年4月現在、11センターが活動しています。
理研と外部との連携は、これだけにとどまりません。JSTやJSPS(日本学術振興会)、NEDO、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)などから、公的な資金を獲得するために国のプロジェクトに参加すると、必然的に多くの企業や研究機関、大学と共同研究を行うことになります。そこでは新たな共同研究契約を締結したり、お互いの知的財産をどう扱うか、協議したりする必要が出てきます。
企業との連携からベンチャー企業が誕生することもあります。企業は基本的に自らのビジネスサイズから事業化を考えるため、年間売上高が数兆円もあるような企業は、年間売上高が1億円程度しか見込めないプロダクトはなかなか作ろうとしません。そうした企業側が受け取らなかった研究成果を事業化したいと望む理研の研究者が、自らベンチャー企業を立ち上げるのです。研究者の要望に応える形で、理研自身もスタートアップベンチャーの育成を始めています。
2019年、こうした「知的財産管理・契約締結」「ベンチャー育成」「共同研究のマネジメント」「共創機能」という理研内の4つの部門をまとめて、理研が100%出資する株式会社「理研鼎業」を新たに設立しました。研究と社会との接点である産学連携をより機動的に動かしていくために、独立組織を作ったわけです。理研鼎業は「研究成果を最大化し、その社会還元を加速すること」を企業理念に掲げ、理研の産学連携をスピードアップし、共創の成果を世の中に還元していく役割を担っています。
本年5月、コロナ危機で全国に発令された緊急事態宣言が解除されました。理研としてもこの間、中断していた共同研究や共同事業が少なくないので、今後はぜひそれらを再開させていきたいと思っています。ただ危機からの回復度合いは一様ではなく、先を見据えた共同研究を進めたいという企業もある一方で、まだ共同研究の再開が難しい企業もあります。産学連携をマネジメントする人間は、そうした個々のシチュエーションにも十分に配慮しつつ、注意深くプロジェクトを進めなければなりません。
大学と企業の研究者の違い
研究者は大学や国立研究所などの「学」にも、「産」である企業にもいます。
それぞれの違いを考えると、大学や理研の研究者は基本的に「Curiosity Driven」で、自分の興味、好奇心に基づいて研究をやっています。大学の研究者も、最近は予算をもらうためにいろいろ理由をつけなくてはならないので、「これは何の役に立つの?」と訊くと、一応は答えてきます。でもその実、「どうやって研究成果を社会に還元していくのか」を真剣に考えている人は少なく、自分がやりたい研究をやるために、「こんなふうに役に立ちますから」というストーリーを後付けしているのが実情でしょう。
そうした研究のモチベーションを一概に否定するのは間違いです。個人の持つ好奇心、興味もある程度は認めていかないと、研究の自由度が下がり、「あれも無駄、これも無駄」となってしまい、研究者もやる気を失くしてしまいます。
本当のところ、基礎研究に「無駄」というものはないのです。たとえ狙っていた成果が出なかったとしても、「このやり方ではうまくいかない」とわかったこと自体が、1つの成果なのですから。
一方、企業の研究は「出口オリエンテッド」です。たとえ基礎研究部門であっても、「会社のこの事業に役立つ」というストーリーを描き、経営陣を納得させられなければ、研究を認めてもらえません。私も昔、会社で研究室を持っていたときは、次年度の予算をつけてもらうために、10月、11月ぐらいにヒアリングを受け、「こういう役に立つので、これだけ予算をください」と上司に申請していたものでした。
そのストーリーも、こちらが言っているだけではだめで、事業部長や分社化した子会社の社長といった、こちらが開発する技術を受け取る側の人たちが、「その技術は確かに役に立つので、ぜひ研究を進めてください」といって判をついてくれないと、やらせてもらえません。
日本の基礎研究は負けていない
メディアでは最近、「日本は基礎研究をおろそかにしている。このままでは10年後にはノーベル賞などまったく取れなくなるだろう」といった批判がよく聞かれます。
しかし私自身は、必ずしもそうは思っていません。理研の研究成果にしても、トップレベルの科学ジャーナルへの掲載率や取得した重要特許の数といった指標面を見ても、よくがんばっています。理研だけでなく日本の研究機関全般を見ても、同じことがいえます。
もちろん国によって、「この分野が得意」という得手不得手があり、日本が全ての分野でトップレベルにあるわけではありません。また基礎研究から産業化に至るスピードについては、個々の研究以上に、産業化に携わるプレーヤーの層の厚さが問われます。基礎研究の実用化に必要な研究者・技術者の厚みについては、日本はアメリカ、ヨーロッパに比べて薄い領域がある。また、当初多くの研究者・技術者がいたものの現在では衰退している分野もあります。最近では中国も人口の多い分、プレーヤーの層が厚くなっています。そういったことから日本に不利な点があるのは事実でしょう。
理研は今年2月、神奈川県衛生研究所と共同で、新型コロナウイルスを迅速かつ高感度で検出する手法を開発しました。
このように迅速に対応ができたのも、以前から理研内で基礎研究を続け、PCR工程の時間を短縮するための原理を見つけていたからです。だから神奈川県衛生研究所がダイヤモンド・プリンセス号の乗船者の検体から新型コロナウイルスの株を分離することに成功し、ウイルスの遺伝子構造がわかったとき、すぐに検査キットを開発することができました。
よく「基礎研究はいつ役に立つのですか」と訊かれるのですが、研究開発とは、今日研究を開始して明日には結果が出るというものではありません。ですが上の例でもわかるように、日頃から基礎研究を積み重ねていることが、いざというときの力になってくれます。
今も理研のホームページ上にはさまざまな研究テーマが並んでいます。それらは一見すると、必ずしも緊急性のあるテーマと思われないかもしれません。しかし日頃から基礎研究を続けていて初めて、問題が起きたときに対応できるのです。
基礎研究分野で理研が展開している新たな取り組みに、「数理創造プログラム(Interdisciplinary Theoretical andMathematical Sciences Program)」、通称「iTHEMS(アイテムズ)」があります。現代数学の分野横断的活用を目指し、理論科学・数学・計算科学などの専門家が、一つのテーマの下に異分野の研究者と「研究セル」を作り、議論していくことで、宇宙・物質・生命の解明や、社会における基本問題の解決を目指しています。
iTHEMSでは現在もコロナ危機の中、Zoom等を利用して、数学や生物学、物理学などのセミナーや討論会を開催しています。4月にオンラインで行われた「数理で読み解く科学の世界」という特別講演会には、1,000人単位の参加者がありました。
求められる共同研究の仕組みづくり
理研は約3,000人の科学者・技術者を擁し、およそ600のプロジェクトを進めていますが、世の中から見れば「たった3,000人」であり、一つ一つのプロジェクトチームの人数もわずかです。
日本の各大学も一見するとたくさんの研究室を抱えていますが、分野別に分けていくと、1つのカテゴリーに属する研究室はごくわずか。例えば、今はやりのテレコミュニケーションにしても、1つの大学にある研究室は多くて3つ止まりでしょう。それは、教授の数にして3人程度ということです。
1人の研究者が研究できる範囲は、ごく狭いものにすぎません。大きなプロジェクトを進めていくには、やはり大人数のほうが有利です。同じ分野の研究者が連携して1つの大きなテーマに取り組むことが重要で、さらに異分野の人たちとも連携していかなければ、研究成果を社会に還元するところまでたどり着けません。
そうした連携では、メンバー全員が毎回自分の利益だけを考えるのではなく、「今回はほかの人のために協力し、何かを生み出そう」と割り切らなければ、うまく進みません。
そう思えるためには、日頃からお互いが知り合い、コミュニケーションが取れている必要があります。たとえ小さなプロジェクトであっても、同じ目標に向かって研究してきた経験が一度でもあれば、それだけでまったく違ってきます。そうした機会を増やすためにも、外の組織との間で信頼関係を醸成し、共同研究をマッチングしていく仕組みが必要です。多くの人を取りまとめられる、プロジェクトの司令塔となる人材の育成も欠かせません。
理研では日本全体に共同研究の輪を広げていくための取り組みとして、「科学技術ハブ」構想を推進しています。これは理研が科学技術におけるハブの役割を担い、大学、研究機関や産業界と協働し、研究開発のネットワークを形成強化することで、イノベーションの創出を後押ししようとするものです。私は現在、その本部にあたる、「科技ハブ産連本部」の本部長を務めています。
2019年には九州大学との間に連携研究拠点を設けて、若手研究者育成のための共同研究プログラムを始めました。このような連携は広島大学、大阪大学など西日本の各大学とも行っていますが、今後、東北大学とも行う予定です。
私はこうした異なる研究組織同士の日常的な連携が、日本全体としての研究成果の最大化に不可欠と考えています。幸い、コロナ危機をきっかけにオンライン会議のシステムが普及したことで、遠隔地でも顔を合わせてのコミュニケーションが取りやすくなっています。
こうした連携で難しいのは、ただ研究者同士を引き合わせればいいというものではない、ということ。研究者も人間で、お互いの相性がよくないと共同研究もうまく進みません。サイエンスの世界でも、やはりコミュニケーションと相互の信頼が大切なのです。
広報と科学コミュニケーション活動
研究者の役割の一つに、一般の人たちに科学への興味を持っていただき、社会全体の科学リテラシーを上げていくことがあります。これは日本の科学技術の水準を上げていく上でとても大事なことで、国立の研究所としての責任であると考えています。
理研では編集工学研究所と共同で、2017年より「科学道100冊」というプロジェクトを始めました。科学の素晴らしさを教えてくれる本を100冊選び、全国の図書館や書店等でイベントを開催し、紹介していく試みです。2019年からは毎年恒例の企画となり、成人向きの「科学道100冊」のほか、幼児から小学生、中学生の皆さんに向け、科学の入り口となる書籍を紹介する「科学道100冊ジュニア」も開催しています。
100冊に選定された本は、私たち科学者が読んでも面白い内容のものばかりです。ご興味のある方はぜひ、図書館でお尋ねください。理研の広報でも、一般の皆さんへの情報発信は積極的に進めていきます。
理研では今回のコロナショックでも、国の研究機関として新型コロナウイルスに対してどうアプローチしていくかを議論し、理研内の生命科学系の各センターが外部の研究機関と連携し、3月から治療薬の研究を開始しています。こうした取り組みについてもぜひ広く知っていただき、社会における理研の役割に対しての理解を深めていただかなければなりません。今のような危機に科学者は何をなすべきか。ただ事態を検証して終わりではなく、社会貢献につながる、より積極的なアクションに結びつけていければと思っています。