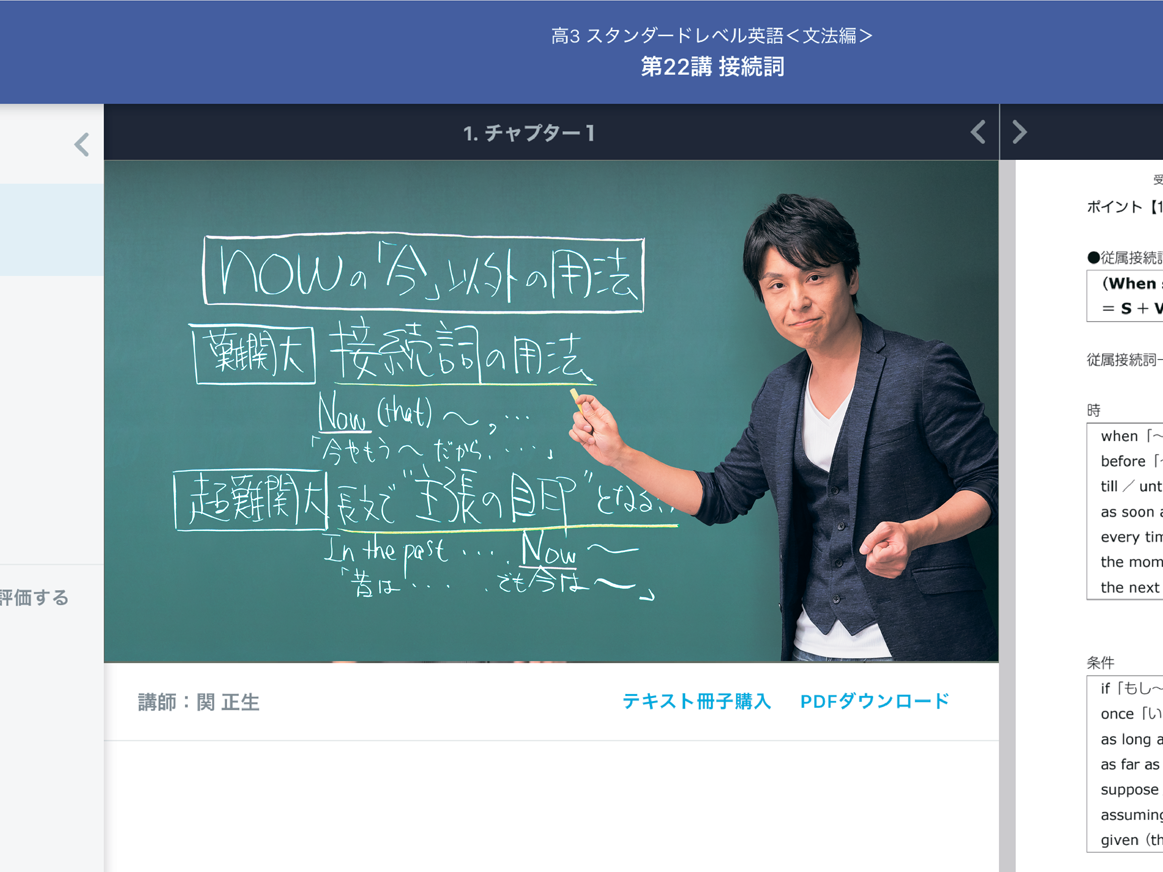教員としての原点
― 二川先生は教員になって何年になりますか。
二川 2009年からなので、今年で12年目です。ぼくの場合は中学校のときの先生が、信頼して任せてくれたことで、自分自身が変わることができたという実感があって、それから先生に憧れるようになりました。それで最初は中学の先生を目指していたんですが、大学の教育実習で小学校に行ったとき、ぼくの実習を担当してくれたのが現在の小金井市教育長の大熊雅士先生で、すぐ近くに、メディアなどにもよく出演している「ぬまっち先生」こと沼田晶弘先生もいらっしゃって。その実習で「小学校の先生って面白いなあ」と感じて、小学校の教員になりました。
でも、いざクラスを受け持つと、全然うまくいかなくて、ある年とうとう、学級崩壊を起こしてしまったんです。自分の力のなさから、子どもとの間に信頼関係が築けず、子どもたちや保護者の皆さん、同僚に大変な迷惑をかけてしまった。「二度とあんなことが起きてはいけない」という思いから、いろいろな活動を始めました。
― 学校での仕事以外に、武蔵野市で「BeYond Labo(ビヨンド・ラボ)」という活動をされていますね。
二川 学級崩壊の翌年、高校の同級生で米国UCLA(カリフォルニア大学ロサンゼルス校)で脳神経科学を勉強していた青砥瑞人という友人が帰ってきて、「教育に携わりたいから、何か一緒にやらないか」とぼくに声を掛けてくれたんです。彼は今「DAncing Einstein(ダンシング・アインシュタイン)」という人材開発や教育の会社を経営していますが、彼と半年ほどいろいろ話して、そこから自分が変わったと感じています。
BeYond Laboは勉強会で、教育関係者がさまざまな分野のキーパーソンと交流できるよう、各方面から講師を呼んでいます。新型コロナウイルスの感染が広がるまではリアルで集まっていて、2月には経済産業省で「未来の教室」という、教育関連の実証プロジェクトやEdTechの情報を発信するサイトを主導している柴田寛文さんをお招きしました。5月からは有料オンラインイベントに変更。参加費を頂き、そのお金で吉祥寺の飲食店のテイクアウトチケットと栄養ドリンクを医療現場に届けるという、「学びで吉祥寺も医療も支援しよう」プロジェクトをやりました。
コロナ禍と学校
― 今回のコロナ禍では、教育の問題が大きくクローズアップされたと思います。先生方は休校中はどうやって過ごされていたのでしょうか。
二川 ぼくはコロナの間に異動があったので、新しく自分が担任になったクラスの子どもたちの顔が全然わからなくて困りました。なにしろ新学年が始まってから、みんなに会ったのは1時間だけで、教科書を渡して「さようなら」でしたから。
休校中、学校としての最優先事項は勉強ではなく、子どもたちの生存確認でした。ちゃんと家にいるのか、元気で過ごしているのかを確かめる。世界では虐待が増えているというニュースもあったので、そういったケアも必要でした。区の方針が「電話で連絡するように」ということだったのですが、クラスが多いので、職員室の限られた電話をほかの先生と代わる代わる使って連絡を入れました。
― 世の中では「公立校はIT化やオンライン授業で遅れている」と言われがちですが、動画の配信などはされましたか。
二川 5月末の休校明けに向け、「元気に登校してくれるのを待っています」と伝える動画を作りました。区が5月初めにYouTubeに公式チャンネルを開設してくれたので、各学年の先生と校長をビデオで撮って、それをつなげて動画を作って配信しました。ただ授業の動画を作るとか、宿題の解説をするといったことはやっていません。
― 休校中、生徒の皆さんとZoomで朝会を行ったと伺いました。スムーズに実現できましたか。
二川 やはり紆余曲折があって、本当は4月中にやろうと思っていたものが、5月になりました。Zoomでの朝会については「実験的にやってみます」ということで、なんとか進めることができました。校長にiPhoneを持ってもらってZoomをつないでみたり、職員室で先生方全員のスマートフォンをZoomにつないで回って、体験してもらったりしましたね。
8月下旬に2学期の始業式があったのですが、体育館に集まれないので、それも各教室をつないでZoomでやってみました。ただ、他の学校でも同じことを考えていたようで、各校が一斉に行ったために区のサーバに負荷がかかり、映像が固まって、あまりうまくいきませんでした。
公立校といっても、置かれた状況は自治体によってさまざまです。武蔵野市と練馬区では規模も意思決定の方向性も違います。どちらの自治体も学校の現場を考えて最大限の支援をしてくれていますが、今の校長はZoom朝会のような新しい試みを応援してくれるので、とても心強く思っています。
コロナのような問題が起きたとき、学校が何もしないでいると、静かに信用を失い、いずれ誰からも期待されない存在になってしまうでしょう。その状況に応じて、何が最善かを探って試行錯誤しながら挑戦していく姿勢が学校にも求められます。
社会の変化と公立校に求められる機能
― 社会のデジタル化が進んでいますが、子どもたちはこの10年で変わってきたと感じますか。
二川 よく「昔の子どもは」とか「現代の子は」と言いますが、ぼくはそういう言い方はあまり好きじゃないんです。「子どもがスマホばかりいじっている」と言いながら、そう言う大人にとってもスマホは欠かせないものになっていますよね。結局、子どもも大人も現代という環境に適応しているんです。時代が変わり環境が変わったら、人がそれに適応して変わっていくのは当然です。ただその一方で、根底のところは変わっていないとも感じています。子どもたちは今も、素直に「学びたい」という気持ちと、純粋さを持っています。もし子どもたちが素直に育っていないとしたら、原因はそのための環境を与えていない大人のほうにあるのでしょう。
― 最近は「自己肯定感を高めよう」とか「個性を伸ばそう」といった、昔はあまり聞かなかった言葉をよく耳にします。環境の変化とともに、公教育に期待されるものも変わってきているのでしょうか。
二川 確かに書店に並ぶ教育の本のラインナップを見ても、昔とタイトルが変わってきていますね。ぼくらも多かれ少なかれ、子どもたちの個性を育てていきたいと思っています。ただ公立校でそのための仕組みを実装するのは難しい面があります。
例えば、学級崩壊したクラスを立て直してきたことで有名な、北九州市の菊池省三先生が提唱した、「ほめ言葉のシャワー」という取り組みについて。これは子どもたちに積極性、自主性を持ってもらうために、日替わりで一人ずつ教室の前に立って、クラスのほかの子たちが、その子の良いところを発表していくというものです。実は以前、試みたことがあるのですが、「授業の時間が取れなくなる」との意見があって、他の先生との合意形成ができませんでした。
教員は自分一人で教えているわけではなく、学校として、学年として指導する立場ですし、最優先はやはり授業です。いろいろやってみたいとは思っても、なかなか実践できないケースもあります。
また、公立校には、教育以外の面でも社会から期待されている機能があります。
第1は子どもを受け入れること。これは社会のインフラとしてなくてはならない機能で、「限られた時間でも、子どもを学校に託せられなくなる」ことが、世の中の親にとっていかに大変なのか、コロナ禍の3カ月間で、まざまざと見せつけられたと感じています。
第2は友達との関わりです。休校中にZoomでオンラインの朝会をやったときは、保護者の方から「友達の顔を見られて、子どもがうれしそうだった」という声が、一斉に届きました。学校がないと子どもたちは、友達との接点がなくなってしまうんですね。「ぜひ続けてほしい」と言われました。学校は人が集まるミニ社会で、友達との接し方を学ぶ場所でもあるということです。
第3は体験です。学校ではそんなに特別なことはできないですが、みんなでドッジボールをやったり、運動会でたくさんの声援の中で走ったり、学芸会でスポットライトを浴びてみんなに見てもらったり、ボランティアで清掃活動をして「ありがとう」と言ってもらったり、いろいろなことを体験しますね。
自分一人だとできないことや、進んではやろうとしないことを、学校という枠組みの中で、機会として体験してもらう。それが子どもたちにとって大切な学びとなり、そういったことにも学校の価値があると思っています。
小学校教育における新しい取り組み
― 最近、小学校でも高学年には英語やプログラミングの授業が入ってきました。子どもたちの反応はどうですか。
二川 新しい教科のいい点は、スタートがほぼ横並びだということです。6年生にもなると塾に通う子も多くなって、算数や国語の漢字や社会といった教科では、塾で勉強している子とそうでない子で、始まった時点で大きく差がついています。最初から差があると、できない子は引け目を感じてワクワク感がなくなってしまう。でも外国語や道徳、総合学習といった教科ではそういうことがないので、子どもたちも「頑張ろう」と思えるんですね。
プログラミング教育で、去年初めて「Viscuit(ビスケット)」という簡単な言語を使ったのですが、子どもたちは教わった内容をどんどん吸収して、すごく楽しそうにやっていました。それは誰もが初めてだったからだと思います。全員にとって新しいことを一緒に体験できるのは、やはりうれしいことなのでしょう。
ただ休校中に家で、自分の娘たちにビスケットをやらせてみたら、そっちは全然だめでした。うちは小3と幼稚園の年長の2人の娘がいますが、2人ともモチベーションが上がらなくて、すぐ飽きてしまうんです。そのとき「学校ってすごいな」と改めて思いました。学校では、いい意味での強制力が働いているんですね。
― 現状で、小学校のITの状況はどんな様子ですか。
二川 練馬区の場合、各教室に置かれた大型ボードはタッチで操作できるタイプで、各教室にはパソコンが1台あり、インターネットも見られます。YouTubeが自由に見られる点は、都内のほかのところより進んでいます。これまでどの学校でも、YouTubeはブロックされて見られないようになっていましたから。
ぼくは朝、子どもたちのリクエストを聞いて音楽を流すんですが、大抵はYouTubeにあるので、それを使ってできます。教材に合わせて、例えば7月に国語の教材で『森へ』というのがあって、熊が鮭を食べるシーンが出てきたので、そういう映像をYouTubeで探して、みんなで見てたりもしました。
その一方で、生徒数あたりのパソコンの配置数に関しては都内でも遅れていて、パソコン室でも生徒2人に1台ほどです。これからGIGAスクール構想に向けて、教育委員会の方々がいろいろと考え、動いてくださっているので期待しています。
学校と社会の間の壁を低くする
― 今の学校に、どんな課題があるとお考えですか。
二川 ぼくは「学校はもっと外に開いてほしい」と思っています。
痛ましい事件が続いたこともあって、今の学校のセキュリティは厳しくなっています。学校を外から見ると、職員室の中がどうなっているのかわからないし、先生の顔も見えない。学校の側も地域の人たちとつながりがない。
ぼくらは日頃、職員室で「保護者はこう考えているだろう」などと言っていますが、実際に聞いたわけではないので、本当のところはわからないんです。Zoom朝会のときも、「通信環境がない家があるのに不公平だ」といった批判がくるかもしれないと危惧していたら、実際には「応援したい」という声が多くて、それが励みになりました。保護者の皆さんのリアルな声を拾うことができてうれしかったです。
今の子どもたちには、日常的に社会と触れ合う機会がなかなかなく、関われる大人にしても、先生と親のほかは近所のおじいちゃん、おばあちゃんぐらい。できたら学校外の人たちが学校に関われる機会を増やして、子どもたちに学校でいろいろな大人と出会い、関わりながら育ってほしいと願っています。
保護者の方々の中には面白い人がたくさんいると思うんです。でも現状では知るすべがないし、こちらからはアクセスしようがありません。Zoomにしても、実は保護者の方に詳しい人がいたそうで、本当はそういう人にホストになってもらえたら、ぼくがやるよりよっぽどよかったのにと思います。
学校が外の人の力を借りようと思ったら、普段から接していないとだめなんです。ぼくは学校と社会の間の壁を低くして、学校を外の社会とつなげていきたいと思っています。
― 二川先生は自ら企業でインターン研修をされたと聞きましたが、やはり社会とつながっていくべきだという思いからですか。
二川 そのとおりですね。練馬区には採用後10年目の教師を対象に、一般企業に3日間訪問する体験型の研修を実施しています。ぼくは有給休暇を加え、今年の夏休みの5日間、企業で実務研修をしてきたんです。
受け入れてくれたのは、ソーシャルビジネスを専門とするボーダレス・ジャパンという会社です。ぼくは貧困に苦しんでいる方に職業を紹介する事業の面接現場に同席させていただいたり、ボーダレス・ジャパンを通して起業された社長の方々にお話を聞かせてもらったりして、そこで得た学びを毎日SNSで発信していきました。
― これからの学校の理想形は、どういった姿だとお考えですか。
二川 学校が地域のラーニングスペースになり、そこにいろいろな人が出入りするようになればいいな、と勝手に思い描いています。
教員と子ども、保護者の方、そして地域の人たちが対話できる場があれば、コミュニケーションができて「これに力を貸してください」と言えたり、「こんなのやりたいと考えているんですけど」「じゃ、私が話をつなげますよ」となるはず。それが実現できたら可能性の幅が広がりますよね。
そして企業と学校関係者が交流する場も創出できたらと思います。教員が研修した先の企業と学校がコラボして何かやれたら面白いし、企業の人に学校で話してもらうのも勉強になります。ぼくらは年間に1,000回ぐらい授業をしていますが、いつも同じ先生がやるより、外のいろいろな人の話を聞くほうが、子どもたちも強く印象に残るんです。
また、地域のイベントに学校を貸し出すことがあってもいいんじゃないか、と思います。学校は土日の教室の稼働率はゼロなんです。自分で勉強会をやってみたら、場所がなかなか見つからなくて、しかも高い。1時間2,000円の貸しスペースなどよりも教室のほうが全然広いですし、それが学校の収益になれば教育に役立てられる。
「ねぶくろシネマ」といって、広い場所にスクリーンを立てて映画を映し出して、星空の下で飲み食いしながら観るというイベントが今、各地で行われていますが、学校の校舎の壁などは、まさに映画を映すには絶好の場所です。そんなことが可能な場所になり得るのが、地域のハブとしての学校だと思っています。
教師の役割の変化と教育の個別最適化
二川 ぼくは今後、「子ども1人に1台の端末を用意する」という文部科学省のGIGAスクール構想が実現すると、今のティーチングは動画に取って代わられることもあると考えます。
芸人の小島よしおさんが「おっぱっぴー小学校」という、「コロナで休学している間に勉強しよう」というチャンネルを作っていて、そこに小6の算数に出てくる「線対称と点対称」という動画があります。正直ぼくには、あんなに面白い授業はできないです。ほかにもYouTube上には、素晴らしい授業の動画が本当にたくさんある。パワーポイントの資料なども、ぼくがやるよりずっと入念に準備されていて、ユーモアがあって、わかりやすくて、かつ時間も短いんです。
GIGAスクール時代には、先生は自ら授業をする代わりに「はい、じゃ、動画見てください」と言って、子どもたちをサポートすることが仕事になるかもしれない。そうなったら授業力の定義が変わってくると思っています。子どもたちが身に付けるべき力も昔とは変わってきていて、歴史年号などは覚えなくてもググれば出てくるし、知識は最低限あればいい。大切なのは必要な知識を持っている人にどうアクセスするか。究極の生きる力は、実はコミュニケーション力ではと思うようになりました。
― 1人1台の端末が支給されるようになれば、学習の進度を個別の生徒の理解度合いに合わせて最適化していくべきだ、という声もあります。公教育の先生として、どうお考えになりますか。
二川 今の一斉教育が限界にきていることは確かです。子どもたちは一人ひとり育ってきた背景が違っていて、小6にもなると、中学受験を目指している子は中学レベルの問題もできてしまうし、一方で小3、小4レベルでつまずいてしまう子もいます。そこまで差がある中で同じ内容を一律に教えていくのは、両方の子にとって不幸なことですから。
ぼくは学びというものは、その子が必要なときに身に付けばいいと考えています。
現在、九九は学校では小2で教えていて、学習指導要領によると小2の終わりまでに全部覚えることが目標となっています。でも現場で子どもたちに教えていると、学びのタイミングというのは人それぞれで、情報を吸収するのに適切なタイミングがあるのだと感じます。
何かを教えても、その子にとってそれを学ぶ時期に当てはまらないことがある。九九にしても、小2ではなく小4になって、やっと意味がわかるタイミングが来るかもしれない。最終的にわかることが第一なので、あえて小2のうちに全部覚えることを強いなくてもいい、と考えることもできるかもしれません。今は種をまいておくだけにして、どこかでその芽が出るのを待つべきなんじゃないか。教えたことがその子にとって、何かプラスになればうれしいですが、「今、これができなければいけない」と言うべきではないのでは。そう思うので、ぼくは九九で「100点を取れなければ再テスト」とは言わないようにしています。
ただ「学びの内容は人それぞれ違うべき。覚える時期も違っていいんだ」ということが認められない限りは、個別最適化は難しいでしょうね。
― もしやるとしたら、今の学年制の学校制度と、どう折り合いをつけていけばいいでしょうか。
二川 まだイメージしきれていないんですが、個人的に考えていることは、個別に学ぶのではなく、協働で学べないかということです。
新潟の上越教育大学の西川純先生は長年、「学び合い」を提唱しています。これはティーチングしないで、子どもたちだけに学習を任せてしまうものです。西川先生は「異学年学び合い」とも言っていて、6年生と1年生とか、4年生と3年生とか、違う学年の子どもたちが一緒に学びをすることで、縦で満たされることがあるということなんです。普通の学校でも、6年生と1年生が一緒に勉強するとか、学年が溶けていったら面白いなと思います。
オランダやドイツで行われている「イエナプラン教育」でも、1つのグループが2、3学年の子どもたちで構成されていて、子ども同士でわからない所を教え合います。
ただ日本は学校を出た後も縦社会で、1年上なら先輩面をしている人も多いので、学校だけを変えようとしても難しいでしょうね。
学年制を変えないまでも、いわゆるギフテッド(先天的に高い知性と倫理観を持っている人のこと)の子、学校の授業がつまらないという子たちが、授業のファシリテーション(会議等で進行を助けること)役になって、理解が不十分で授業から落ちそうな子を支えてくれるなど、みんなが同時に成長していくことができたら、理想なんですが。そういった「協働」を、教師だけじゃなくて子どもと一緒につくっていけたらいいなと思っています。
自主性と主体性
― 子どもたちと接するとき、心がけていらっしゃるのはどのようなことですか。
二川 「大人でも難しいことを子どもに強いない」ように心がけています。子どもの場合、「やる、やらない」以前に「できる、できない」ということがある。子どもたちができるのにやらない場合は、ぼくは「ちゃんとやりなよ」と言ってやらせます。しかし、できないものは仕方ないですよね。そういうときに無理は言いません。
― 最近よく「ほめて育てる」と言いますが、今の学校では先生は、あまり怒ったらいけないことになっているのでしょうか。
二川 そんなこともないです。実はぼくも今日は、大きな声で怒ってしまって。今のクラスになってから、怒るのはずっと封印してきたんですが。
叱って響くかどうかは、信頼関係次第なんです。本当にそこに信頼関係があれば、怒鳴ってもなんでもちゃんと伝わるのですが、「何言ってんだ」と思われたら、何を言っても響かないし、怒鳴ったらむしろ逆効果です。ぼくが今日声を上げたのも、「2カ月待ったからできた」という面がある。信頼関係がある程度できるまではずっと封印していて、「もう怒鳴っても大丈夫」と感じたからやった、ということでもあるんです。
一方で怒りも叱りもせず、じっと待つという接し方もあります。
自主性と主体性という言葉があります。大人のやること、上司の言うことを、言われる前に察して自分からやるのが自主性です。主体性はそうではなく、「自分はこういうことをしたい」と思って、枠組みから自分で作っていくことです。
自主性は教えることができます。ぼくが今日子どもたちを叱ったのも、怒られる前に気づいて直すという、自主的な行動を促しているわけです。
主体性は、本人が自分からそれを始めるまで、こちらは待たなければなりません。ずっと待って、その子の主体性の芽がポツッと出た瞬間をとらえなければいけない。けれども本当に根気が必要で、なかなかできません。子どもに主体性を求めるというのは、教える側にはとても難しいことが課されています。
でも主体性が芽生えるタイミングというのは、あると思うんですよ。そのために、いろいろな知識を教えてあげたり、体験させるのです。幸せな瞬間というのは、自分で自分のハンドルを握っているときに訪れるもの。できれば子どもたちに、そういう体験を味わってほしいなと思います。最終的にはその子が自分でハンドルを持って、一緒に走ってあげるのが先生だったり、親であるというのが理想でしょうね。
― それができる学校や地域社会であったらいいと。
二川 もしそうなれば、子どもは幸せだと思うんです。誰かにやらされてることって、つまらないじゃないですか。うちの娘を見ていても、宿題はやろうとしなくても、大好きなアニメの『鬼滅の刃』の図鑑を勝手に自分で作ったりしていて、そこではとても難しい漢字を書いています。それって自分がやりたくて、自分がハンドルを握っているからやれることなんですね。同じことでも、もし人から「『鬼滅の刃』のファイルを作ってきなさい」と言われたら、その途端につまらなくなってしまうでしょう。
実際にはなかなかうまくできなくて、ぼくも待っているとイライラしてしまうんですが、「本当の教育って、そういうことだよな」と思っています。