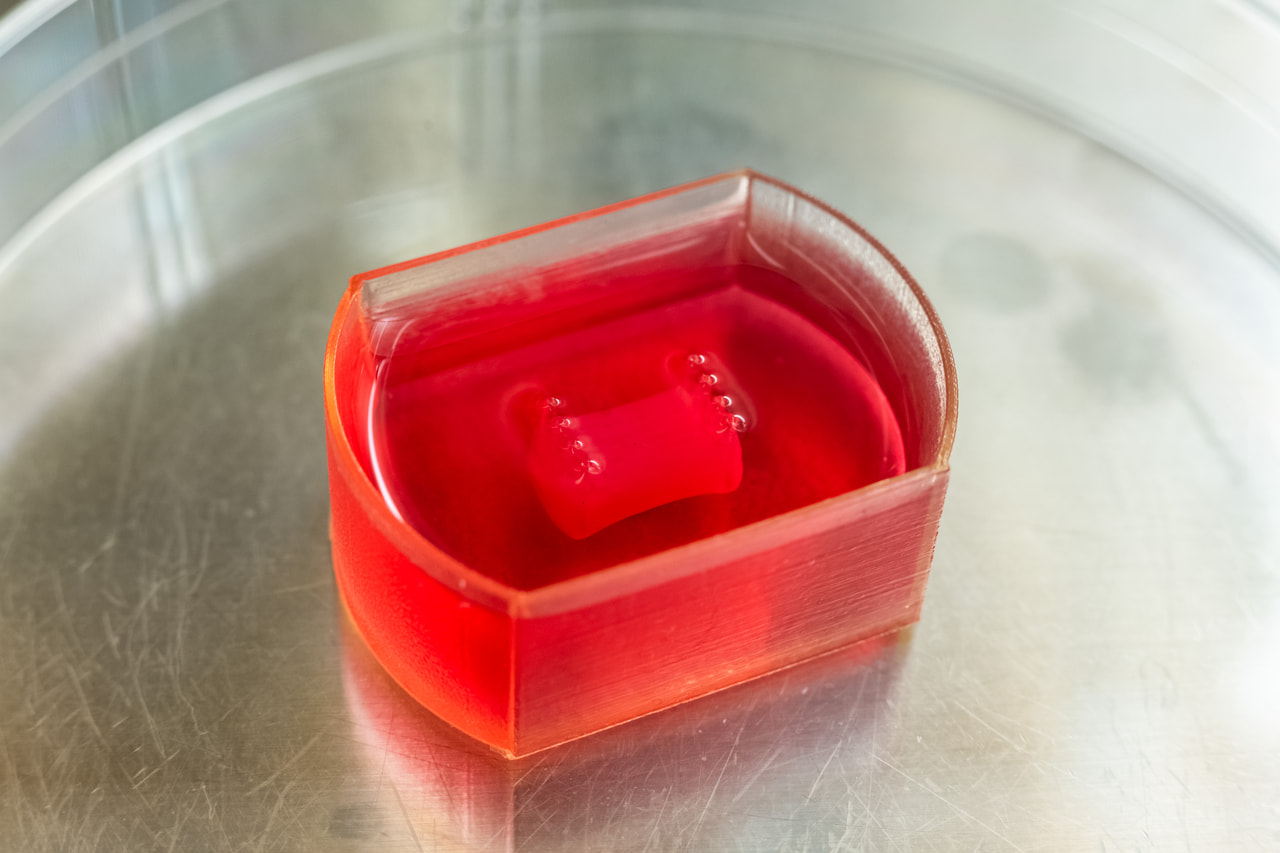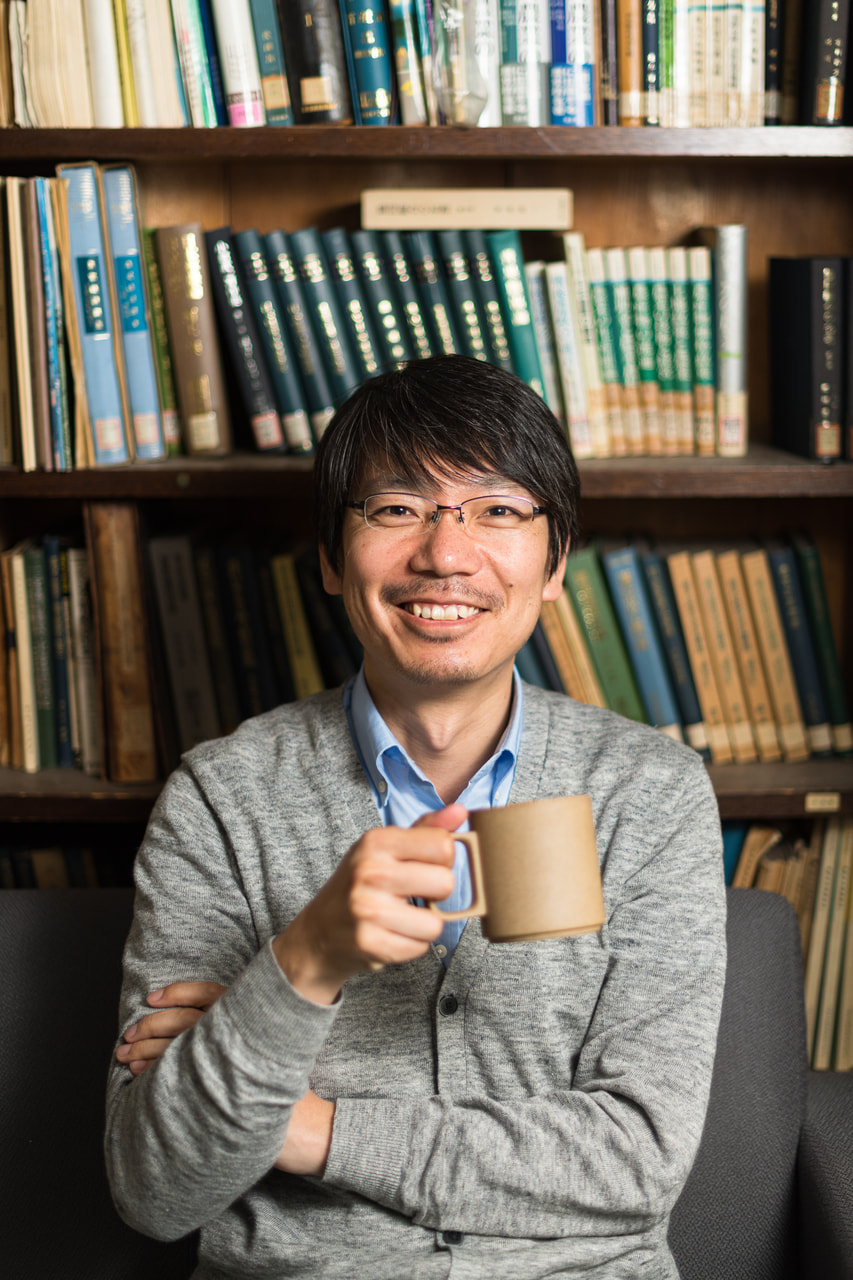農業はやりがいがない?
─東京生まれで東京農業大学を卒業されています。農業にはいつ頃から関心があったのでしょうか。
及川 私の父は岩手県出身で、実は私自身も県の文化大使・観光大使をやっています。父は私と違って寡黙なのですが、米農家である実家で育った苦労話はこんこんと聞かされていました。非常に生活が苦しかったと。そこで幼いながらに「食の根幹にある農業という産業がなぜ儲からないのか。携わる人がどうして苦しい思いをしているのか」ということが理解できず、いつか農業を学んでみたい、という気持ちが漠然とありました。ただ、実際はそれほど強いものでもなかったのですが、縁もあり農業大学に入学したのです。
そして卒業論文には「未来の農業」というテーマを選び、いろいろと調べてみました。結果、出てきたのは現在と同様、農業人口の減少、就農者の平均年齢の上昇、耕作放棄地の増加、食料自給率のいっそうの低下といったデータ。そこで改めて「あれっ、日本の農業って本当にやばいな。危機だな」と思いました。しかし、そこにようやく気づいたのも、大学がそろそろ終わる頃。自分こそ最もだめなのではと猛省し、卒業後に農業関係の仕事に就こうとしたのです。しかし当時はバブル景気崩壊の煽りを受け、大きな証券会社も破綻した就職氷河期。さらに自身の成績も芳しくなく、残念ながら希望はかないませんでした。
─卒業後、一般の会社に就職されていますが、そこから農業関連の仕事をするようになったのは、どのような経緯があったのでしょうか。
及川 大学卒業をして、主に半導体工場にガスを販売するガス会社に就職しました。そこでは新入社員100名の総代もやらせてもったり、仕事も充実して楽しかったのですが、やはりずっと農業のことが気になっていた。だから当時付き合っていた妻と結婚することになったのを機に、彼女の和歌山の実家が農家だったので、男ながら寿退社をして、妻の実家で農業を始めたのです。それがこの会社のルーツと言っていいでしょう。
実は前々から「農業の衰退は仕組みが悪いからだ」と考えていて、その仕組みについて知りたかった。そこでまずは生産現場を知る必要があると思い、和歌山県美浜町というところで、キュウリ農家を3年間やりました。楽しいこともしんどいこともいっぱいありましたが、結局、その時に一番感じたことは「農業にはもっとやりがいが必要だ」ということでした。
─農業はつまらないと思ったのですか。
及川 そうです。というのも学生時代のアルバイトやガス会社で仕事をして、なぜ楽しかったかといえばお客様から「ありがとう」「またよろしく」と言ってもらえたからです。それで「明日も頑張るぞ」と思えました。ところが当時、私がやっていた農業は農業協同組合(以下JA)に100%出荷するもの。JAにキュウリを持っていくと、引き換えに伝票を渡されて終了。伝票には何のメッセージもなく、ただ「真っすぐなキュウリが100本、曲がったキュウリが50本、合計150本」といった記載だけ。「このキュウリは誰が食べてくれるんだろう。美味しいと言ってくれるのだろうか」と、どこか手応えを感じにくい。そんなふうにお客様からの反応のない中で、モチベーションを保つのは本当に大変な仕事でした。
そしてもう一つわかったことがあります。それは一農家、一生産者という立場で、日本の農業の仕組みを変えていくのは、かなり難しいということでした。
─そこで次は青果店を開かれたんですね。
及川 はい、生産現場から仕組みを変えられないなら、販売からやってみようと思いました。そこで、ある会社と提携して、次は大阪の千里中央で青果店を1年間営みました。
やってみて何が起こったかというと、当然ながら店の利益を出したくなった。そして農家からの仕入れ値を叩いたんです。農家のときは1円でも高く売りたかったのに、お店では逆に1円でも安く仕入れたかった。自分でも「あれ?」って思いました。立場によって180度考え方が変わってくる。油と水、生産と販売が交わるところ、つまり流通を変えなければ農業は変わらないのではないか、そんなことに気づきました。また両者のコーディネートは、両方やったことがないと無理だな、とも。
そうして再び和歌山に戻り、手元資金の乏しい中、作った会社が農業総合研究所です。
─社名が研究・開発機関のようですが、込められた意図は何ですか。
及川 まずはどの業界で活躍しているかわかるように、「農業」の2文字は絶対に入れたかった。さらに皆さんに「農業とはどんな仕事?」と聞くと、多くは「農作物を生産して売る仕事」と答えるかもしれませんが、花は愛でてもらって、そして農作物はやはり食べてもらって価値が出るもの。作るところから口に入るまでを総合的にコーディネートすることが農業の使命、仕事だと私は思っています。ゆくゆくはそのように農業を総合的に研究できる会社を作りたい。そういう気持ちを込めて現在の社名にしました。
農家をメーカーに
─現在、農業総合研究所が取り組んでいる事業について教えていただけますか。
及川 全国の生産者と提携し、新鮮な農産物を都市部のスーパーマーケット(以下、スーパー)を中心に委託販売するプラットフォームを提供。店内に「農家の直売所」という直売コーナーを展開しています。
最近は大手企業も農業に参入していますが、どこも生産の領域です。「自分たちのノウハウを生かして良質なものを多く生産して、農業を活性化する」といったアプローチです。一方、生産と販売の両方を経験した私は、農業で一番変えるべきは生産でなく、流通だと思っています。農業には、いいものを作りすぎると、逆に農家が貧乏になるという「豊作貧乏」という言葉までありますから。
また一方で、DtoCやCtoCなど、生産者と消費者をダイレクトにつなぐプラットフォームも増えつつあります。しかし我々は、スーパーを中心にプラットフォームを構築することに意義を感じています。例えばスーパーでは大きな白菜を200円で売っていますが、農家さんから自分で直接仕入れたら、輸送コストだけでも1,000円ほどかかってしまう。スーパーでなぜその価格で売られているかといえば、大量流通・大量販売をしているからです。流通を考える上で、最も重要なのは物流コスト。物流コストは、大量流通・大量販売をしない限り安くならない。現在、市場を経由する野菜・果物の70%はスーパーマーケットで売られています。ということはスーパーに出口を持たない限り、物流コストも下げられないということです。
現在、農作物についてDtoC事業を手がける企業は増えましたが、コストがかかって高くつきます。少量・大量品種もなかなか難しいのではないでしょうか。
─生産者側にとって貴社と組むメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
及川 従来の流通では、生産者は自分で作る作物や値段、販売先を選べませんでした。JAが指定したものを市場に持って行き、競りにかけられて値段が決まり、市場から先はどこに行ったかわからなかったのです。さらにB級品、C級品だと引き取ってもらえず、産地で廃棄されていました。
しかし我々のプラットフォームの場合、これらを全部なくし、生産者がメーカーポジションで流通できます。つまり生産者が作りたいもの、売りたいスーパーの店舗と末端売価まで自分で決められるようになっている。だからあるスーパーの「農家の直売所」には同じキュウリでも、5本100円があれば、10本100円のものもある。また、売れないともちろんロスになってしまいますが、売れた分だけお金を支払う委託販売方式なので、B級品でもC級品でも傷物でも形が悪くても、食べられるものは出荷できるのです。
併せて各生産者がどこにどの値段で売りたいか、決めるための判断材料となるよう、毎日1回、「このお店であなたの商品がこれだけ売れています」という情報をフィードバックしています。そして自社開発した登録生産者専用ポータルサイト「農直—のうちょく」を通じて、あらゆる情報がわかるようになっている。例えばそれは、スーパーが市場から仕入れた品目の値段や他の生産者の値付け、先月・昨年など過去の自分の売り上げや全国・地域内での自分の売り上げ順などのほか、各スーパーに関する定量的な情報(立地・駐車場の有無・客層・レジの数など)や廃棄量までです。
─そのような情報があると、確かに1カ所のスーパーなどに集中し過ぎないでしょうね。
及川 そうです。加えてうちの集荷場は全国で92拠点あるのですが、そこに生産者が農産物を持ち込み、自分で金額を決めていきます。その際、人気店向けのコンテナが積み上がっていくのがわかる。それを見て、最終的にどこで競争するか、判断もできます。さらに拠点同士で、こちらの拠点でAの店への物流が多ければ、隣の拠点でのAの物量を減らすなど、需要と供給のバランスをとることもITを使って可能です。
さらに広域になると、例えば、夏が暑過ぎて作物が取れない和歌山と冬が厳しい長野とで調整を図り、冬は和歌山、夏は長野の農作物を大阪のスーパーでコーナー展開する。また和歌山名産のみかんの出荷量が増えてくると、関西だけでなく、東京まで出荷できる仕組みを作るなど、全国的な需給調整といったこともやっています。
ITと現場力の両方を重視
─さまざまな情報の収集・伝達や需給調整にITを活用されているわけですね。ITを使った仕組みづくりにシフトしたのは、何かきっかけがあったのでしょうか。
及川 普通、ITの会社というのは「こういうものがITでできたら世の中、便利だろうな」という発想で作っていくと思うのですが、我々はアナログでやっていたものを一つひとつ、IT化していっただけですね。
初めの3年間ほどは毎日、私が一人でスーパーから送られてきたファックスをもとに、生産者さんそれぞれに「今日、あなたのキュウリは3本売れました」と売り上げの報告をメールしたり、集荷拠点にスーパーでの販売価格を紙に書いて張り出したりしていました。それらを、ITを用いることで、自動配信にして、ネットに情報を集約してアクセス可能にするなど少しずつ改善を図っていったわけです。
さらに最近、まだまだ実験段階ながら一部のスーパーでは、弊社が納入した商品のパッケージに印刷した2次元バーコードをアプリで読み取って、生産者さんへメッセージを送れるようなことも始めました。最初に言ったように、農業は、生産者に「ありがとう」の声が聞こえづらい。しかしこの機能を使えば、スーパーのお客様から農家へ「昨日食べた○○さんのキュウリが美味しかった」とダイレクトに送れて「ありがとう」を伝えられる。すると農家の方のモチベーションも上がるはずです。コロナの流行以降はアプリのダウンロード数も一気に上がりました。
そうするとスーパーからは「農家とお客様が直接取引を始めるのでは?」といった声も聞こえますが、一農家の規模からすると大した金額ではありません。もしそうなったとしても、前述のように物流を考えたら我々のほうが使いやすいので、戻ってくるはず。それに何より私は、農家のモチベーションが上がることが第一なので、まずは農家とお客様をつなげることを優先してやっています。
─ITを使った仕組み作りの一方で、農家やスーパーの方と関係性を築く営業的なアプローチも大切だと思いますが、いかがですか。
及川 実は営業はほとんどしていません。生産者さん、スーパーの担当者の方々のクチコミと紹介でじわじわと広がってきた感じです。
というのも、我々の会社はITを使って特別高度なことをしているわけではありませんが、実は参入障壁がとても高い。今のところコンペティターはいないんです。あまり儲からないという理由からかもしれませんが、生産者から流通・販売まで経験して、農業の全体を見渡すことがやはり難しい。実際に全て経験したのは、多分、私ぐらいではないでしょうか。
生産者やスーパーの仕入れ担当者と話すには知識も必要です。例えば、野菜は月ごと、週ごとに出荷される品目が変わるので、ものによっては1年に1回の出荷もある。それをいちいち全部覚えるのは現実的には無理です。直営拠点に勤める社員には生産者と話しながら、少しずつ覚えるようにと言っています。
一方、スーパーには各店を回って販売支援もする店舗巡回員という社員がいます。売り場への陳列の手伝いや、時には自ら店頭販売も行う。また各店の売価を調べて生産地に送ったりもする。ITを活用しながらも、現場ではそういったかなり泥臭いコミュニケーションをとっている点を評価いただき、クチコミ等につながっているのだと思います。ここをもう少し効率的にすれば、確かに利益は上がるかもしれませんが、コアな部分なので今後も大事に続けていくつもりです。
─では今後の事業拡大のポイントはなんだと思われますか。
及川 やはり物量ですね。弊社はプラットフォーム業なので、手数料が粗利益となります。現在は手数料30〜35%、年間で約100億円の野菜と果物を流通させていますが、物量を上げるには、当たり前ですが、まず納入店舗数を増やすこと。今の約1,700店から、それを3,000店、5,000店に拡大する。そしてまた、同時に1店舗当たりの我々のシェア率を上げていく。インショップ形式の「農家の直売所」の売り上げは、現状、スーパー全体の農産物の売り上げの10%前後。残りの90%はスーパーが市場から仕入れているものです。生産者から手数料を頂いてこのプラットフォーム上で販売する以外に、生産者から農作物を買い取って、ブランディングして「100%農直」というPB商品として納入するということを始めています。このところ取扱額がとても伸びており、これも含めて各店舗でのシェアを拡大できればと思っています。さらには現段階では野菜と果物がメインですが、米や花など徐々に扱うアイテムも増やしていきたいですね。
そしてそのためには特に東京・大阪・名古屋といった都市の物流拠点の強化を図っていくつもりです。最終的にはすべての自動化を目指しています。
─現場はスーパーがメインの主戦場ということですが、他の販売チャンネルなどは考えてらっしゃいますか。
及川 弊社商品の取り扱いスーパーが増えれば、今度は飲食店への個配も視野に入ります。さらに最終的にはBtoCも可能になる。宅配など、外部の業者を介さずに、お客様の自宅まで農産物の個配送が可能となるでしょう。そこまでいけば、かなり強い企業になれると思います。
また海外の市場に向けては、グループ会社である(株)世界市場があります。いわばうちの会社の海外部門。海外に農作物を輸出するというと、高額な果物を富裕層向けに販売するようなイメージがありますが、私たちはそういう発想ではなく、やはり物流が鍵だと思っています。
例えば日本のメロンが香港で、1万円で売られていたとしても、単に物流コストがかかってその値段になっているだけあって、日本の生産者の手取りは上がらずに下がっている場合さえある。これだと本末転倒だと思うんです。だから香港の一般の方が毎日買えるぐらいの金額で流通させることが目標で、これこそ大量流通・大量販売が求められます。
20フィートから40フィートのコンテナの船便をチャーターして、鮮度がそれほど要求されないジャガイモ、タマネギ、ニンジンなどを毎日輸送。一定量売れるようになってから、徐々に鮮度が要求されるもの、高級なものを組み入れる。そうやって日本の農産物が食べられるという仕組みを構築したいですね。現在、食料自給率がゼロで、関税がない香港から始めています。ここでしっかり成功させて、シンガポールや台湾、そのほかのアジアに進出したいと思っています。
コロナ禍で実感した社会インフラとしての役割
─今回のコロナ禍では、食に関わる方々は明暗が分かれているように思います。御社の場合は、この機会をどう捉えていますか。
及川 数字だけを見ると、プラスです。外出自粛で外食が減り、健康にも気遣い、自分で料理する時間も増えたのでしょう。ご存じのように売り上げが増えたスーパーが多く、我々もその恩恵に預かっています。
しかし生産者の中には、取引先の飲食店から突然に契約停止になった方もいます。その際に、私たちのことを偶然知って農産物を出荷したところ、予想以上の値段で売れて感謝されたりもしました。
そして今回のコロナ禍で改めて感じたのは、我々のやっている仕事は水道や電気と同じ、社会インフラだということでした。全国に及ぶ食料流通の一端を担っているので、農産物の出荷も物流トラックも止めてはいけない。またスーパーにとっても、従来のように市場だけでなく、複数の納品先を確保できたということでお礼を言ってくださったところもあり、とても有り難かったですね。
もちろん、インフラを止めないためには大変気を遣いました。生産者が全国の拠点に農作物を持ち込む際には、いち早くマスクの着用と消毒を依頼。マスクのなかった方にはマスクを差し上げました。もちろん運送会社の方も全部マスクをしてくれと。そこまでやっている市場等はあまりなかったと思いますが、これは徹底しました。おかげでスタッフや生産者の中から、今まで誰一人として感染者は出ていません。
市場内外をつなぐ新しい試み
─最近、富山中央青果さん、富山銀行さんと提携されました。その座組みを拝見すると、普段は競合ともいえるJAさんも加わっています。具体的にはどのような役割分担をされているのでしょうか。
及川 改めて整理をすると、市場流通と市場外流通とありまして、市場流通というのはJAによる流通。市場外とは我々のような産直業者などです。確かに競合する部分は多いですが、外と内で分かれてやるのではなく、仲良く協働してやったほうが、効率がいいことも多い。コロナを機に、そんなふうに強く感じていたところ、富山中央青果の社長が偶然同い年だったこともあり、意気投合。今後、農業の流通を変えていく必要があるという点で意見が一致して、市場の内と外ではなく、何か面白いことを一緒にできないか、という話になりました。
そこで注目したのが情報です。市場流通は、どうしても情報の伝達が弱い。というのは共選といって、例えばトマトをJAに出荷して以降は、「和歌山のトマト」としかわからず、それ以上の情報は落ちてしまいます。すると個々の農産物の価値が曖昧になる。一方で、お客様が知りたいのは、多分、「和歌山のどなたが、どういった風土の中、どんな気持ちで作ったトマトなのか」ということだと思うのです。今回は、私たちがそこをサポートしてブランディングしましょうということ。弊社のマーケティングチームが入ってJAや生産者たちを取材。「どうやって作っているんですか」「どこに特徴があるんですか」「どんな風土なんですか」などをうかがって、情報をまとめて買ってくださるお客様に伝えられるようにしました。
一例として、富山は白ネギが有名なのですが、富山の白ネギは白い部分と緑の部分が半々。白い部分をメインに食べたい関東圏の人にとってはいささか物足りない。しかし地元では「緑の部分も食べるので、半々がちょうどいい」と取材で聞き出し、「仲良しろねぎ」とネーミングをつけてブランド化。専用パッケージを作って販売したところ、最近、非常にヒットしています。
このように私たちが入ることで、情報の伝達がうまくいき、お客様も関心を持ってくれる。結果、たくさん売れれば、生産者の販売量も上がる。全員がハッピーなので、今後は市場外だけではなく、市場と組んで、こういった取り組みを増やしていければと思っています。
─最後に今後の包括的なビジョンをお聞かせください。
及川 「豊作貧乏をなくすために市場外流通を作る」ということは、ある程度は達成できたかなと思います。生産者が自分の好きな金額で売れるので。しかし、それでも市場の相場に価格が引っ張られる部分がある。自分はトマトを1,000円で売りたいけど、市場が10円なので10円で売るしかない。合わせるしかないということがあります。
また一方で、私たちの究極の目的は、「生活者を豊かにすること」と思っています。そのために大切なのは、持続可能な農産業を実現することです。食べる人が幸せになる世界をつくるためには、農業がなくならない仕組みをつくるべきだと。そして農業生産者もまた、食べることが欠かせない生活者でもあることに間違いありません。
といったことを考えると、夢を実現するには、最終的にすべての農業流通に関わっていくことしかないと思っています。これは買収を重ねて実現するなどでは決してなく、JAさんも含めてアライアンスを組み、市場内外でトータルに、適切に、生産・流通を調整していくといったイメージです。定量的には2035年までに1兆円の農産物の流通を扱う。それぐらいまでできれば、農業を変えられるんじゃないでしょうか。
1つ例を出すと日本で年間のみかん生産料は約70万トン。一方、消費量は約50万トン。その年の収穫量が70万トン以上になると価格が下がり、50万トンになると供給量が減って価格が上がるといった状況です。でも、それ以前に20万トンの差があるのはどう考えてもおかしい。20万トンを加工に回すとか、輸出に回すとか、最初から全体を見通せている人が、結局いないのです。やはりここが農業の大きな問題だと捉えています。
そういう点では、私のように自分で農業をやって、青果店をやって、流通をやった経験を持つ人間は、おそらく世界にもいません。オンリーワンです。自分で現場をやったから、農業に関わるあらゆる人と一人称で会話ができる。なのでそれを生かして、市場も市場外も私たちが見て、全体を調整し、豊作貧乏がなくなる仕組み、生産者が誇りを持って農業に臨める仕組みを作りたいのです。
初めにお伝えしたように、今の農業だと仕事のモチベーションを上げるのはなかなか難しい。でも、先ほどの富山県の例だと、自分が作ったネギが近くのスーパーでも売ってるのがパッケージからわかる。すると子どもたちに「俺が作ったネギ、そこに売ってるだろ。これが仕事だよ」と伝えられて、仕事のモチベーションが上がったと言われ、とても嬉しかった。
自社の市場外も市場流通も一緒にやりながら、農作物を作る人も食べる人も、さまざまな面で選択の幅が広がるようオプションを増やしていく。それが私たちの目指す一つの大事なポイントじゃないのかと思います。