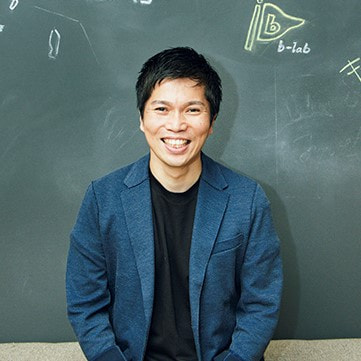―どのようなきっかけでデンソーのデジタルイノベーション室を率いることになったのでしょうか。
成迫 私は新卒で1985年にIBMに入社して、91年に伊藤忠商事に転職しました。IBMで得たI Tとソフトウエアの経験と知識があったことで、90年代半ばにインターネットが登場してからは、インターネット関連のビジネスに携わるようになり、インターネット黎明期の企業、インターネットイニシアティブや楽天、ライブドアなどと一緒に仕事をしてきました。その後、香港に駐在し、中国アジア地域でのI Tビジネスの展開を担当。一貫してIT・ソフトウエア関連の仕事をしてきていますが、システムインテグレーター(SIer)のビジネスではなく、先進的なITを使いこなしたサービスビジネスの開発と展開です。
デンソーに入社する直前は、ビットアイル・エクイニクスというデータセンターとクラウドのサービス事業者で、技術とサービスの担当役員をやっていました。そのときヘッドハンターから打診があったのが、現在のポジションです。それまでITの会社からお声がけいただく機会は多かったのですが、自動車業界は初めて。それで興味を持って話を聞かせてもらいました。
―オファーを聞いたときの第一印象はどうでしたか。
成迫 今まで私のキャリアは外資系が中心。伊藤忠にしてもグローバルにビジネスをしていて、いわゆる日本の伝統的大企業とは違うのだろうと思っていたので、純粋な日本の会社という点に、まず関心を持ちました。また製造業は未経験とはいえ、日本の製造業の強さは、現場力にあることは周知の事実。
松下幸之助さんや本田宗一郎さんの話はもちろん、IBMでは製造とは縁のない組織に所属していながら、製造業で盛んなQC活動に参画したこともあり、自分でもTOC( 制約理論)やトヨタウェイなどに興味を持って勉強していました。
現場、現地・現物にフォーカスして改善を積み重ねていく方法も頭では理解しているつもりでしたが、実際に体験してみなければわからない部分も少なくない。そういう場所に身を置いてみるのも面白いだろうなと。
―デンソーではどのような役割を求められたのですか。
成迫 デンソーは自動車部品メーカーで、インカー、つまりクルマの中のさまざまな部品をつくっています。部品はメカや、電装品などの電気系統、あるいはサーマルという冷凍機やラジエーターなど熱関係もあります。また、それらはコンピュータ制御されているので、クルマの中のマイコンや、その上で動くソフトウエアも手がけています。
ただ、コネクティッドカーの時代になると、クルマの中だけではなく、私がやっていたようなクラウドとのデータ交換の仕組みや、そのデータを使ったクラウド上で動くソフトウエアの仕組みが必要になります。このアウトカーの領域は、それまでデンソーであまりやってこなかったため、そのチームの立ち上げを担当してくれないかというオファーでした。
そういう意味では、新たにものづくりの世界に身を置くというより、私が従来やってきたフィールドをデンソーという製造業でゼロから立ち上げるに近い。私としては今までの延長線上ですから、未経験の製造業に身を置いた割には戸惑いは比較的少なかったです。
―そのミッションを担うのが、デジタルイノベーション室ですね。
成迫 このミッションを従来の組織で担うのか、新しい組織をつくるのか。既存の人材でやるのか、新たに外部から採用するのか。それを検討するために、まずは、既にアウトカーを手がけている部門や情報システム部門の方々に幅広くヒアリングをしました。その結果、従来の組織は既存の業務で忙しく、また守りのITに徹している部署や人が多かったため、攻めのITに関しては新しい組織でやることにしました。
アウトカーは、ビジネスとして新しい領域です。社内の情報システムを構築したり、インカーでマイコンのソフトウエアをつくる世界とは大きく異なります。アウトカーは、どちらかというとネット系・Web 系企業の世界に近い。そうすると技術だけでなく、スピード感もカルチャーも違います。ならば既存の組織ではないほうがいいだろうという判断です。
新しく組織をつくるなら、従来の文化やプロセスに引きずられないようにしたかったので、本社内ではなく、いわゆる出島に組織をつくることにしました。また、外部から優秀なIT 人材を採用することも考えると、本社のある愛知県より、首都圏にあったほうが採用しやすい。それも踏まえて、4年前に横浜にデジタルイノベーション室をつくりました。
―成迫さんだけでなく、ほかにも外部から新しい血を取り入れたのでしょうか?
成迫 立ち上げ時は、外から来た私と生え抜きの中堅の2人だけ。
この生え抜きの人間は、情報システム関連やインカーのビジネスをしていたのではなく、カーナビや運行管理サービスなど、クラウドやデータ処理などのビジネスを担っていた者です。
2人で始めた後は、まずは外部の優秀な人材をキャリア採用して仲間を増やし、1年ほど経った頃から社内公募で内部の人に入ってきてもらいました。キャリア採用にしても社内公募にしても、「こういうチームをつくったのでジョインしませんか」という形で募ったので、私たちのチームに入りたくて来た者ばかり。“ 会社に命令されて移った者”は一人もいません。
現在、チームは総勢35人ほどで、その7割が社内公募などで異動してきた生え抜き社員。設立当初は35歳以下の若手が中心でした。そこから4年経って年齢は上がったものの、いまだ40歳以下がメインです。デンソーの中では比較的若いチームだと思います。
日本の伝統的産業にスタートアップのやり方を移植
―新しい組織をつくる際にはどのようなことを意識しましたか。
成迫 先ほど言ったように、従来の情報システム部門や組み込みソフトウエアの部隊と違う技術、スピード感、カルチャーを持つ組織をつくろうと考えていました。
お手本にしたのは、シリコンバレーのスタートアップです。
スタートアップは、ファウンダーCEOの世界観、あるいはそれを実現する技術に共感する人たちを集めます。集めるといっても大人数ではなく、少人数。そして、その少数精鋭部隊の中で、明確な役割分担をするのではなく、チームが一丸となって新しいものを創っていく。
例えば技術者もビジネスのことを考えるし、ビジネスサイドの人間も技術のことを理解し、分け隔てなく全員でワイワイやっている。私たちもそれを参考にして人を集め、チームをつくっています。
―シリコンバレーのスタートアップ組織の強みはどこでしょうか。
成迫 デンソーも含めて日本の製造業の大企業は、とても巨大なプロジェクトを動かします。巨大なプロジェクトゆえに、それに関わるたくさんの部門が社内に存在します。
その結果、組織が階層構造になってしまう。また、プロジェクトは上流から下流まで工程が細かく分割されて、その中でそれぞれの部門が自分の仕事をしています。この構造では、現場で働く人たちはプロジェクトの中のごく一部の役割しか担うことができません。大きなプロジェクトの中で各自の裁量の範囲がとても狭くなり、結果として全体がなかなか見えにくくなってしまうのです。
それに対してスタートアップは少人数なので、1人の裁量の範囲が広いでいすよね。また、やってみてダメだったら方針転換しよう、ピボットしようというカルチャーがある。ピボットのタイミングも非常に早く、素早く動いて、それが合っているかをすぐに確認するというやり方です。
ですから、巨大プロジェクトで「構想1年、設計2年」みたいな世界観とはスピードがまったく違う。小回りが利くといいましょうか。スタートアップはそれができる組織とカルチャーを持っている。
これはシリコンバレーだけでなく、日本のIT 系スタートアップも共通している強みです。
―内部・外部問わずに人を集めると、メンバーのバックグラウンドはそれぞれ異なるかと思います。そういった方々をまとめるマネジメントのポイントはありますか。
成迫 基本的には、とにかくフラットであること。そして“ 心理的安全性”を持って双方向のコミュニケーションをとることです。
私たちがつくりたいのは、上意下達の階層型の組織や工程ごとに役割分担された体制ではなく、チームが一丸となって業務を遂行する体制です。ですから、チームがプロジェクトの業務をうまく遂行できる環境をつくることが、マネジメントの役割だと思っています。
具体的には業務を行うためのお膳立てをしたり、チームがうまくいかなければ調整して機能させたり、いわゆるサーバント型のリーダーシップですね。それを私自身は目指していますし、私たちのチームのマネジャーも意識しています。
―チーム内のコミュニケーションで心がけていることはありますか。
成迫 そこもシリコンバレーのスタートアップ流です。例えばグーグルは「HRT(ハート)の原則」を大事にしています。
HRTの原則によると、チームが行き違う理由は「謙虚でないから」「尊敬しないから」「信頼関係がないから」の3つしかありません。
逆にいうと、謙虚(Humility)、尊敬(Respect)、信頼(Trust)を大事にすれば、感情的なぶつかり合いがなくなって、本質的な議論ができるようになるというわけです。
先ほどの心理的安全性を確保できていれば、何でも言いたいことを言えるのです。私たちも何でも言い合えるカルチャーをつくりたい。そこで組織を立ち上げたときから壁に「HRTの原則」を貼って、これを大事にしようとみんなに伝えています。
―成迫さんは外資系企業にもいらっしゃいました。国によって、ものが言いやすいかどうかの違いはありますか。
成迫 私がいたIBMでは“オープンドアポリシー”を実践していました。偉い人はそれぞれ自分の部屋を持っていますが、いつ誰が入ってきてもいいようにドアを必ず開けておくというポリシーです。
新入社員と役員クラスの間には数えきれないほどの階層がありますが、当時新卒で入社した私でも、役員に話をしに行こうと思ったら行けるわけです。IBMは巨大企業でしたが、そういう文化があることを知って、すごくいい会社だなと感じていました。
このようなオープンな文化はアメリカ企業だけなのかと思っていたのですが、IBMから転職した先の伊藤忠も実に風通しがよく、若手であっても自由に意見を言い合えました。そう考えると、どこの国だからというのはあまり関係ないようです。
アメリカの会社でも、縦の階層を非常に重んじる会社はあるでしょう。香港駐在中に付き合っていた中国や東南アジアの会社もさまざまでした。結局、国に関係なく、縦の関係をどう考えるかなのかもしれません。
―その点でデンソーはいかがでしたか。
成迫 自由闊達に何でも言える会社ですよ。技術の会社であり、実際にエンジニアがいろいろなアイデアを出して、世界初の製品を幾つも生み出してきた歴史があります。下の人が意見を言えなければ、イノベーションは起きませんから。
ただ、縦を感じることもあります。特に社内の人を呼ぶときは、「A 課長」とか「B 部長」。口に出すときだけでなく、メールでもそう書く人が多い。これは製造業全般の傾向かもしれません。
一方、IBMや伊藤忠は役職とは関係なく、全員が「さん付け」でした。私たちのチームも、外部から来たIT 系の人たちは自然に「さん付け」です。少なくともチーム内ではフラットなコミュニケーションを取れるようにしたい。ですから内部から来た社員も含めて、必ず「さん付け」にしようと話しています。
事業部との混成チームでイノベーションを促進
―デジタルイノベーション室は出島の役割を果たすということでした。既存の事業部とはどのような関係で、具体的にどのようにイノベーションを生み出していくのでしょうか。
成迫 よくあると聞いているのが、威勢のいい若手を集めて社長直下でチームをつくって、「さあ、イノベーション起こせ」というケースです。
アウトカーのテクノロジーを使う私たちも、社内外から腕に自信のある人たちを集めて出島に組織をつくりました。ただ、よくあるイノベーション創出組織のように、出島のメンバーだけでプロジェクトを動かすことはほとんどなく、社内のさまざまな組織と共に混成チームを組成してプロジェクトを推進しています。
なぜそのような形にしているのかといえば、従来の組織がそれぞれにビジネスの変革に取り組んでいるからです。
例えばサーマル部門では、トラックの冷凍機や冷蔵機を遠隔監視して、故障や異常を即時検知する仕組みを構築する構想がありました。しかし、部門内部にはアウトカーやソフトウエア開発を担える人材がいなかった。
従来の組織に既にそうした課題や取り組みがあるのであれば、そこに私たちが入っていけばいい。私たちが単独で何か考えるより、そのほうがずっとイノベーションを多く、早く生み出せると思います。
具体的にプロジェクトの進め方はこうです。まず従来の組織からプロダクトオーナーを1人、アサインしてもらいます。スタートアップ企業でいうところの創業者、ファウンダーCEOですね。
プロダクトオーナーは兼務ではなく、自部門を離れ、従来の仕事を他の人に引き継ぎ、私たちの横浜の拠点に移って、専任でプロジェクトを率いてもらいます。そしてそのプロジェクトには、私たちの組織のエンジニアを数人つけます。
だいたい7人前後からなる少人数の混成チームで、ソフトウエアの開発とビジネスの開発を同時に回していくのです。
―事業部側から見ると、開発を外注するのと比べてどのような利点があるのでしょうか。
成迫 外部のITベンダーやSIerに開発を依頼する場合は、まず仕様を固めなければいけません。しかし、今はVUCAの時代で、ユーザーの要求事項を最初に明確にすることが困難です。その中で開発していこうと思えば、つくりながらどんどん変更していくアジャイル開発が最適解でしょう。
アジャイルでやるなら、プロダクトオーナーが内部のエンジニアと議論して、仕様もつくってプログラムも書く形がいい。外注ではどうしてもウォーターフォール型にせざるを得ず、素早い開発は難しいのではないでしょうか。
―事業部とデジタルイノベーション室が組んで開発して、既にリリースされた商品やサービスがあれば教えてください。
成迫 例に出した冷凍機の遠隔監視サービスは「D-FAMS」として発表されています。これはまさにサーマル部門の方がファウンダーCEOになって、私たちのエンジニアと一緒に横浜の開発ルームにこもり、スタートアップ的にソフトウエアやサービスを全部つくりました。
デジタルイノベーション室が自ら企画し、開発を推進している例としては「Misaki」が挙げられます。
これからクルマは、クルマの中で動くソフトウエアとクラウドで動くソフトウエアが密に連携して、MaaS(Mobility as a Service:サービスとしてのモビリティ)の世界観を実現していく時代に入ります。さらにその先にはスマートシティもあるでしょう。
そういったものを実現していくには、あらゆるソフトウエアをあらゆる場所で自由自在に動かせ、それらがうまく密に連携する仕掛けが必要になる。そのための基盤が「Misaki」です。
例えば、クルマの中のセンサーやカメラなどで発生したデータをクルマの中で一次処理して、それがクラウドとシームレスに連携してクラウド上で二次処理が行われ、それがまたクルマの中に戻って何らかのユーザー価値を提供する。
こういったことはすべてソフトウエアが支えるわけですが、Misakiは、そのような仕組みを自由自在につくれる基盤技術なのです。
さらに将来、エッジコンピューティングが始まって、交通インフラとクラウドの境い目をなくして、あらゆるソフトウエアがあらゆるところで走るような仕掛け―Deploy Anywhereと呼んでいますが―も必要でしょう。クラウド上でのソフトウエア実行環境の技術であるコンテナ、さらにそのコンテナを管理する「Kubernetes」という仕組みをクルマの世界にも取り込んだりしながら、現在も開発を継続しています。
―デジタルイノベーション室から発信・開発した企画は、ほかにも何かありますか。
成迫 ほかに「yuriCargo(ゆりかご)」というものもあります。これはスマートフォンをクルマとつなぐことなく、スマホ単体で安全運転を数値化して測れるアプリです。
自動車業界に携わっている以上、やはり交通事故をなくしたいというのが共通の思いです。そのためにADAS( 高度運転支援システム)や自動運転の開発もしていますが、それらが幅広く普及するにはまだ時間がかかります。
そこでそうした技術が浸透するまでの間に交通事故を少しでも減らすために、まずは個人の運転を見える化して、それによって安全運転の啓蒙をしようという狙いです。
このように私たちで企画したものもあれば、事業部側から持ち込まれたものもあります。また、事業部側からのものも、企画が詳細化する前、構想の段階で相談いただくことも少なくないですね。
構想を実現するためにどのような技術が有効なのか、エンジニアと議論をしないと良い企画にならないので。
積極的な情報発信で事業部との連携を深める
―どちら側のきっかけで始まるにせよ、連携が重要になるかと思います。事業部をうまく巻き込み、あるいは事業部にうまく巻き込まれていくために工夫していることはありますか。
成迫 連携のための制度をつくっても、うまくワークしないのではないかと思っています。
デンソーの社内には、サーマル、パワートレイン、エレクトリフィケーション、電子システム、モビリティシステム、非車載事業といった部署があります。またグループ会社には、QRコードを開発したデンソーウェーブのように、自動車とは異なる分野の事業を行う会社もある。
私たちはこのようなデンソーグループ全体のさまざまな組織と連携するのですが、そうした幅広い組織対して制度的な発想で連携する仕組みをつくっても機能しにくい気がするのです。
幅広いところに横串を刺すのに一番いいのは、現場同士が直接つながること。ただ、「直接つながって」と言っても向こうから来てくれるわけではないので、まず私たちから情報発信することを心がけています。
現在、取り組んでいることをできるだけオープンに発信すれば、「こんなことができる」「あんな事例がある」ということが伝わって、さまざまな組織の人たちが「ならば自分たちも」と気軽に相談してくれるようになる。スタートアップの企業同士もそうやってオープンイノベーションを進めていますが、同じことを内部でやっています。
―情報発信は具体的にどのようにやっていますか。
成迫 社内で有志の勉強会を草の根活動的に開催したり、社内イントラネットでさまざまな情報を発信しています。
社内SNSをやっている会社は多いと思いますが、事務局が一方的に情報を出すだけではコミュニケーションが盛り上がりません。
私たちは情報量と透明性にこだわって、プロジェクトの内容はもちろん、「技術的にこういうことで困っていたが、こうしたら解決できた」といったストーリーや、人によっては個人の日報まで全社に公開してしまいます。
さすがに人事評価は出せないですが、よほどのことがなければ基本的にはすべてオープンに透明性を持って情報公開する。その姿勢で発信していたら、ほかの部署の人たちもSNSで情報発信をしてくれたり、そこでのやり取りがきっかけでディスカッションが生まれたり、コミュニケーションが活性化してきました。
例えばyuriCargoを外部リリースの前に社内にリリースしたときは、社内のユーザーから社内SNSを通して、多くのフィードバックがありました。結果、そこでyuriCargoはスマホ単体なので、「GPSの情報が飛んでしまって走っていなかったことになっている」「スピードを出していないのにスピード違反したことになっている」などの不具合が判明。
そういった情報を社内SNSで教えてもらい、すぐ対応できるものは対応したし、すぐに解決できない問題については、ユーザーと共に回避策をディスカッションしました。コミュニケーションを密に取れたことで、アジャイルにサービスを進化させていくことができたと思います。
―事業部が気軽に相談できるように、デジタルイノベーション室と組んでやると予算的に有利になるといった仕組みはないのでしょうか。
成迫 基本的にプロジェクトは受益者負担が原則で、一緒にやれば自動的に安くなる仕組みはありません。ただ、私たちは全社のプロジェクトに関わっているので、「これなら他の部署でやっていたものを一部流用できますよ」といったアドバイスができます。流用すれば、当然、開発の時間は短くなって、コストも下がります。
ちなみに流用されるのはソフトウエアだけではありません。私たちはそれぞれのプロジェクトからノウハウを得ています。
相談してもらえれば、私たちが知っている内容はすべて出しますし、「あの部署のこの人なら知っているはず」とつなぐこともできる。また、私たちが得た情報は、社内SNSで発信していますので、結果、直接のコミュニケーションはなくても、別の部署がその情報を見て、自分たちの業務に役立てるケースも出てきました。
―デジタルイノベーション室や社内SNSが情報のハブになっているのですね。
成迫 社内SNSは、まさにその役割を果たしていますね。リアルな業務に直結する技術の話や、先ほどのノウハウの話、また困ったことやそれに対する解決策がSNS上でどんどんやり取りされていて、いいネットワークができてきたなと。
ちなみにデンソーは、ソフトウエアおよびクラウド関連の技術力を磨くために、著名な有識者の方々を技術顧問として招いています。その方々には、プロジェクトの現場でコーチしていただいたり、社内SNSでの議論に加わっていただいたりしています。
そうしたネットワークへの参加は、情報をアップデートするというだけでなく、若手社員のモチベーシュョンアップの点でも大変有効に作用しています。
のれん分けで開発スタイルを全社に展開する
―デジタルイノベーション室の今後のビジョンを教えてください。
成迫 CASEの時代は、より多くのソフトウエア人材が必要になります。そうなると、外部から獲得するだけでなく、社内の人材をソフトウエア人材として育成する必要も出てきます。ソフトウエアの世界は技術革新のスピードが速く、そして実務の力をつけるためには、座学より実践で学ぶことが大事です。私たちの組織でも、社内公募で来た人が業務を通して新しい技術に触れながら、1~2年で一人前になるように育成します。
また、自分ができるようになったら、次は先生役になって教える取り組みもしています。もちろんキャリア採用で来た人や技術顧問の方にも、人材育成面で支えてもらっています。
ただ、外から来た人に頼るだけでは組織がスケールしないのです。ソフトウエア開発者を増やすには、内部で先生をつくって次の世代を教え、そこで育った世代がさらに次の世代に教えるというネズミ算的なやり方が有効です。
―デジタルイノベーションを起こせる人材の育成を、全社的に横展開していくことは可能でしょうか。
成迫 そうしたいですね。ただ、いきなりは難しいので、まずは研修で広げているところです。新入社員研修でアジャイル開発やクラウドなどの講義は、私たちが先生役をやっています。
また、実践の場として、私たちが関与しているプロジェクトに、他の部署やグループ会社の人に参画いただくこともあります。
―デジタルイノベーション室は、スタートアップ的な仕事の進め方をしています。今後、そういった仕事のスタイルやカルチャーもデンソー全社に広げていくのでしょうか。
成迫 それもやりたいと思っています。実際、既存の組織からこちらにプロダクトオーナーが来て、我々のメンバーと一緒にプロジェクトを回してできるようになって、その人たちが自分の部署に戻り、そこで同じやり方でほかの人を巻き込んでやっていくケースも出始めています。
以前、デンソー中国のナショナルスタッフが一定期間、横浜に来て中国のためのプロジェクトをやったことがあります。横浜である程度できるようになった後に中国に戻り、今度は私たちが中国に行って彼らに対する
サポートを続け、今では中国のメンバーだけでプロジェクトを回せるようになりました。いわばのれん分けの形で、私たちのやり方が広がっています。
―今後、デジタルイノベーション室が起点となって、デンソーが変わっていくかもしれませんね。
成迫 デジタルのイノベーションを起こすには、私たちの組織を大きくするより、のれん分けでさまざまな部署に広めていくほうがいいと考えています。プロジェクトは、何よりも現地現物が大事です。
製造業にとっての現地現物は工場の生産現場ですが、サービスの現地現物はエンドユーザーであり、エンドユーザーに一番近いのは、やはり各事業部や各グループ会社なのです。現在私たちが取り組んでいるような開発ができるチームがそれぞれにあれば、デンソーはさらに進化できるのではないでしょうか。
「気がつくと、デンソーは伝統的な製造業であり、かつ最先端のソフトウエアの会社・デジタルの会社になっていた」というのが私の個人的な野望。そこに向けて人材育成とのれん分けを進めていきたいと考えています。