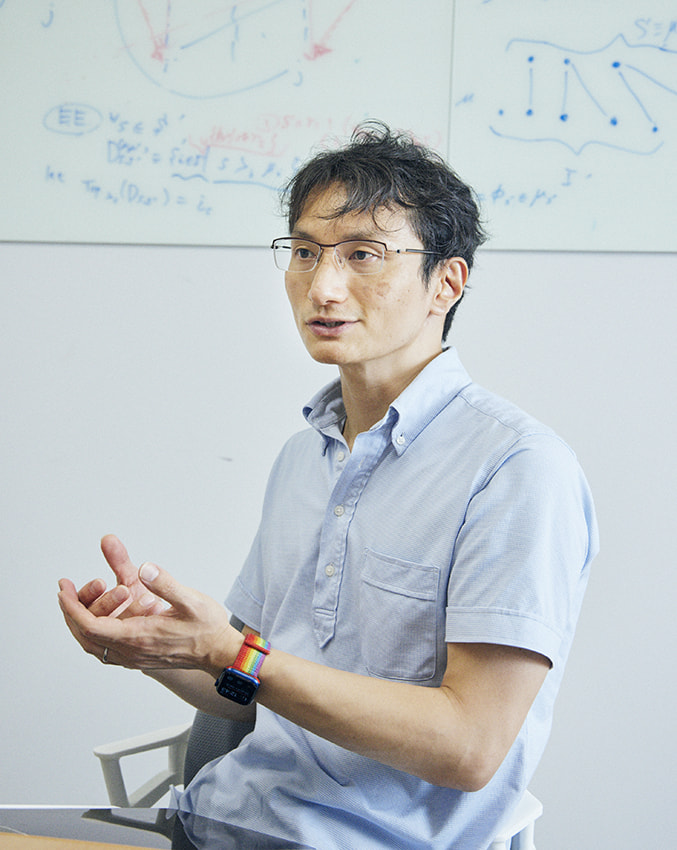隣の芝は青いのか
—原田さんがローンディールを立ち上げた経緯を教えてください。
原田 やはり自分自身が「隣の芝は青いのか」とずっと思っていたのが大きいですね。
私は2001年にラクーンという会社に入り、13年間お世話になりました。入社当初は社員が10人ぐらいで、少しずつ会社が大きくなって百数十人ぐらいのところまで勤めていたのですが、やはり愛着が増すんですよ、同じ会社でやっていると。ただ一方で、30歳を過ぎて仕事がこなせるようになってきて、自分が「今も成長できているか」と問われると自信がない。そして「外に行ったら自分は通用するのかな」とか、「自分はこの仕事を一生やっていくのだろうか」といった疑問や葛藤をずっと抱えていました。
そのときに「サッカーだとレンタル移籍がある。そういうものがビジネスでもできると面白いんじゃないかな」と妄想していたのです。しかしまだ起業するのが怖くて、結局、カカクコムへの転職を選びました。カカクコムは当時で1,000人弱の規模感の大きな組織でした。で、何となくですが、仕事が面白く感じられなくなってしまって。それは会社が良い悪いという問題ではなく、結果的に自分には1社目のほうが合っていたということ。企業文化だったり、周りが自分のことを知ってくれているといった理由だったと思うのですが、そういったことは中にいては気付けなかった。“ 離れたからこそわかった有り難さ”といった感じです。
—具体的にどのような部分で違和感を覚えたのですか。
原田 例えばカカクコムはWebのアドテック系のビジネスモデルなので、月間ユーザーが数千万人。そこに人間的な手触り感を、僕は得られなかった。多分そういった世界にも手触り感を得るタイプの脳の人もいると思いますが、僕はもう少しお客さんの近くで仕事をしたり、みんなで議論しながら進めていくのが好きだと気付きました。
そしてその自分の実体験から、漠然とずっと持っていたレンタル移籍というアイデアについて、「これを実現させよう」と起業を決めた、そんな経緯です。
—起業を決心された際の周囲の反応はどうでしたか。
原田 いろいろな方に「こんなことやろうと思うんだけど、どう思う」と聞いたら、もうみんなが「それやってみたい」と。特に興味を持ってくれたのが、大企業の方でした。大企業の30代ぐらいの方々、それこそ結婚して子どもがいて家のローンを組んだばかりで―という世代の反応が大きくて。身動きがだんだん取れなくなっていく実感がありつつ、果たして自分はこのままでいいんだろうかという課題感を持っている中で「そんな仕組みがあったらいいなあ」と共感してくれました。そして「どこに行ってみたい?」って聞くと、多くが「ベンチャー企業に行きたい」といった答えだったのです。やはり就職の際、大企業かベンチャーか、皆さんが迷った経験があるのかもしれません。そういった文脈から“ 大企業からベンチャーへ”というビジネスモデルをつくったわけです。
鳴かず飛ばずのスタート
—意見に賛同してくださった大企業の方々とのパイプはどうつくられたのですか。
原田 当時はリアルな、ベンチャーのピッチイベントなどが夜ごと随所で開催され、結構盛り上がっていた時期でした。そういう場所にベンチャー仲間を開拓しようと頻繁に出かけていくと、同時に大企業の人たちも意外と集まっていて、そこで知り合いになったのです。自分のキャリア的にはそれまで大企業の方との接点はなかったので。1年ほどの間で約2,000人の方と名刺交換をしました。
—実際に創業してからの手応えはどうでしたか。
原田 2015年に創業して最初の1年目は、すごく忙しかったのですが、契約は全然取れませんでした。「アイデアは面白い。個人としてはやってみたい」と言われるのですが、これを会社の制度として組み込むのは別の話。そこから進まない状態が長く続いていました。それが2016年に入ってから、NTT 西日本さん、NTTドコモさんなどが「試しにやってみようか」と、立て続けに導入してくださった。そうすると「あの会社がやっているなら」といった流れで、少しずつ実績が増えて今に至る、そんな状況ですね。
初期に導入してくださった会社の方々には本当に感謝しています。
「LoanDEAL」で行っていること
—では御社がやられている企業間レンタル移籍について、内容を具体的に説明いただけますか。
原田 はい、順序としてまず、行き先を本人に決めてもらいます。要は会社の出向ではないので「どこに行って何を経験するのか、自分で考えましょう」と。もちろん会社の研修でもあるので、自分がやりたいだけではなく“ 会社に貢献でき、自分にとっても意味がある”、その2つの視点が重なる部分が何かを考えていただく。しかしその前提としては、個人としてどういう意思を持っているのかが、非常に大事だと考えています。というのも特に大きな組織で仕事をしていると、「自分はこんなことがやりたい」ではなく、「会社から求められる仕事を返すのが第一」という思考に陥りやすく、自分の中に本来ある意思が埋もれてしまっていることがあります。そこで「あなたは元々何をしたいのか」を問い掛け、覆っていた皮を剥がしてあげます。そうして会社と重なる部分とずれている部分を分けて言語化していく。こうした検証のためのワークショップを約10時間、日を分けて行います。
—そこからサポートが始まるわけですね。
原田 自分が何をやりたいかがクリアになったら、今度は「どこに行きましょうか」に進みます。現在、受け入れ先として登録されているベンチャー企業は400社以上。なぜこんなに多いのかといえば、やはりベンチャー企業は、今も採用が大変なのです。日本の有名大学を出ると、コンサル以外では、まだ大手企業に行く人が多い。資金調達面の環境は随分良くなったものの、それなりの給料が出せたとしても優秀な人材が来てくれない。さらには採用しても余力がなく、十分に育てられないといった問題があります。そういうわけでこの400社も僕らがプッシュ型で営業しているというよりは、ベンチャーキャピタルさんから紹介いただいたり、受け入れてもらったほかのベンチャーから噂を聞いてとか、そういう形で自然発生的に広がっています。
—人材の受け入れ先について、登録時に審査はありますか。
原田 反社会的ではないかの確認などは行いますが、間口は狭めないようにしています。もちろん、どこでもいいわけではなく、実際には登録の前後に会社にうかがって、経営者の人材育成に対する思いや、マネジメント経験も結構大事だったりするので、そういう点を見極めて、「ここだったら安心して人を送れる」というところをつなぎます。
そしてもう一つ、移籍先で重要な要素に事業フェーズがあります。どこも社員が30人ぐらいを超えてくると、どうしても組織ばってきます。僕らが面白いなと思うのは、5人から10人ぐらいの会社。その規模だと役割分担が決まっておらず、リソースもないし、もう何でもやらなければいけない状況になる。ところがベンチャーの動向は刻々と変わるので、それも都度都度、「1年前は良かったけど今はちょっと」とか「ちょうど、とても面白いフェーズですよ」とか、社内で情報を交換し合って確認をしています。
—以前から大企業ではジョブローテーションで経験を積むという施策がありました。それとレンタル移籍とでは何が違ってくるのでしょうか。
原田 部署は役割や機能が分かれていて、人事やります、労務やりますとか、どんどん細分化されています。となると部署を異動しても、細分化された特定の業務ができるようになり、自分の機能が増えるだけです。しかしベンチャーに行くと会社の1から10まで自分で見なくてはいけない。なので機能を増やすというよりベースとなるOSを変える、マインドセットを変えることに近い。それは大きな組織の異動ではなかなか経験できません。
ただ一方で、いろいろな部署を異動してきたという経験は、ベンチャーに行くと圧倒的に役立ちます。経理の経験もあって営業もやっていた人材は、ベンチャーからすると大変価値がある。だから大企業のジョブローテーション自体は、本当は事業立ち上げの際などすごく有益なのです。しかし残念ながら、その経験を生かし切る機会が日本の会社には少ないように思います。
—皆さん、どのくらいの期間移籍されているのですか。
原田 私たちは最低6カ月から12カ月と提示をしていて、平均すると10カ月弱ぐらいですね。逆に1年以上いると元の会社への気持ちも離れてしまう場合があるので、その辺も考慮しています。
参考までに我が社のビジネスモデルをお伝えすると、移籍元・移籍先の両方からお金を頂いており、それが特徴の一つかもしれません。双方共に有益な仕組みだと理解しているので、移籍期間内に弊社が両社から頂く報酬の月額も同じ(移籍元は移籍前後の4カ月分が加わる)。人件費は元の会社の負担でもあり、ベンチャーのほうが実質負担は少ないのですが、無料となると「誰でもいいや」となりかねません。ベンチャー側も「費用がかかるなら」ということで、真剣な対応につながります。そういう中でお互いが本気度の高いプロジェクトをやっていきたいと考えています。
人の手で行われる緻密なサポート
—ご本人の意思を尊重して移籍先を決める場合、会社の意向と全く異なるケースが出てくる危惧もありますが、調整はされるのですか。
原田 基本的には「本人に選ばせましょう」を前提に導入いただいています。ただ、時々は互いの目的に大きな相違が生じることもありえるので、まず会社側で400社の中から100ぐらいに絞ってもらいます。それから本人には「この100の中から選んでもらうのはどうですか」と、そんな感じで進めます。しかし本人が希望し、会社が了承しても、今度はベンチャー側がOKかどうかは、また別の話。そこはそこで厳しく面接をしてもらうので、希望が叶わないことも普通にあります。合格率は47%ほど。でも多分、その程度のほうが健全です。受け入れ側も本気で仲間として考えているということだし、大企業から行かれる方にとっても「これは気合を入れなければ」とより熱が入るはず。面接自体からして、既にいい経験になっているかな、と感じますね。
—ちなみに希望が通らずに、他ベンチャーへの再チャレンジを諦めてしまう方もいらっしゃいましたか。
原田 今のところはいません。だいたい3社ぐらい受けると1社は成立する感触です。ただ途中のプロセスで、「この人は転職しそう」とか、「移籍元の会社に対するエンゲージメントが低いな」ということが垣間見えたり、あわよくばそのまま転職を考えているかもと思ったら、断ります。そうなってしまうと、僕らの本来の意図からして本末転倒になってしまうので。あるいはいわゆるベンチャーに適性がなさそうな人、例えば最近は珍しいですが、あくまで上から目線で物事を言うタイプとかですね。そういう学ぶスタンスが乏しいと判断された場合には、別にその人が駄目ってことではないですが、「うちの取り組みとは合わないので、申し訳ありませんが……」と率直にお伝えします。
こうしてバックヤードではかなり手間をかけています。
—確かに相互のマッチングがとても重要ですね。
原田 そうだと思います。やはり入り口でちゃんと見極めをする。そこでは「ビッグネームが欲しいからこの契約を取ろう」などと焦らず、慎重に手間をかけている自負はあります。それができるのは独立資本だからかもしれません。我が社は一応、規模的にはベンチャーですが、資金調達を外部からしておらず、自己資金だけで回している。それが一つの特徴でもあると思っています。おかげで、いつまでにどの程度売り上げを立てなければいけないというプレッシャーがない分、自分たちのポリシー、やり方を大事に貫いてこれました。
そして晴れて行き先が決まって移籍が始まると、一人一人にメンターが付き、必ず伴走していきます。行ったら行きっぱなしではなく、「週報を書く」「月に1回は1on1をやる」「月報も書く」などを課しています。なぜかというと、行った本人には学びがあるわけですが、それを周りに伝えたり、会社に戻った後に再現してもらう必要がある。そういう再現性を担保するには言語化が不可欠で、その言語化も1人ではなかなか難しいため、メンターがサポートするのです。例えば、書いてもらった週報に必ず問いを立ててフィードバックをするとか、月に1回会って対話をするとか、そういう支援をしていく。すると本人も変わっていきます。
また移籍者とメンターのやり取りは、元の会社の人たちにもCC メールで共有しているので、「あいつはこんなことで苦労しているのか」とか、いろいろなエピソードが見えてくる。すると周りも自然に応援するようになる。そういうスタンスが生まれると感じています。
重要となるメンターの存在
—メンターの役割は重大ですが、どういう方がなられるのですか。
原田 実はそこも特徴の一つなのですが、僕らの社員がやることもありますが、業務委託で副業とか、ボランティアでやっていただいているケースが多い。現在、メンターは50人ぐらいで、多様なバックグラウンドを持った方々です。例えば大企業で新規事業を実践しているとか、VC出身で今はベンチャー企業のCFOをやっているとか、あるいは自分で起業しているなど、本当にいろいろな方が集まっていますね。
また中には、自分がレンタル移籍を経験した大企業にお勤めの方もいる。自分の経験もあって「メンターをやりたい」とおっしゃってくれて、企業側も「そういうことなら」と認められ、僕らとしても「この方だったらぜひ」と協力いただいています。
「この人にはこのメンターが合いそう」とあれやこれや社内で検討を重ね、マッチアップしていきます。責任重大ですが、腕の見せ所でもあります。
さらには移籍中から移籍後のことを見据え、後の報告会で話す際に使う資料はこういうものがいいのではとか、あるいは報告会の直前になると内容を見せていただいてアドバイスもします。それぞれの会社の言葉に的確に変換をしないと伝わらないので、移籍者にはそこに気をつけて話してもらいます。
それから「スピード感が違います」とか「ベンチャーってこうでした」など、報告が単なる感想だと「そんなことみんな知ってますよ」となってしまいます。そうではなく、例えば「戻ってきてから僕はこんな仕事をアサインされていて、そこにベンチャーの経験をこういうふうに役立てています。ほかにもこんなやり方ができると思っているので、次はこうしていきたい」といった、「移籍の経験を“ 次のアクションにどう生かすか”という報告をしてください」とお願いしています。
—細かく丁寧なサポートで驚きました。単にデータ上で大企業の人材とスタートアップを結びつけているわけではないのですね。
原田 はい、そうなんです。大企業の人は移籍中に大体一度はへこみます。行くとやはり全然違う文化の中でやっているので、最初の数カ月ぐらいは結構しんどい思いをされるのです。でもそこから皆さん本当に頑張りを発揮されますね。そんな姿を見せていただくと「この人には戻ってからももっと活躍してほしい」と、やはり応援する気持ちがより強くなります。なので皆さんとは仕事を超えてお付き合いすることも多い。例えば「ちょっと相談があるんですけど」とか「資料作ったので見ていただけますか」といった連絡を気軽に頂いて、長時間喋ったりなどしていますね。
コミュニティの運営
—レンタル移籍経験者の方々のコミュニティがあると伺いました。
原田 そうですね、コミュニティ運営にも力を入れています。
現在、移籍を経験した人は累計で150人ほど。大企業とベンチャーと両方の名刺を持つこうした方々は、貴重な存在ですから、その方々に向けたイベントを月に1回ほどやっています。例えば移籍を終えた人の報告会をみんなで聞いてみようとか、もしくは外部から講師を招いて、それこそVCの人の話を聞いてみるとか、そういういろいろなパターンで、学びを深めたり、広げたりするのが目的です。移籍者にとってみると、熱が冷めないようにする機会であったり、ネットワークを広げる場だったりもします。
—さらに送り出す上司の方の会もあると伺いました。それはどういう意図からでしょうか。
原田 最終的に求められるのは「組織還元をどうするのか」ということ。企業からすると投資をしているわけなので、やはり「どうやって回収するんだ」となります。そういう中で移籍者と上司を「ピッチャーとキャッチャー」に例えると、ピッチャーばかり剛腕になって速い球を投げられるようになっても、受け止めてくれるキャッチャーがいなければ、そのスピードでは投げられません。だからキャッチャー役の上司の人たちにも視野を広げていただく必要がある。「ベンチャーにかぶれたのでは?」みたいな受け取り方だと、移籍経験者の得たものが生かせません。そこを補完するために上司の方々に向けたイベントも実施しています。
今の40代ぐらいは、ベンチャーがどんな仕事の仕方をするのか、知らない方が少なくありません。だから僕らから「ベンチャーって仕事に対して例えばこんな考え方を持っているので、過去の例からすると部下はこういうタイプになって帰ってくる。戻ったらこういった仕事の振り方がいいですよ」とか、もしくは「ベンチャー企業ってマネジメントスタイルがこうなっている。そちらの会社でも新規事業を手がける際には、そのスタイルがいいかもしれません」といったマネジメント手法のミニ勉強会みたいなものをやらせていただく。すると「確かにうちもこのままじゃいけないから、自分も変わらなきゃ」と、上司の方の変革に対するモチベーションが高まる場面を何度も目の当たりにしました。
日本社会の変化
—起業後のこの数年で何か日本の働き方が変わったな、と感じることはありますか。
原田 うちの会社の仕組みは独特なので、初めにいろいろな方に相談したときに「経営者に話に行かないと無理だよ。こういう意思決定ができるのは役員クラスじゃないと」と言われることが多かった。ところが蓋を開けてみると、ほとんど現場からの提案で企画を上げてもらっています。
例えば、京セラさんの場合、 入社4年目の人事担当者が「ほかの同世代と比べて自分は成長できているのか、外の状況も見てみたい」という課題意識をお持ちだったのですが、レンタル移籍を知り、社内に提案して導入が決まりました。そういった事例もあります。これは多分、起案をする人たちが我々に共感をしてくださっているということもそうだし、一方で、上の方々もそういう若い人たちの提案をしっかり聞こうというふうに、日本の縦社会の構造というかパワーバランスが、少し変わってきたのかなという印象はあります。
—やはり大企業の中でも変わらなきゃいけないと、問題意識が共有されてきたのでしょうか。
原田 そうだと思います。今までは会社を移るのは、かなりハードルが高いことだった。だからリスクテイクできる人にしかできなかったはずなんです。我々がその許容度を少し上げられたとすれば、一つ前進かなと思っています。企業の中にも「若手が熱い思いを持っているのだったら、やらせてみるか」みたいなところが出てきているのでしょう。
あとは役員の方などが承認してくださる背景に、自らの経験もあると思います。彼らが若い頃、1990年前後だと、まだ日本企業が海外進出したり、新規事業を始めたりで、何かに挑戦する機会に恵まれていた。「自分はいきなり海外に飛ばされて、右も左もわからない中で仕事させられたのが生きている」といった感覚を持っていらっしゃったりします。でも同様の機会を今の若手に与えられているかというと、「最近はコンプライアンスも厳しくて難しい」といった状況です。そんな中、若手から「ハードな経験をしてみたい」という人が出てきたことで、両方の気持ちが合致したのかなと思います。
—コロナ禍の影響はどうですか。
原田 昨年の今ぐらいは、さすがにそれどころじゃないということで動きが遅くなりました。ただ、今年に入ってから案件が増えてきています。これはリモートワークが日常になったり、コロナ禍で「何か不可逆な変化が起こっている」という認識が共有された結果だと考えています。いってみれば停滞していた分のリバウンドで、新しい動きが始まっている気がします。
日本らしい変革方法
—案件数が増えているのは、それだけニーズがあったということですね。改めてお伺いしますが、転職ではなく他社へのレンタル移籍をサービスにされたのは、やはりご自身の経験が大きいのでしょうか。
原田 そうですね、端的に言うと僕は戻りたかったんですよね、1社目の会社に。外に出てみて、やっぱり1社目のほうが合っていたなと実感したとき、「再びあの会社で仕事ができたら、もっといいパフォーマンスが出せるのに」と、もどかしさが残りました。そう考えると、大企業の新卒入社で育ってきた人が外を知って帰ってくる、そんなルーツを同じくすることも実は大切な気がします。明治維新もそうですが、外にいったん出た人が戻って変革を起こす、といった社会構造が元来、日本にあるのではないでしょうか。それが日本らしい変わり方なのかもしれないと思っています。
—このところ“ 働き方改革”が叫ばれる中、欧米の方法を直接的に採用しても、日本には合わずに根付かないのではという、そんな違和感が確かにありました。
原田 おっしゃるとおりです。なので僕らは「日本的な人材の流動化」を大切にしていきたい。企業の成り立ちも違うのに仕組みだけ、「シリコンバレーはこうだから日本も」と強引に押し進めるのは、どこか短絡的です。
最近、一つの会社でしか働いた経験がないことを、どこか後ろめたく語る人がいらっしゃるのですが、「全然いいじゃないか、それもかっこいいじゃん」と思うわけです。ただ、それで硬直化して視野が狭くなってしまうのはよくない。外の世界は知っていたほうがいいわけで、だから転職しなくても「一つの会社で頑張りながら、外が見られるのもいいよね」というのが、僕らが提示したいことなのです。
事業の多角化へ向けて
—今後、新しく始める事業の予定などはありますか。
原田 まず、地方自治体と新たなビジネスを始めます。今回は地方の企業を支援する試みの一つです。例えば広島であれば、地元の中堅企業の社員を、主に東京のベンチャーにレンタル移籍させ、その間の費用の半分を県が補助します、といった今までとは逆パターンの制度で声がけをいただいています。
また少し前に発表したのですが、大企業の人たちに地方の教育現場の経営再建のようなプロジェクトに携わっていただく「大人の地域みらい留学」(https://ocm.jp/)というプログラムがスタートします。これは地域・教育魅力化プラットフォーム(https://c-platform.or.jp/)という一般財団法人と一緒にやっています。ここは「高校教育から地方の持続可能性に挑戦する」といったビジョンの下、活動されている団体です。島根県の隠岐の島の海士町の高校への島留学を企画して、全国から希望者が集まり、話題になりました。同様の試みを「地域みらい留学」として全国展開していて、そのプロジェクトのコーディネーターとして大企業の方に参加いただこうと思っています。来年スタートの予定です。
創業の経緯でもお伝えしたように、元々「大企業からベンチャー」に固執したわけではありません。「一つの会社で働いている人に、別のところで働く機会を提供したい」ということのほうが大きいので、どこから出てどこに行くかは、今後も広げていきたいと思います。
あとは「outsigh(t アウトサイト)(」https://outsight.jp/)という今年の4月から始めたサービスがあります。これは週に1回1時間、いろいろなベンチャー企業が抱える戦略課題を大企業の社員の方々が聞き、それに対して解決策を考えるという実践的プログラム。異なる業界を含め、ベンチャー企業の課題に当たって発想力を鍛えることが目的で、こちらも既に約30社に研修の一環として導入いただいています。
—これからも多彩な案件について相談をされるケースが増えていきそうですね。
原田 そうですね。「日本企業の特性に合った人材流動化を進める」という軸がブレなければ、お役に立てて、自分たちも面白いと感じられるものには積極的に挑戦したいと思っています。実はうちの会社はビジョンを持たず、事業計画もありません。
ローンディールがやってることと、関わってくる人との掛け合わせで、さまざまなものが生まれればいい。僕らの仕組みを見て「大企業の変革のため」という人もいれば、「個人の働き方改革の一つ」や「ベンチャーのエコシステムになる」という人もいて、それぞれ自由に解釈をしてくださる。だから僕らが何か「これがビジョンです」というと、ほかを排除する気がしてしまう。「こんなことをやりたいんだけど」といわれて「それ、面白いね」とできる限り受け入れて一緒にやる。今はそんなスタンスでいることが、僕らにとって心地いいのです。
理想的な働く社会とは
—最後にこれから原田さんの思う働く人にとっていい社会とは、どのようなものですか。
原田 挑戦を決めた人が一歩踏み出したとき、企業や周りにいる人たちがサポートし、それが企業にとっても次の成長の種になる。そして今まで経済合理性の中で「課題があるのはわかっていてももうからないからやれない」と大企業が手をつけなかった小さな領域に取り組める機会が増えてくる。そんなふうになればいいな、と思います。このレンタル移籍もそうですが、事業規模が小さくても、誰かの人生に寄与できることはまだ沢山あるはずです。
同時にやりたいことを明確に見いだせていなくても、人の挑戦を近くで見て刺激を受ける、といったことも必要です。例えばテレビ番組で有名な起業家が紹介されても、どうしても遠すぎる気がしますが、でも同期がベンチャーに行って、あんなことをやってきたとなると「あいつがやったなら、俺も」となるのではないでしょうか。僕らはHPに「ひとりの挑戦が、あなたを変える。」と記していますが、そういう隣の人の挑戦こそ大切にしていきたい。そこから挑戦の連鎖が波紋のように広がっていけばと思っています。