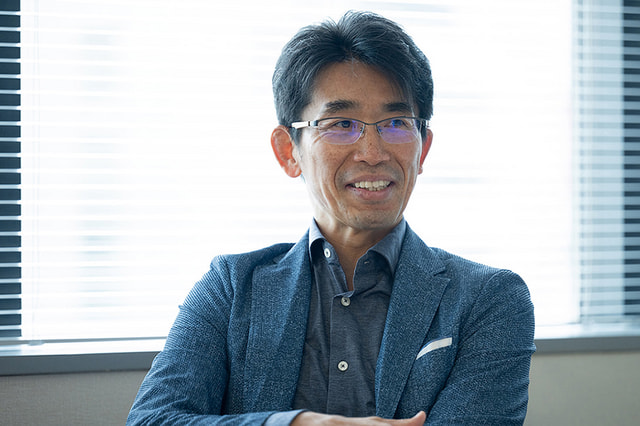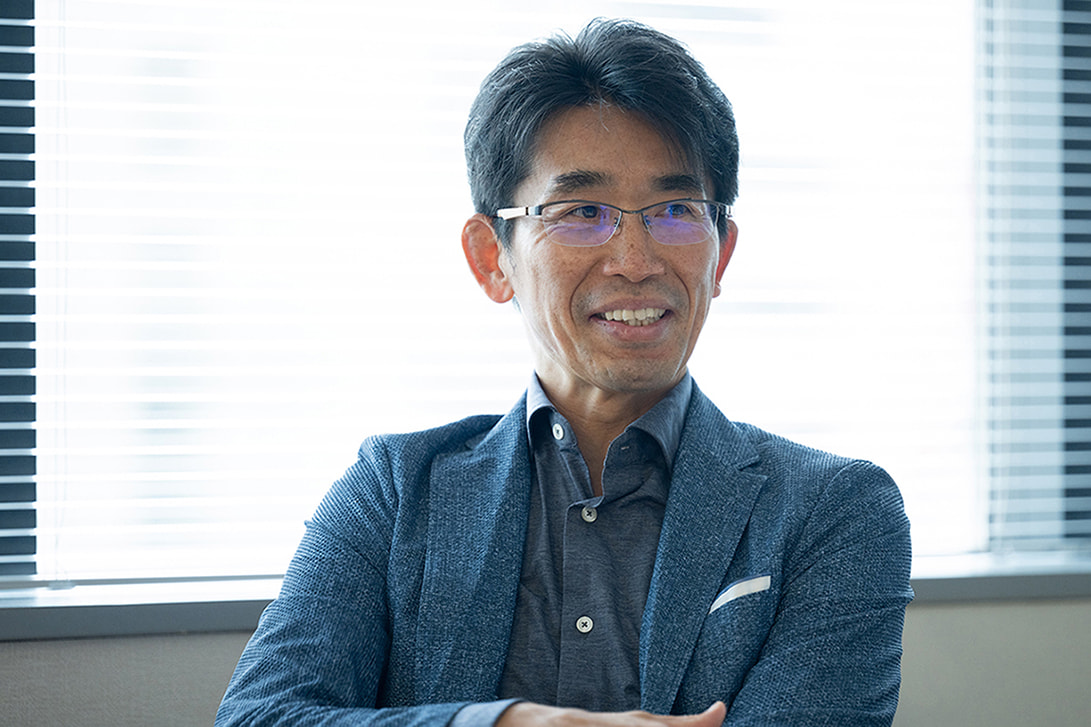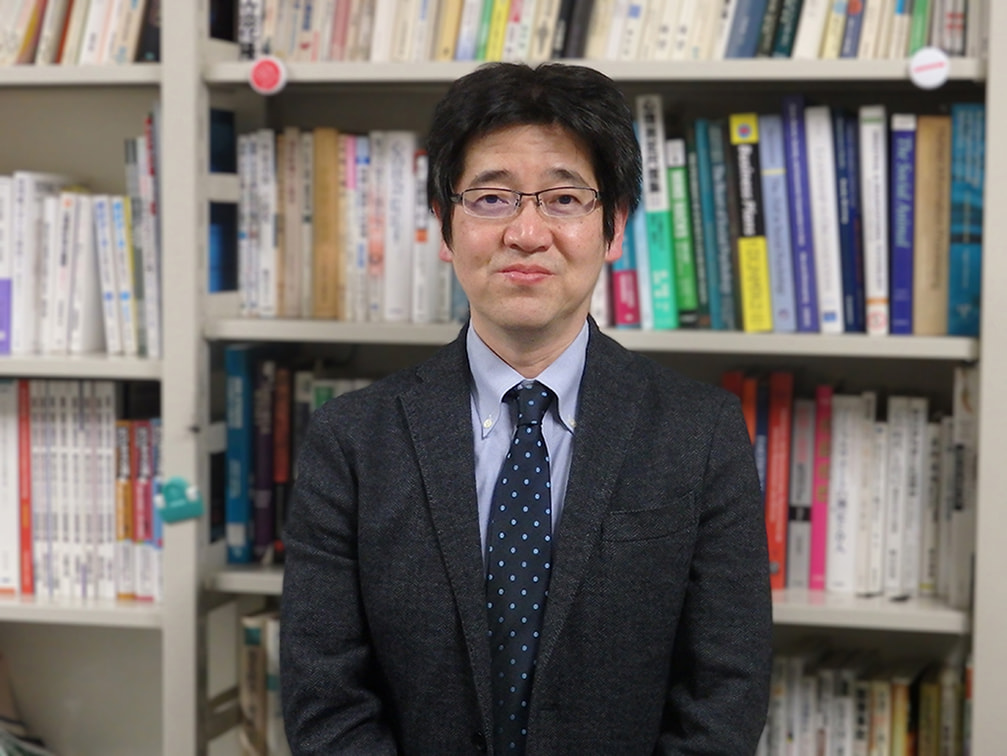目立たないポジションでも勝利に貢献できるラグビー
―中竹さんがスポーツを始めたきっかけは何ですか。元々、ラグビーには興味があったのでしょうか。
中竹 小学校1年生の頃、たまたま家の近くにラグビーチームの拠点ができ、兄がそこでラグビーを始めたのです。それで自分もやってみようか、といった自然の流れでした。もちろん、サッカーや野球のチームも家から少し離れたところにはありまして、それらがもっと近ければ、多分、どちらかを先に始めていたと思いますね。
ラグビーをやってみて良かったことは、ラグビーにはたくさんのポジションがあり、たとえ運動能力が高くなくてもチームに貢献でき、それぞれの役割を果たせる点。だから自分も続けられたのだと思います。
小・中学生のラグビーでは、まだ役割分担が曖昧なところがあり、一試合を通して一切ボールに触らないのにチームに貢献できる、といったケースもありました。俊足でもなく非力な私にとって、これは有り難かった。目覚ましい活躍はなくても、チームへの貢献が自分とメンバーで共有できて、心が満たされたのです。
―ラグビーにおける“ 目立たない貢献” とは、どのようなことですか。
中竹 野球やサッカーの場合、一人のミスで試合の勝敗が決まってしまう、ということもあります。一方、ラグビーは、個人の力に頼らなくてもいい。スター選手を活躍させるための個人の貢献を、チームで分かち合います。例えば、自分がボールに触らなくても、最後に足の速い人に、いかにいい形でパスが通るか、といったことが大切なのです。
ただ、単にボールを渡されても、すぐに捕まります。しかしモールやラックの状態でゴリゴリ押していると、相手チームが「押されてはいけない」と集まってきて、みんなで身を挺してグチャグチャになる。そのようにモールやスクラムをすることで、相手も体力を消耗し、集中力が欠けてきます。その間にエースが一人起き上がり、そこに長いパスを出すとトライに結び付くのです。
ラグビーのトライは、みんなのおかげであって一人で喜ぶものではなく、特に我々のチームは、「トライした人もガッツポーズをするな!」という指導法でした。これはすごく日本っぽくて、海外にはないと思います。しかし最近は、日本でもメディアを意識して、トライ後のガッツポーズや、ボールを投げることもありますが。
―中竹さんは、どちらのポジションでしたか。
中竹 大きく分けるとフォワードです。ラグビーのフォワードは、サッカーと逆で、ボールにあまり触らない地味なポジション。足が速い人の担当がバックスで、トライを取りに行くことが多い。私はフランカーで、スクラムの最前線の過酷なポジションではなく、将棋の駒でいうと歩のような感じですかね。歩は捨て駒ともいえますが、自分にとっては、試合の状況を客観視できる役割でした。
そして、いつも競技の素晴らしさをひしひしと感じ、リスペクトしていました。自分のように運動能力のそれほど高くない人間にも活躍できる場を用意してくれて、それを共有する雰囲気があった。もちろん試合に負けて悔しくて泣いたこともありますが、ゲームの勝敗以上に、自分のことをわかってくれる仲間が好きでした。その仲間たちとラグビーをやりたい、という気持ちで、その後の進路を選択しました。
なので「ラグビーというゲーム自体が好きだったか?」と問われると、そうとも言えなくて。プレーすると痛いし、怖いですし(笑)。今も仕事を離れると、ほとんど競技を観戦しません。これはスポーツ全般に対してそうですね。勝敗はあまり好きじゃない。このような仕事に携わる者としては、珍しいタイプだと思います。
本気で議論する場をつくった主将時代
―そして早稲田大学のラグビー部では、キャプテンを務めました。
中竹 それまでは、早稲田のラグビー部のキャプテンは、前年度の監督か、4年生のキャプテンを中心とする学生幹部が次を任命する、というルールがありました。しかし我々の代で、初めてそれを覆したのです。元々キャプテンに任命されていた者に対して、その本人と私以外の同期メンバーが、「いや、違う」とクーデターを起こしたのです。「我々は中竹でいきたい」と。
結局、卒業する4年生、OB会などと議論の結果、我々の主張が通りました。私の正直な気持ちとしては、立候補したわけではありませんが、光栄なことでした。
当初任命されていた者は、1年生からレギュラーで大活躍して、プレーヤーとしては抜群だった。だけど同期からは、「プレーがうまいからといって、本当にチームをまとめて一丸となれるのか」と疑問視されていたのです。ほとんどの体育会系チームでは、競技のうまい人間が偉い、といった文化があります。しかし当時の同期は、「お前のそういう態度に俺はついていけない」と、2軍以下の選手でも1軍に対してハッキリ物言う珍しい代でしたね。
今から思うと、エースの奴らに「うまいからといって、我々を見下し、練習を本気でやらないのは絶対に良くない」と意見するし、言われたほうも「いや、俺は努力している。だからお前は俺に負けているんだろ」と返す、わりと本音のやり取りをしていたんですね。
そんな時、私はみんなが本気で議論できる場を用意していました。1年生の頃からです。1年生のうちはグランド整備とか、遠征の準備とか、さまざまな仕事を同期で分担していたので、何か問題が起こると学年全員で考えます。ミスをしたり、先輩に怒られると、学年全体できちんと解決しないといけない。そこで全員を招集し、時にはケンカになるような話し合いをさせていました。主将というより、ファシリテーターのような感じだったかもしれません。
―運動能力とは違うところで、求められるものがあったということですね。
中竹 高校野球のチームにもありますが、補欠の子がキャプテン、というケースでしたね。
早稲田大学のラグビー部は強豪校にしては珍しく、ほとんどが一般受験で入った選手です。スポーツ推薦は学年に4、5人程度。その限られたメンバーが基本的にチームを引っ張っていきます。当初キャプテンに任命されたのも推薦枠の選手でした。でも、そういった選手には誰も口を出せない雰囲気があり、これまでのチーム運営には限界があったのです。私は、「みんなが単に推薦枠の奴らが嫌いで文句を言っているのなら、キャプテンは引き受けない。でも本気でこのチームを変えたいと思っているなら、自分も本気でやる」と心に決め、チームにとってより良い方向に向かうよう冷静に状況を見守っていました。
そんな経緯があって、主将となった後もチームのメンバーたちが話し合う場を、ひたすらつくり続けました。当時まだ20歳くらいでしたが、「どうすれば人が本気で議論するか」をかなり体得できたのではないでしょうか。
―全員が意見を出せる場をつくるのに、何か工夫したことはありますか。
中竹 例えば、声の大きい人たちばかりの議論になりそうな場合は、意見を出せそうにない人を指名しました。「明らかに不満な顔しているじゃないか。今、言えよ」と促しましたね。また事前にアジェンダを作成して、メンバーに意見を用意するよう周知することには、時間をかけました。現在なら「ファシリテーション」ということでしょうが、そういった方法論は、当時はまだ一般的ではなかった。「チームが勝つために、どうすればみんなが本気で発言し、戦うことができるか」を常に考えていたので、グランドの外での役割が多かったかもしれません。
ミーティングに集まるときには、私も含めて全員が、相当疲れている状態です。というのも練習の後、ウエイトトレーニングをして、食事も体重をキープするためのトレーニングの一つとしてこなしてと、一日中ずっとプレッシャーの中で過ごしてきているわけです。そんな状態でミーティングを設定するので、集まると全員まさにグッタリ。一刻も早く寝たいという状況ですよ。幹部のミーティングは23時から始まることも結構ありました。
ですから、そんな状況でも「自分と同じ気持ちでみんなが参加してくれて、良い議論の場にできる方法」をいつも模索していました。
社会学との出合い、そして教育関連事業へ
―それだけ力を尽くされたのに、卒業後はラグビーを離れ、海外に留学されました。
中竹 正直、「やっとラグビーを終われる」と思いました。たまたま同期に恵まれて主将を務めましたが、選手としてのレベルはそこまでではなかったし、体ももうボロボロでした。このままラグビーを続けたり、ラグビーを就職につなげよう、という気持ちはなかったですね。もちろん、OBを通して就職の話はありました。バブル崩壊直後でしたが、まだまだ体育会系の学生の需要は高かった。でも、「中竹という人間が欲しいのではなく、キャプテン経験者が欲しいのでは」と感じてしまい、就職ではなく留学を選択しました。
―留学先で何を学ばれましたか。
中竹 当初は学びたいこともなく、語学留学です。とにかく日本を離れたい、と逃げるように留学しました。ところが、いざ留学生活を始めると、ホームステイ先の家族に恵まれずに差別を受けるなど、思い描いていたものとは全く違っていた。そこから必死で勉強をし、箔をつけて日本に帰りたいと思い、オックスフォード大学を受験しました。その際に合格しそうな学問として文化人類学を選択したところ、予想以上に面白くて驚きました。
でも、オックスフォード大学には落ちました。面接が難しくて(笑)。
そこで片っ端からほかの大学を受けたところ、何と全部受かったのです。どこに行こうかと迷っていると、チューターが「あなた、本当は社会学じゃない? レスター大学が合っているわよ」と勧めてくれました。既に幾つか目ぼしい大学もあったので、その時はレスターに行くつもりはなかったのですが、「イギリスで一番カレーが美味しい街だから、食べに行くついでに受けてみれば」と言われ、旅行感覚で受験しました。ところが行ってみたら、「こんなにいい大学があるんだ!」と衝撃を受けてしまって。まだ受かってもいないのに、「やばい、俺はここに住んじゃう」と(笑)。
―なぜそんなに感激したのでしょうか。
中竹 後で知ったのですが、レスター大学は社会学のメッカ。その分野では超一流の先生方が揃っていました。そのうちの4人の教授が私の面接を担当し、全員が私のレポートのコピーを手に持って「お前がやりたいことは何だ」と真剣に問いかけ、向き合ってくれました。面接時間も1人30分ずつ。アドミニストレーターの分も合わせると、合計2時間30分もかけてくれた。1人に対する面接時間ですよ。その他の大学の場合は、大体15分で終了してしまい、心の中で「2時間もかけてここまで来たのに……」と思っていました。
レスターでそのような経験をしたので、「安易にオックスフォードに行きたがった自分は愚かだったな」と痛感しました。当時住んでいたロンドンの仲間たちからは「レスターは田舎で、ロンドンのほうが刺激があって楽しいのに」と、かなり引き留められましたが。
レスター大学では、もちろん人だけでなく、学問そのものにも惹かれました。専攻した社会学は、形態的社会学(Figurational Sociology)というもの。物事を捉える際のさまざまな視点を用いて、人や社会の価値基準の形成について研究する学問です。人がどのように事象を捉えて価値観を構築し、物事の見方を変えていくのか、を追求する面白さと難しさを学びました。メジャーな社会学を斜めから分析する学問、といった感じですかね。
その学問を通して、人の価値基準を善し悪しではなく、多様なものと受け止めることができ、自分のキャパシティが増した気がします。これが現在の私の、基本的な考えをつくっています。レスターで本当に究めたいと思える学問に出合って、博士課程まで進み、研究者になろうと思っていました。ラグビーと違って、「本当にこれは好きだな」と。
―しかし、日本に帰国されたのですね。
中竹 そう、不思議なのですが、突然「研究職で安穏と生きるのではなく、一度日本に戻って、現場で戦ってみよ」という声が聞こえた気がして。そこから就職活動を始めました。自分が働く際に重視するキーワードを打ち込んでみて就職先を検索したところ、トップに出てきたのが三菱総合研究所。シンクタンクという業界さえも知りませんでしたが、調べてみると希望にぴったりだと思い、その1社だけを受けるために帰国。結果、運よく受かりました。
レスター大学でアカデミックな勉強をした後、三菱総合研究所においては、議事録や書類の作成という、自分が苦手な実務を徹底的に鍛えられました。素晴らしい上司に恵まれ、たくさんのチャレンジもさせてもらった。会社全体の事業規模も大きく、あらゆるジャンルを手掛けている中、私が携わったのは、わずか数百万円規模の教育事業でした。ただ、だからこそ仕事は無茶苦茶面白かったです。
ITを使ったまちづくりに関連した案件では、目立った活動をされている方を全国で探してインタビューし、事例集を作るなど、自由にさせてもらいました。教育関係の依頼も次第に頂くようになったものの、会社としては収益規模が小さいため、残念ながら思うようには引き受けられなかった。ところが、当時の上司が私と2人だけのバーチャルな教育スポーツ研究チームを立ち上げ、「本業でしっかり予算を達成したら、好きにやっていいぞ」と、教育事業やスポーツの仕事をやらせてくれました。
当時、杉並区が教育改革を掲げて小中一貫校をつくり、民間人校長として藤原和博さんが運営する学校に独自のプログラムを導入する、という試みがありました。私のところにその話が来たときは社内で反対されていたのですが、「いや、これは絶対にやったほうがいい」と上司が再び上と交渉。おかげで、やりたかった教育改革に携わることができました。さらに外部からも注目され、朝日新聞の夕刊1面に載ったことがあります。
“自ら考え、動く”チームへの改革
―しかし、ラグビーの世界に再び戻られました。清宮監督から次の早稲田大学ラグビー部監督に指名されたと伺っています。
中竹 そうです。必ずしもやる気があったわけではないのですが、話を聞いてみると、「自分がやるしかないな」という気持ちになりました。ところが引き受けると、選手からは「なぜ断らなかったんだ」と詰め寄られまして(笑)。
ただ、「それはそうだな」と冷静に受け止めていました。指導経験もなく、現役時代にキャプテンを務めていた理由も曖昧で、しかもラグビーに興味がなさそうなOBがいきなり来たわけですから。前任の清宮監督は、“この人がいたら絶対に勝てる”という人。現場の本音は、「もっといい人がいたでしょ?」ですよ。
ずっと優勝していて、今年も勝ちたいと思っているチームなので、私に対してはやっぱり拒否反応です。大歓迎されるはずはないことは想定していました。
しかも私は「意見や聞きたいことがあったら直接伝えてほしい」と言い続けていたので、「なぜ監督を辞めないんですか?」と素直な質問がたくさん出ました。でも“ 文句を言わせない”といったスタンスで上から抑えても、選手たちは口をつぐむだけ。心の中で思うことは変わらず、それを怒っても仕方がない。「本気で優勝したいと思っている選手の本音だと思えば、何もひどくない」と常に自分に言い聞かせていました。
そして「文句を言っても仕方ないので、そこから頑張ろう」と伝えるためには、監督として一度しっかりとみんなの本音を聞かないといけないな、と思っていました。
―その時、監督として何を大切にされていましたか。
中竹 常に問いかけていたのは、「本気で勝ちたいか?」ということ。「本気で勝ちたいなら自分たちで頑張らないと」という気持ちに選手がなれるかどうかです。当初、私の目には「負けて惨めになりたくない」という思いのほうが強いように映っていました。
これまでずっと勝ち続けていたのに、監督が代わった途端、春のシーズンから、急に負け始めるわけですよ。試合に勝てない、練習も全然うまくいかないし、チームの雰囲気は悪い。その原因は「監督が悪いからだ」となっていた。確かにそうかもしれませんが、大切なのは、そこから「このままだと負け続けるのは自分たち」と気づき、本気で意見を言うことです。
明らかに選手同士で本音を言い合えていませんでした。スター選手に「なぜ、そんなに練習をさぼるの?」「なぜ、そんなわがままなプレーをするの?」とは誰も言えなかった。それが言えたのは、前任の清宮監督だけ。これまでは清宮さんがいたから、選手たちが言いにくいことを言わなくてもチームはうまくいっていた。
しかし、その人がいなくなり、代わりに誰かが言わないといけなくなったとき、その役割を私に求めたのです。だけどそもそも私は、ラグビーの指導に関しては素人同然。指導法がわからないので、指摘しようがないわけですよ(笑)。
―弱い部分を見つめ、口に出すのは、覚悟が要るようですが。
中竹 「清宮さんは答えを出してくれたけど、今、答えはない。一人ひとり言いたいことを存分に言って、あとは自分たちで考えるしかない」と、ひたすら言い続けていましたね。
監督1年目の夏合宿でのこと。夏合宿はチームにとってすごく重要ですが、雨が続き、練習ができなくなったことがありました。計画どおりにいかず、選手同士で不満がたまり、陰口ばかり言い合うようになっていた。
そこで練習時間を全部つぶして「お前ら、殴り合うくらい話せ」と、話し合いの場を設けたのです。その場で、激しいやり取りがありましたが、まだ私が期待した10分の1程度。でも、選手たちは慣れていなくて、衝撃を受けたと思いますよ。その時の主将が号泣していましたから。
その後もあらゆる手を使って「言いたいことを言わないとダメだし、勝てないよ」と繰り返し伝えました。「思っていることは残さず言いなさい」と促し、みんなが心の奥に溜めていたことをさらけ出せるようになると、「ようやくチームになってきたね」と声をかけました。勝利をどうつかむかよりも、選手一人ひとりのスタイルをいかに発揮するか、ということを、ひたすら毎日考え抜いていました。
求めていたのは、選手が、監督から指示を受けて動くのではなく、自分たちで考え、監督と一緒に答えを出す姿勢です。選手と監督が共に勝利を目指すという、対等な関係性。それができるようになり始めると、チームの空気も変わっていったのです。
監督に就任した2006年度の大学選手権は準優勝でしたが、選手が自ら考えて行動するチームへと変わり始め、翌年から2年連続で、大学選手権で優勝を果たしました。
“自分らしさ”を出すことで、組織が変わる
―4年間、監督を務めた後も、ラグビー指導者を続けられました。どのようなことをされていたのでしょうか。
中竹 はい、2010年度から日本ラグビーフットボール協会の初代コーチングディレクターを務めました。ラグビーの一貫指導体制をつくるために指導者のレベルを上げるのがミッションで、高校ラグビー界のコーチたちを指導しました。
高校ラグビーは、社会人や大学と比べると層が厚く、そこの指導者が変わると、日本全体のラグビー文化の改革につながります。目指したのは、トップダウンではなく、ボトムアップ型のフォロワーシップで改革を進めること。そのためには、指導者が自ら考え、動く必要がある。指導者が主体的に学び続ける姿勢を目にすると、選手たちも本気で考え、動くようになります。このようなリーダー育成は、個人の成長を組織のレベルアップや変化につなげていけるのです。
そして2014年には、企業などのリーダー育成トレーニングを行うための会社「チームボックス」を設立しました。自分が指導者と向き合ううちに、指導者を育成し、組織を変えていくという手法はスポーツだけではなく、どんな分野にでも応用できるという感覚がありました。今ではビジネスをはじめ、あらゆる分野の組織マネジメントに携わっています。
―今後、どのような活動をしていきたいと思われますか。
中竹 現在、「組織文化をどう変えるのか」に関心を持っています。組織を変えるには、目に見えてわかりやすいマネジメントのフレームワークだけでは不十分。そこからはみ出す、目に見えない部分の風土や空気から変えなくてはいけません。
そのために大事なのは“ 個の解放”です。「組織内部や周りの空気によって本音が言えない」「本当にやりたいことが見つからない」「やらされたから仕方なくやっている」と思う人たちの心を解放し、その人らしさが出せるような状況をつくることが大事。強いチームをつくるには、時代や環境に左右されない、それぞれの“ 組織らしさ”を持つことですね。それは、メンバーたちが、自分らしく振る舞うことでもあります。
このように目に見えにくい部分を「組織文化」と定義づけ、問題提起をしています。でも、個人で組織文化や空気を変えるのはなかなか難しい。あらゆる立場の人が本音の議論に加わることによって“自分たちの組織文化”を築いていけるのです。
思えば、私がラグビー時代と組織マネジメントや指導者育成を通して、常に向き合ってきたのが“ 組織そのものを変える”という取り組みだったといえるでしょう。
また、近年はコロナ禍でオンラインでのコミュニケーションが増えています。まだまだ戸惑う人が多いかもしれませんが、そのような状況下での組織文化を築くことを受け入れたほうがいい。オンラインでのコミュニケーションの場合、オンとオフのスイッチが曖昧です。だからケアすることも多い。
例えば、あえてオンラインで雑談の時間をつくるより、ミーティングの始まりにちょっと雑談する時間を取り入れるなど、自然なコミュニケーションにするための工夫も良いでしょう。オンラインにおいても、穏やかに時間が過ごせるように意識していかないと、人は変わっていかないかな、と思っています。