CG動画制作とプログラミングを独学で習得
―天野さんはカヤック入社以前には、どんな仕事をされていたのですか。
天野 僕は高校を出てすぐ、美容師になりました。通信制の大学で勉強しながら、美容の現場に入ってアシスタントを経験したのです。そして美容師として働く一方で、クラブで音楽に合わせて映像を流すVJ(ビデオジョッキー)を趣味でやっていたところ、段々と自分でも映像を作りたくなって、CGの勉強を独学で始めました。
―10年以上前は、今と違ってCGを独学するのは難しかったのではないですか。
天野 僕は「やりたい」と思ったらすぐに行動に移すタイプ。元々、映像がすごく好きで、アメリカの実験映像の父ケネス・アンガーや、人形を使ったチェコ・アニメのヤン・シュヴァンクマイエルやイジー・バルタの作品に興味を持って見たりしていました。日本の『攻殻機動隊』『サマーウォーズ』『エヴァンゲリオン』『フリクリ(FLCL)』といったアニメ、漫画ももちろんファンでした。
当時は広告映像でもいろいろな試みがなされていて、ミュージックビデオの全盛期でもありました。僕はbjörk やThe Chemical Brothersのミュージックビデオを手がけたフランスの映像作家ミシェル・ゴンドリーの作品が大好きで、「自分も同じような映像作品を作りたい」と考えたのです。
最初に2万円ぐらいのCGソフトを使ってみたのですが、扱いづらいし機能不足。「もっとすごいものが欲しい」と調べたら、世界中の映像作家や広告会社が使っている「Maya(マヤ)」というソフトがあるとわかり、すぐに買いました。当時100万円ぐらいはしたと思います。その頃は3DCGの映像制作の技術書も日本語のものは1~2冊あるかないか。買ったソフトのタブを1個ずつ押して操作を覚えていったような感じです。
何でもお金を払って買う時代でしたから、映像関連にはかなり投資しました。Roland V-5というビデオミキシングの機械が20万円ぐらいしましたし、アフターエフェクトのプラグインだけでも30~40万円分は買っています。稼いだお金はほとんどそれに使っていましたね。
僕から見ると、今の子たちはうらやましいですよ。無料で使えるソフトが結構あって、使い方などもYouTubeにいくらでも上がっていて、簡単に学ぶことができますから。
なんとか3DCGソフトが使えるようになったところで、それを仕事にしようと、独りでCG作品を1本作って人づてでいろいろな方に見せました。それが気に入ってもらえて、映像制作会社のIMAGICA Lab.で働くことになったのです。
インスタレーションに衝撃を受けて転身
―入社した映像制作会社では、どんな仕事をされたのですか。
天野 3DCG、映像クリエイターとして、ゲーム映像などを作っていました。
そうしているうちに、ユーザーの周囲の空間に映像を投影して没入感を感じてもらう、インスタレーションという手法が広がり始めました。そこで注目されたのが、ユーザーの動作を感知してそれを映像に反映させる、インタラクション(双方向性)による演出です。僕はインタラクションを可能にする技術であるフラッシュ(Flash)と出合い、それを使ってインタラクティブな映像を作るようになりました。フラッシュにはプログラミングとビジュアルワークの両方の側面があり、人の数や温度など、その場の状況を反映させることで映像を変化させられます。それに衝撃を受け、「これからはインタラクションの時代だな」と感じ、フラッシュのプログラミングもまた独学で勉強したのです。勉強してみたらこれが面白くて、インスタレーション系の仕事をメインにできる会社を探して、カヤックに移りました。
―当時のカヤックはまだ小さな会社だったと思います。大手の映像制作会社を退社して移ったのは、何が決め手だったのですか。
天野 インスタレーション系の映像制作をしている会社はチームラボ、バスキュールなど幾つかありましたが、中でもカヤックは考え方がユニークだし、雰囲気も良いと感じたのが大きいですね。「面白法人」を名乗ってサイコロを振って給料を決めたり、社員の似顔絵を描いた名刺を作ったり、会社自体も変わっていました。
入社の決定打は、カヤックの「つくる人を増やす」という経営理念に共鳴したことです。当時カヤックは「wonderfl build flash online」といって、ブラウザ上でフラッシュのソースを書いて、右側のビュアーにそのソースの内容を反映させるというWebサービスを行っており、僕もフラッシュでインタラクティブな映像を作るとき、よく利用させてもらっていました。このサービスを使えば、みんなで書いた音楽やグラフィックス、ゲームなどのソースコードを人に分け与えたり、それを上書きしてシェアしたりできます。
また同じ頃にカヤックは「こえ部」という、声だけのSNSも開設していました。これはユーザーがセリフや詩を音読して投稿し、お互いに評価し合うというサイトです。今はもうサービスを終了していますが、若いユーザーが集まっていて、その後にVTuberになった人や、声優になった人もいます。
そういう、一般の人たちにどんどんクリエイションの場を与え、クリエイターを増やしていこうというカヤックの姿勢に共感したので、面接を受けて入社しました。
初音ミクからXRの世界へ
―カヤック入社後、初音ミクを使ったアプリが人気になったと伺っています。
天野 僕が入社した2011年前後から、日本でもiPhoneが普及し始めました。カヤックでも2010年に、「スマホのGPS機能を使って、どこにでもピザを宅配できる」というiPhone用のドミノ・ピザのアプリを作っており、これが非常に好調で、第2弾を作ることになったんですね。「初音ミクがはやっているようだけど、それを使って何かやれないか」という話から始まった企画でしたが、実は皆さん、初音ミクをよく知らない。僕は初音ミクが大好きで、ニコニコ動画で“MMD 動画”をアップロードしていたぐらいだったので、「適任だろう」ということで企画から任せていただきました。MMDというのは、「MikuMikuDance(ミクミクダンス)」の略で、初音ミクなどボーカロイドキャラクターの3Dモデルを操作して、コンピュータアニメーションを作成できる無料ソフトウェアのことです。
そうした経緯で開発したのが、2013年に配信した、「Domino's App feat.初音ミク」という、ドミノ・ピザと初音ミクのiPhone向けコラボレーションアプリでした。このアプリを使うとピザの注文が初音ミク仕様の画面から行え、初音ミクバージョンの箱に入って届きます。この箱がAR(拡張現実)のマーカーになっていて、iPhone のカメラでスキャンすると、iPhoneの画面上でピザの箱がライブステージになり、初音ミクが歌って踊るのです。
初音ミクの場合、UGC(User Generated Contents)といって、曲も歌も動画もそれぞれお互いに会ったことのない人同士が作ってネット上で発表していました。ユーザークリエイティブで次々とボーカロイドコンテンツが作られていて、僕はそこに新しさを感じていました。ですからアプリも、その方向性で作ろうという話になりました。
ドミノ・ピザには約3,000人のアルバイトが登録しています。その中にはCGで絵を描ける人や、ボーカロイド曲を作れる人、初音ミクの衣装デザインやダンスの振り付けができる人もいるのではないかと考え、ドミノ・ピザ内で募集を行いました。すると狙いは当たって、最終的に13人の志願者を選出。ユーザークリエイティブを軸にして10曲のプロデュース曲を制作し、そのうち4曲を配信しました。ダンスや初音ミクの服も彼らに考えてもらったものです。
―反応はいかがでしたか。
天野 まだAR自体が珍しかったこともあり、このアプリは世界的な評判になりました。世界中でダウンロードされ、開始から1カ月でApp Store 無料ライフスタイルランキングの1位になりました。ただ、アメリカでは大勢のYouTuberがこのアプリをネタに、口からデジタルのゲロが出てくるとか、初音ミクに脳が侵食されるといった、過激でマッドな動画も続々上げていました。この頃のインターネットは今に比べて、ヘイトも含めて個人の自由な発言に寛容な部分があり、二次創作的なパロディもユーザー間で好きにやって面白がる雰囲気があったと記
憶しています。
このアプリが大ヒットしたことで、いろいろな企業からアプリやコンテンツ制作、研究開発等の依頼を頂けるようになり、ARやVR(仮想現実)の仕事を本格的に始めるきっかけにもなりました。
この「Domino's App feat. 初音ミク」のARが注目されたことで、VRゴーグル「オキュラス クエスト」開発版用のVRコンテンツをはじめ、さまざまなVR 関連の開発プロジェクトを手がけることに。結果、入社から10年で150件ほどの案件に関わることになります。この世界は技術の進化のスピードがものすごく速くて、どんどん新しいことに挑戦しているうちに、自然とXR(クロスリアリティ)分野が専門になっていきました。
米津玄師や妄想キャリブレーションのミュージックビデオでテクニカル・ディレクターを務め、その仕事の一環でVRお絵描きソフトを開発したり、『ソードアート・オンライン』のVRイベントや『宝石の国』のオープニング、『マギアレコード』の作中演出など、アニメ関係の仕事もいろいろ手がけました。

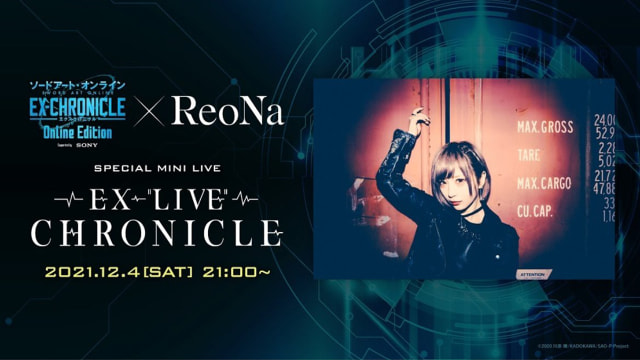

秋葉原から世界に発信していく
―「カヤックアキバスタジオ」で天野さんがCXO(Chief XR Officer)に就任された経緯について、お聞かせください。
天野 「カヤックアキバスタジオ」は元来は2006年に設立されたゲーム開発の会社でした。それがカヤックグループの傘下に入り、2018年にカヤックアキバスタジオとなって、XR、CGアニメ、オンラインコミックのWebtoonと事業範囲を広げていったのです。
僕は「カヤックアキバに専門部隊を作って、メタバースの開発を突き抜けられないか」と社長に相談され、2022年2月に立ち上がったメタバース専門部隊のリーダーとして、秋葉原に移ってきました。
―鎌倉のカヤック本社ではなく、子会社のある秋葉原をメタバースの拠点としたのはなぜですか。
天野 カヤックではかねて「地域資本主義」「職住隣接」を謳っていて、働く場所選びにはこだわりがあります。秋葉原は海外の人から見るとアメリカにおけるニューヨークのような、世界的に有名な場所です。そういう日本のベンチマークとなる場所に開発拠点を設置し、そこから世界に展開していこうという狙いがありました。
メタバースチームはARやVRなどを含むXRを担当し、プログラミングはもちろん、映像用のツールやソフトウェア開発まで自分たちでやっています。ここを強くしていくことが、今の僕のミッションです。
―天野さんは「一般社団法人Metaverse Japan」や「日経メタバースコンソーシアム・未来委員会」でアドバイザーをされたり、 経済産業省の「Web3.0時代におけるクリエイターエコノミーの創出に係る調査事業」のメンバーにもなっていますね。
天野 僕は現在、大きく3つの仕事をしていて、一つはカヤックアキバでやっている、XR 関連の業務ですね。
もう一つ、企業の方がデジタルサービスを開発する際の相談を受けています。「こういうアプリを作りたい」という依頼があれば、黒子として開発のお手伝いもしますし、レポートを上げ、「資料を作って」といったコンサルティングの仕事もやっています。
3つ目が官庁や公共団体のアドバイザリーに入ったり、シンポジウムなどに参加して、クリエイター代表として社会に問題提起をすることです。例えばVRでコンテンツを展開するとき、IPの権利保有者との関係が面倒で、あまり攻めたことができなかったりします。2Dアニメを3D 化するとゲーム化権や声優さんの声の権利ともぶつかることがある。そういう複雑な事情を整理できれば、メタバースにしてももっと可能性が広がってくるでしょう。
そういった公的な法制度の整備を行う中で、僕に声をかけてくれる人がいます。経産省では「バーチャル空間についての法律面をどう見ていくか」という視点から、市場調査や実証実験を行っています。その中で僕は現場の声をぶつけていく立場で、求められているのはこれまでの経験値。みんなの抱えている課題を、どうすくい上げて伝えていくかを考えています。
Web3とは“個人が自由を取り戻す”戦い
―天野さんはカヤックに入社して10年以上になるわけですが、時代の変化を感じますか?
天野 強く感じています。僕がカヤックに入社した2011年から12年にかけ、TwitterなどからSNS文化が広がり、「Web2.0」と騒がれるようになりました。それからこの10年でさまざまな情報が簡単に手に入るようになり、表現すること自体も非常に簡単になりました。
XRの技術を学ぶときも、基本はインターネットで調べています。今では新しい技術が開発されるたびに企業から声をかけてもらえるようになってきましたが、企業のレポートや大学教授の論文もWebサイトで読めますし、専門家がSNSやブログで個人で発信もしているので、フォローして情報を得ています。その意味では、昔に比べて情報格差は格段に少なくなったと感じます。
―クリエイターエコノミーやユーザークリエイティブの垣根も低くなったのでしょうか?
天野 そう思います。僕はそれを加速するためにカヤックに入ったようなもので、入社してからは常に「つくる人を増やすこと」を意識していました。
間口が広がったことにより、コンテンツ全体のクオリティも上がってきたとは思うのですが、一方で均一化が進んでいる印象もある。僕もあまり偉そうなことは言えないのですが、「これはすごい」というものはあっても、「これまで見たことがない」という作品が少ないのです。
あらゆる情報が簡単に手に入り、制作のためのソフトも無料になっている。個人で簡単に発表できて、その受け皿もある。これだけ土壌が豊かになったのだから、それを土台に大きくジャンプするクリエイターがどんどん出てくるかと思っていたら、それほどではなかった。もちろん中には突き抜けたコンテンツもあるのですが、全体としてはそうした作品の比率は前と同じか、むしろ減っている気もしています。
―今、Web3が注目されていますが、過去を振り返ると、Web2.0ではクリエイターエコノミーの動きが出てきた半面、GAFAMをはじめ大企業に多くのリソースが集中し、成果も吸い取られてしまった印象があります。
天野 おっしゃる通りで、僕は個人的にWeb3は、Web1.0からWeb2.0に進んだことで難しくなった個人の自由をもう一度取り戻すための“ 新たな戦い”と捉えています。
インターネット誕生以前は、多くの人が特定のメディアからしか情報を入手できませんでした。しかも情報は一方通行で、雑誌やテレビで情報を受け止めても、一般の人々はそれにリアクションすることができなかった。新聞やテレビを通じて発言が伝えられ、一部の偉い人たちにしか発言権がなかったわけです。結果、偏った思想が広がり、最終的に戦争に至ってしまうこともあった。
インターネットはそもそも、そうした時代背景の下で、個人が自由に発言できるインフラとして構想された歴史があります。しかし2000年以降、インターネットもビジネスの舞台として、いろいろな試みが企業主体で行われるようになりました。
Web2.0が始まった時点では、まだインターネットにつながったり、そこで何かしたりするのが難しい面もありました。そこを「もっと便利に、もっと自由に」と進めていくうちに、気づくと“ 大企業主体のSNS”という、本来目指したのとは違う方向に行ってしまった。結果として情報が屈折し、正しく伝えられていないという状況が起きていると感じます。
僕は情報が不均一になったり、規制されて自由に得られなくなってしまうのが嫌で、ブロックチェーンを使ってP2P(Peer to Peer /ピア・ツー・ピア:ネットワークにつながれたコンピュータ同士が、サーバを介さずに通信すること)で創作活動をやっていければ面白いと考えたのです。
―Web3は本来あるべき形で展開されそうでしょうか。
天野 Web3で個人間で情報や経済価値を交換していくためのインフラとなるのが、ブロックチェーンの技術です。しかし現状、ブロックチェーンもかつてのWinny(ウィニー)のようになりつつあると思います。 Winnyはファイルの共有に中央サーバを必要としないP2Pのファイル共有ソフトで、2002年頃から「2ちゃんねる」を舞台に開発されたといわれており、技術そのものは優れたものでした。しかし、結果としてそれを使って著作権を侵害したファイル交換が大量に行われるようになり、既存の音楽や映像コンテンツのエコノミーが崩壊してしまう事態に至りました。そこには、開発者の理念と利用する人たちの目的の間に乖離があったと思います。
ブロックチェーンは既存の中央集権的な制度を根本から取り払う力を持っており、本来はWeb1.0と2.0で実現できなかった“ 個人の自由”という課題を解決するための技術といえます。しかし現在のNFTでは、有名なクリエイターの作品を手に入れ、それをオークションに出して儲けるといったことが横行しています。デジタル作品そのものの価値ではなく、違法アップロードや贋作など意図しない形で市場価値が決まってしまう。クリエイターはそういうマーケットには作品を出したくないと考えますから、このままではNFTアートのマーケットも伸びなくなるでしょう。
同時に現状の仕組みにも問題があります。「NFTは唯一無二のもの」と言いながら、ネット上のイラストやアバターをローカルPCにダウンロードして、それをちょっといじって「自分の作品です」と言って出すようなことができてしまう。証明書とデータを紐づけるだけではそのような行為を止めるのは難しく、NFTをはじめとしたクリエイターエコノミーも崩壊してしまいます。
デジタルでお金儲けすること自体は、僕は別に構わないと思っています。ただお金儲けが先行しすぎてしまうと、本来のアートやクリエイターのあり方が歪められてしまうということです。
遊びと労働に境はない
―カヤックでは理念として「遊びと労働の境界線をなくす」を掲げています。とりわけ天野さんはカヤックのサイトで、「『24時間遊び24時間働く』を体現するクリエイター」と紹介されていますが、それは具体的にはどのようなイメージなのですか。
天野 僕や僕の父親の時代は「労働は苦しいもの」でも良いという捉え方が強かったと思います。苦しいものであれば社員が「会社に行きたくない」と感じるのは、当たり前のことですよね。
僕は全ての労働はものづくりだと考えています。そして、ものづくりは本来、楽しいからやるもの。僕の周りでは皆「楽しいな」と思いながらコンテンツを作っていますし、そういう気持ちを阻害するような要素はなるべくなくそうというのが、カヤックの考え方です。作業が大変だから苦しいということはあっても、好きでもないものを、「嫌だ、嫌だ」と思いながら作るということを推奨していません。
それに加えてカヤックは、「何をするかよりも誰とするか」を重要としています。一緒に働いていて楽しいと思える仲間たちと仕事していきたいと考えているので「会社に行きたくない」などと感じることは少ないのではないでしょうか。仲間や後輩を見ていても、「作るという行為は“ 好き”の先にあるもの」と常々感じます。自由な発想、子どものような発想が生まれてくるのは、作り手の“ 楽しい”という感覚が優先されている結果でしょう。

―親としての感覚だと、例えば子どもが楽しいからとゲームなどデジタル世界にばかりにハマっていると、「大丈夫かな」という懸念を抱いてしまいます。今後はそういう感覚も変わっていくのでしょうか。
天野 「子どもがデジタルに囲まれていると不安になる」というのは、偏った考え方だと思います。eスポーツやボカロ曲の制作など、少し前まで皆が遊びでやっていたことが仕事に変わるといった事例は続々と出てきていますし、今後もそれは続くでしょう。僕もかつて対価なしで創作活動をしていましたが、それはすごく楽しいことでした。
何かを作ることがビジネスに変わっていくクリエイターエコノミーは、インターネット上における革命的な出来事だったと思います。フィジカルな世界では不必要だったり役に立たなかったりすることが、新しい世界では何よりも価値のあることだと評価されるようになるかもしれません。
僕は仕事と同じように勉強にも、「好きなものをくっつけてやること」が大事だと思っています。僕の息子はポケモンが大好きで、2、3歳ぐらいからNintendo Switchやボードゲームをやっていましたが、数字や簡単な計算は、ポケモンをやって覚えていったところがあります。例えばモンスターのダメージは、元の体力からヒットポイントを引いていく引き算ですよね。文字に関しても「キャラクターの言葉を読みたい」という動機から、ひらがなやカタカナを覚えていきました。
この“ 学び”の過程からポケモンを抜いてしまって、数字は数字、文字は文字として、それだけ独立させて覚えさせようとしたら、子どもにとっては何のために数字や文字を覚えなければならないのか、わかりません。それでは学ぶことが苦痛になってしまいます。
自主的な学びには、好きなものをくっつけてやること。その意味ではデジタルとアナログに大きな差はない。ただ、今はいろいろな楽しいもの、面白いものがデジタルで完結するようになっています。
僕が子どもの頃のおもちゃは、キャラクターグッズに代表される“デバイス・ファースト”でした。しかし、今は漫画やアニメのキャラクターも、ゲームなどデジタルコンテンツの形で展開されています。その意味では「学びのための面白さ」もデジタルコンテンツに詰まっています。僕の場合はインスタレーション
がそうで、サイン、コサインで図形が動くことを目でわかる形で体験して、初めて「数学やプログラミングってすごいな」と思って調べていくうちに、「楽しい。もっとやりたい」となって、独学でプログラミングを身につけました。
―好きなことを追求していけば、それが仕事になるということですか。
天野 教育に関していえば“ 独学する力”が大事だと考えています。
僕は大学に通っていません。高校を出て働きながら、3DCGもプログラムも独学で身につけました。自分の子どもにも独学する力をつけてほしいと思っています。ゲームをやるのでも、ただプレーを楽しむフェイズから、「どうしてこれが動くんだろう」「どうしたらうまくなれるんだろう」というフェイズに移ってい
けば、そこから学びに向かうでしょう。「学びたい」という気持ちがあれば、デジタル世界は優れた情報収集環境です。僕もインターネットがあったからこそ、3DCGもプログラムも独学できました。
親があまり子どもの行動を規制するのには反対です。僕の親も放任主義で、「あれはダメ。これをやってはいけない」と言われたことは、ほとんどありません。何かにつけ規制されたり、楽しく遊んでいるのに怒られたりすると、創造力が萎縮します。「学びたい」「もっと知りたい」という気持ちも、規制をはめられることによって阻害されてしまうのです。 これは子育てでも、組織作りでも同じだと思います。カヤックも放任主義。具体的な目標をトップダウンで現場に課すことはほとんどなく、大きめの全体目標を立てて、みんながそれぞれ自分がやるべきことを考え、そこに向かっていくというスタイルです。僕自身もそのほうが働いていてやりやすいですし、これが正しい方向性だと思っています。
「楽しい!」と思えることで独学を進めていくと、もっと学びたいと思うようになる。僕自身も仕事が落ち着いたら大学で勉強してみたいと思うようになっています。学校は、もっと楽しくする目的があるから行くものではないでしょうか。

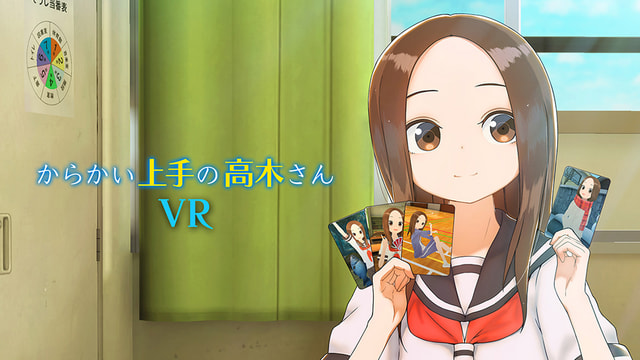
―今は「リアルよりバーチャルの世界でより良く生きたい」という願いは、まだ少数派と思いますが、いずれはそれが選択肢の一つとして受け入れられると考えますか。
天野 VRやARといったデバイスが話題になっていますが、それはツールでしかありません。現在も既に多くの人がSNSやYouTubeなどで、デジタル世界にかなりの時間を費やしています。デジタル世界の進歩が加速すると、やがて触覚や食感などの感覚もデジタルコンテンツに包含されるようになるでしょう。
本物よりも本物らしく見え、触れることもできるデジタル世界が実現したとき、人々はそこで遊んだり働いたり、さまざまな形でより多くの時間を過ごすようになる。そしてフィジカルな現実世界よりも、むしろそちらが日常になっていくだろうと思います。そうすると「アナログのものがなくなっていく」こともありえます。
もっとも今のところ僕たちのチームでは、育児や病気などでやむを得ないとき以外は、できるだけ出社して顔を合わせて作業するようにしています。それについて「意外でした」と言われることも多いのですが、テレビ会議をするより物を見て会話しながら作ったほうが速いし、クオリティも上がる。そしてチーム力も生まれると感じます。
いずれにしても、より便利にスピーディに目的を実現できれば、アナログかデジタルかは重要ではなく、選択肢になるはずです。僕らはメタバースでしかできないことを少しでも多く見つけ、提供していく。そして選択肢として受け入れてもらえるようになればと思います。
―今後、天野さんが実現させたい世界はありますか。
天野 僕はアバター社会をもっと発展させていきたいですね。仮想世界が現実と同等の解像度や操作感を得られたら、物理法則に縛られることもなくなり、現実ではできないことを実現できます。
デジタル世界では、誰もがクリエイターになれる可能性を秘めています。僕はカヤックの理念どおり、メタバースでもクリエイターを増やしていけるような取り組みをしていきたいと思います。例えばクリエイターエコノミーをテーマにしたメタバースを作り、ニコニコ静画で初音ミクのライブ映像をみんなで作っていったように、メタバースでも同じような創造的活動が再現できるのではないかと期待します。それをやることによって、もっと面白いコンテンツが生まれるようにしていく。誰が作ったものであっても、僕の想像を超えるものを見てみたいと思います。








