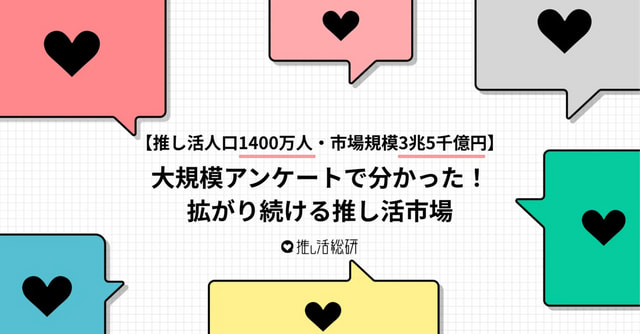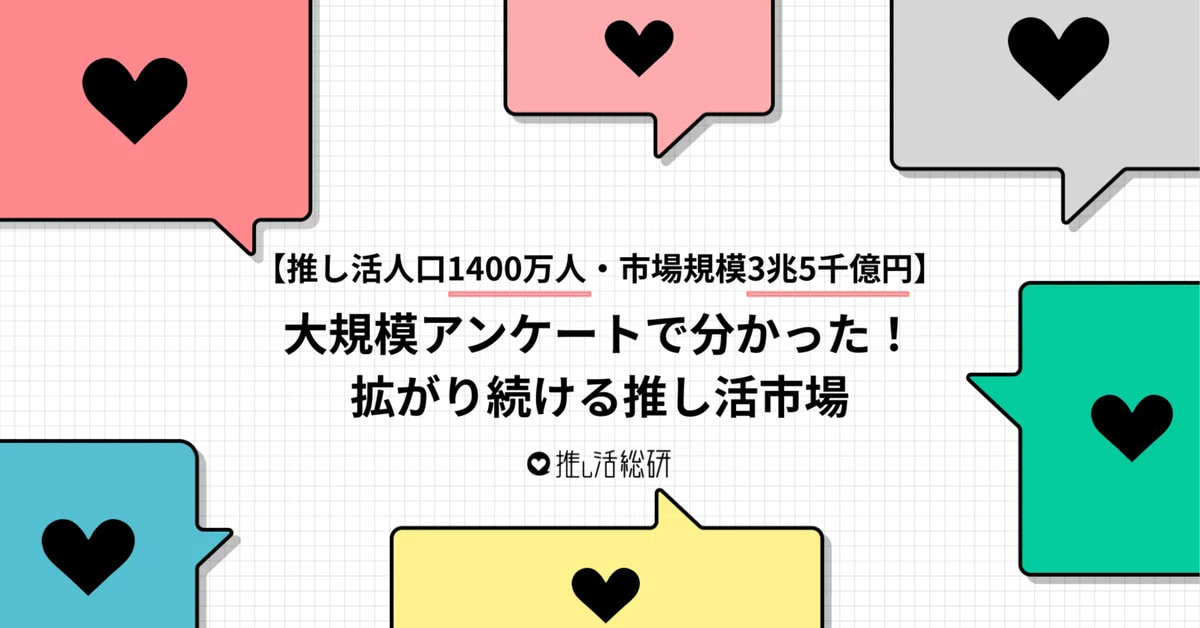推し活をリードする企業の立ち上げ
— 近年、推し活の広がりは目覚ましいです。また、Oshicocoも、2022年の創業から2年で飛躍的な成長を遂げられました。この要因は、何だと思われますか。
多田 ありがとうございます。確かに年商でいうと、4倍以上になっていますね。私がOshicocoを立ち上げた当初は、ビジネスのノウハウもわからず、人脈もありませんでした。そこで、まずは一般の方に注目してもらえるよう、インスタグラムで推し活のリアルを発信し続けてフォロワー数を獲得していったことが大きいと思います。当時は推し活の一般的な認知度がまだ低かったので、推し活をしている人や、興味を持っている若い女性を中心に発信を続け、フォロワー数を増やしていきました。
半年位経った後に、フォロワー数が5万人を超え、推し活グッズも少しずつ売り始めたところ、丸井さんより、新宿マルイアネックスでポップアップストアを出店するお誘いを受けました。オープンするまでは、お客さまに来ていただけるのか、とても不安でしたが、実際は朝から長蛇の列ができ、10日間で1万人以上の来場者を記録しました。売上も大変高かったです。
ポップアップストアをきっかけに、少しずつ企業から、お仕事のオファーをいただくようになりました。また、足を運んでくれたフォロワーの方々との絆も感じられ、自分たちがやってきたことへの自信になりました。このような手応えを得たので、推し活という市場のニッチトップを目指そうと思うようになりました。そこからは、世間で「推し活といえば、Oshicoco」と連想していただけるよう、ポップアップストアのほか、カフェにチラシを置いてもらったり、SNS発信に尽力したり、いろんな場所で名前を知っていただくための活動を進めました。EC(Electric Commerce、いわゆるインターネット販売)でのグッズ販売と並行して、推し活応援ブログを毎日更新するなど、SNS発信のコンテンツ力も強化しました。
— 創業半年後に、いきなりポップアップストアで長蛇の列というのは、なかなか実現できません。多田さんならではの戦略があると思いますが。
多田 インターン時代の4年間に、女性向けウェブメディアのライターを経験したことが大きいかもしれません。そこで発信の神髄を学びました。それは「自分が書きたいことを出すだけでは、興味を持ってもらえないので、世の中をまず見る」ということです。自分が発信する相手が、今、何に悩み、悲しみや怒り、嬉しさや寂しさを感じているのか、ということを、毎日メモに取って考え続けていました。その発信する相手の心の中と、自分の発信したいこととの中間に位置するコンテンツをつくっていくと、世間に効果的に伝わるということを学び、大学時代は、日々の生活でひたすらメモを取り、たくさんの記事に落とし込んで、よく読まれる記事と伸びない記事との違いを考えていました。
— 今、当時のメモを拝見しましたが、すごい量ですね。
多田 当時は手書きのノートを持ち歩き、毎日のように記入していました。 このようにストイックなライター生活を送っていながらも、「世間と同じことを発信するのではなく、これまでにないものを伝える存在になるには、どうしたらいいのだろう」と、考えて続けていました。 その時に悩んでいたことが、Oshicocoを創業し、推し活専門のメディアを立ち上げたとき、大きなヒントになりましたね。
当時、オタクの世界は、アニメやアイドル、K-POPが好きな人など、ジャンルで分かれていて、各コミュニティをつないで情報共有できる場所がありませんでした。しかし、オタクの人たちが共通して求める情報は少なくないので、そこを何とか解決したいと思っていました。例えば、チケットをどうやって取るのか、また、コンサートには何を持っていくのか、 など、共通の情報が集まる場所をつくれば、きっと活用してもらえると思ったのです。
その当時は競合他社がまったくいなくて、弊社のメディアを「推し活メディア」と、ストレートに名付けても、他の媒体と被ることなく、運営を続けることができました。ニッチな分野なので、推し活をしている方は、必然的に私たちの発信する情報にたどりつくことになっていたと思います。あえて言えば、それが最初の戦略です。
— ニッチなところを攻めた後は、どうされましたか。
多田 当初から、推し活という文化に価値があることを、生活者の方や企業の方にもわかってもらえないと、ビジネスとして成り立たないな、という思いがありました。なので、まずカルチャーをつくろうと思いました。それは現在も変わっていません。「推し活は、Oshicocoという会社があったから、こんなに文化として広がったよね」と言われる存在になることを目標にしました。私が尊敬している会社の一つに「北欧、暮らしの道具店」などを運営するクラシコムという会社があります。その会社は、「フィットする暮らし、つくろう。」という理念を掲げ、人々が自分らしく過ごせる「心地よい社会」の実現を目指されています。現在、ターゲットとなる人々の中で、「“丁寧な暮らし”といえば、北欧、暮らしの道具店」という第一想起を得ているように思います。そのように、私たちもビジネスの範囲を超えた文化をつくりたいのです。
よりよい社会をつくりたい
— 推し活を文化にする、というのが創業理念でしょうか。
多田 それよりも先に「世の中をよくしたい」という発想がありました。世の中をよくする、と考えた場合、まず思い浮かんだのが、医療や教育の現場です。でも、自分はそれらに関わる仕事をしていないので、自分が最もよい形で能力を発揮できる方法は何か、と模索していました。そのとき、自分自身がオタクであり、かつ発信することが得意なことに気付きました。
それらを掛け合わせたのが、弊社のスタイルです。ですので、よりよい社会づくりの手段の一つとして、推し活を文化として発信する代表的な存在になりたい、という思いがあります。
— 世の中をよくしたい、という気持ちを持つきっかけは何でしたか。
多田 大学時代にライターをしていた際、コンプレックスに関わる記事のビューが圧倒的に多いことが気になりました。楽しい情報はそんなに読まれなかったのです。ですから、「このまま美容やファッションについて述べていても、精神的な救いにはならないのではないか」という課題意識がありました。
自分のことを振り返ってみれば、明るく活動的になれたのは、推しの存在があったからです。そこで、「自信を持って幸せに生きていくにはどうすればいいか」を考え、哲学や心理学の本を読んだ結果、熱中するものがあることが、人がよりよく生きていくために必要だ、という結論を見出しました。そこで、推し活で起業しよう、と思ったのです。
私はもともと文章を書くのが好きで、中学時代からブログで発信していました。一般的なアイドルに限らず、新選組やUKロックなど、マニアックなものも大好きでした。それらの「推し」を、自分の周囲の人たちと共有できなくても、ネットで世界中に発信すれば多くの人と共有できる、という手応えがありました。当時、つたない中学生英語でブログを発信して、見てくれていたのは10人程度でしたが、それは自分にとって大きな経験でした。そこから発信の楽しさに目覚めて、ライターを始めたのです。
推し活はクリエイティブな活動
— こだわりの世界にこもってしまうのではなく、発信するところが多田さんらしいですね。
多田 弊社は、発信力が一番の強みだと思っています。2010年にツイッター(現 X)が登場するなど、私の子ども時代に、SNSの登場が重なったことも大きいかもしれません。まだアイデンティティが固まっていない年代に、そういうものが身近にあったことは、自分の価値観に大きな影響を与えたのではないかと思います。
— 御社の発信からは、推し活のポジティブさが伝わってきます。発信や商品開発で、大切にされていることは何ですか。
多田 まず、押し付けないことですね。推し活は、自分のアイデンティティを見つけ、かつクリエイティブを楽しむ部分が大きいですから。例えば、コミケ(コミックマーケット、世界最大級の同人誌即売会)にあれだけ多くの人が集まって2次創作をしたり、アイドルが好きな人は手づくりのうちわを工夫したりと、それぞれクリエイティブな活動をされています。
私たちは、その推し活の楽しい部分を味わってもらえるような商品を開発しています。また、新商品を出すことは、コンテンツ力の強化にもつながっていて、新商品のビジュアルや、そこに込めた思いの発信が、とても重要だと考えています。
— 確かに御社の製品は、推し活をする人が、自分なりのクリエイティビティやアイデンティティを発揮できるような、余白のあるものをつくりだしていますね。具体的な利用者のイメージをお持ちですか?
多田 具体的なペルソナは設定していないですね。私や社員、インターンのメンバー全員がオタクなので、純粋に、困っているものや欲しいと思っているものをつくっています。日常での「こういうの欲しいよね」「これ、かわいいよね」などのおしゃべりから、すべてが始まっています。
— みなさん、人生そのものが推し活で、それが仕事につながっている感じですね。
多田 そうですね。私はタイの俳優さんを推していますが、弊社のスタッフは、男性アイドルが好きな子、K-POPが好きな子、アニメが好きな子、2.5次元が好きな子など、それぞれなので、みんなの意見をまとめながら進めています。商品開発のペースは、「こういうのがあったほうがいいよね」という意見が出るタイミングです。
また最近は、企業の方とのコラボ商品も、多様なジャンルにわたっています。推し活用の衣装をはじめ、歯ブラシや保険商品など、さまざまです。弊社だけではできないことも、コラボによって実現可能になる場合もありますので、今後もさまざまな業種の方と「推し活」という文脈でつながっていきたいと思っています。
コラボ事業のきっかけは、企業の方からの依頼と、私たちからの提案の両方です。私たちが推し活をトータルな視点で深掘りし、「きっとこれに困っているのではないか」という点を解決できるような商品を繰り返し提供するイメージでしょうか。私たちのように、「推し活」という視点であらゆる商品とつながる会社はちょっと珍しいと思っています。
— 企業とのコラボレーションにより、推し活グッズも多様化されているのですね。グッズの購入者層は、いかがですか。
多田 中心層は、20代後半の女性だと思います。弊社のSNSの主な読者層は、主に10代から30代ですが、最も多いのは、やはり20代の方です。しかし実際に店舗を開くと、10代から50代以上まで、多様な年代の方とお会いしますので、今後も、あまり年代を特化せず、幅広い層に向けた商品を届けたいと思っています。
日本文化との親和性を見出す
— 最近は、推し活も高度化していて、例えば、推しの名前は記されず、推しの色だけで楽しむグッズも人気を集めているそうです。とてもアーティスティックな領域ですね。
多田 弊社もそういったグッズを手掛けています。このような表現は、日本だからこそ実現したものと思っています。なぜなら日本は外国に比べると、人々の見た目の差がそれほどなく、背格好や肌の色などは似通っている場合が多いからです。
そのように同じようなビジュアルの中から、細かい差異を見つけ、アイデンティティを見出していきます。ですから、同世代で構成された、一見似通った女の子が大勢いるグループの中でも、「この子が推しです」「この子の、こういうところが好き」と、細かな違いによって区別されることになります。このように、わずかな機微を見つけて理解し共感し合えるからこそ、抽象的な概念や細かい部分で楽しむ、という推し方は、日本文化ならではの特徴かな、と思っています。
— 多田さんは、日本古来の文化にも造詣が深いようですね。
多田 極端な言い方かもしれませんが、推し活はアニミズムの世界だと思っています。川や森、一つひとつの石などにも神様がいるという世界観は、人間にかかわらず、モノでも何でも対象とする推し活に似ています。お寺に通う仏像女子や、刀に萌える刀剣女子などは、その典型ではないでしょうか。もっと平たくいえば、クリスマスの後にすぐ初詣に行くという、この何でもあり、という日本人の感覚が推し活文化の源泉だと思っています。
これが一神教を信じる社会ですと、また違ってきます。例えば、アメリカのエンターテインメントでは、基本的に一人のヒーローに注目が集まりますよね。しかし、圧倒的なスーパースターが支持される社会の中で、生きづらさを抱えている人もいると思うのです。ですから、世界中のそういう方たちに向けて、日本の機微の部分を打ち出したコミュニケーションを発信すると、受け入れられるのではないかと考えています。
— 推し活は、「盛って」派手に見せる文化だと思っていたので、抽象的な概念を自分なりに捉える、という姿勢は新鮮です。日本の美意識の「間と余白」に通じるものを感じますね。海外への発信も意識されていますか。
多田 最近では海外でも「推し活」や「推し」という言葉が理解されるようになってきました。漫画『推しの子』の世界的なヒットの影響でしょうか。また、中国ではZ世代を中心に、「痛バッグ」という、缶バッジをバッグにたくさん付ける、という推し活が流行っています。さらに、日本文化の発信ということでは、日本のアニメが世界中で受け入れられる過程で、その周辺の文化にまで興味を持ってもらうことによって、「推し活」が少しずつ文化として理解していただけるのでは、と感じています。
推し活を文化に
— 推し活をビジネスに活かしたいという企業へのアドバイスをお願いします。
多田 大きく2点あります。1つ目は、イベントで盛り上がる印象が強い推し活ですが、日常生活をクリエイティブなものにしていく活動であることもご理解いただきたいです。具体的には、非日常のコミュニティやイベントなどを通して、安心感や自己肯定感を育てる効果があることをお伝えしています。
企業の方から相談を受けた場合、このように、その手前の文化的要素について説明を差し上げています。
2つ目のポイントは、「押し付けない」ということです。「オタクはこう」「推し活はこう」と、一つのワードに集約されがちですが、一言では説明しきれません。もっとアニミズム的といいますか、ファンの方々は、それぞれに信じる「推し」の世界観があるので、そこに対して価値観やスタイルを押し付けない、強制しないことが大切だとお話しさせていただいています。推し活をされるみなさんは、時間もお金も精神力も、ものすごく注いでいますので、人の数だけ推し活のスタイルがあるのです。
— 2024年3月には、推し活総研を設立されました。
多田 こちらも、調査結果を通してさまざまなエビデンスを出し、推し活を文化として高めたいという狙いがあります。さらにはその文化が、サステナブルなものとなることを目指しています。
そのためには、推し活に関わる問題への解決が求められます。推し活には、どうしてもお金の問題がついて回り、例えば、地下アイドルを推すために10代の子がお金を使いすぎてしまったという話も少なくありません。ランダム商法や、スマホゲームで展開される“ガチャ”もそうですね。そのように、消費者にお金を使わせすぎてしまうという課題があります。また、環境問題などのSDGs的な観点から言えば、推しのコンサートやキャンペーングッズは、期間が終わった後、大量の廃棄物となることも、大きな課題になっています。それらの課題に取り組むため、企業とファンとコンテンツ(推される対象)の3者が、理想的な関係を築けたらいいなと思っています。
本当に、3者それぞれの立場の方から、さまざまな話をおうかがいします。例えば企業の側は、利益を出すこととのバランス、また推される対象となる方たちは、セカンドキャリアの問題を抱えています。推される代表格のスポーツ選手やアイドルの方々は、20代前半がピークとなることが多く、その後のセカンドキャリアが保証されていません。そのような課題が「推し活」というテーマから見えてくるのは、弊社だからこそだと思っています。
— それらの会話もまた、調査や情報発信の内容に反映されているのですね。
多田 そうですね。それらの会話の中で、必要性が高いと感じたものを取り入れています。10代から60代までの2万人を対象に実施した、推し活総研の第1弾調査によると、「推し活をしている」と答えた方の割合は14.1%。これは人口換算では1,000万人以上です。推し活はもはや一部の人たちの活動ではない、ということが見えてきましたし、ここまで大きな分母に対しての推し活に関する調査は、おそらく当時前例がなかったため、たくさんのメディアで紹介いただきました。
また意外性があったところでは、男性でも10〜20代では4人に1人の割合で推し活への自覚を持っていることが明らかになりました。女性を含めた母数全体では、3人に1人の割合です。推し活に性別は関係ないということが、この比率からわかります。
男性の推し活は、女性とは異なるスタイルであることにも着目しています。例えば、野球ファンを見てみると、男性は、ゲームの勝敗を楽しむ傾向があり、女性はチームのキャラクターグッズを身に着けて楽しむ傾向が高いです。このように興味深い発見がありますので、これからも推し活全体のカルチャーを探究していきたいですね。
推し活で自己を解放する
— それだけ推し活をしている人たちの多さがエビデンスとして証明されると、推し活の新しい可能性も見出せますよね。その一つが、先ほどからお話があるウェルビーイングです。多田さん自身は、推し活で自己肯定感が高まる経験をされたことがありますか。
多田 私が今、一番応援しているのが、タイの俳優さんです。ハマってから、本当に人生が変わりました。タイ語の勉強を始め、タイ人の友達ができ、タイ料理をつくるようになり、と、推し活を通して、自分はこんなにいろいろなことができるようになったんだ、と驚いています。これまで1人で海外旅行に行くこともありませんでしたが、推しのためならできてしまうのです。
また、普段なら絶対に出会わない地域や職業の方たちとも親しくなれました。私が入っている推し活のコミュニティでは、タイやフィリピン、北海道など、さまざまな場所の方々が、年齢や性別など関係なく、仲よくなっています。
人は普段、会社や学校など、決まったコミュニティの中だけで生活していると、そこでの役割や固定観念に縛られてしまいます。母親や父親、若者など、社会が求める役割と自分自身とのギャップを感じたとき、「自分なんて」と自己肯定感が下がってしまいます。推し活のコミュニティは、そこからの解放なのです。
私が大学生の頃はコロナ禍で、すべてのイベントが中止になり、友達やバイトなどのコミュニティが寸断されました。そんな中で、推し活のコミュニティに救われたのです。推し活がウェルビーイングに結び付く経験を、身をもって感じたのです。
ウェルビーイングといえば、ドミニク・チェン先生が有名ですが、私は大学時代に、先生の授業を4年間受講し、ゼミにも属していました。
— 社会的な役割から解放されて自分軸でいられる、というイメージでしょうか。
多田 そうですね。好きなものでつながる場を増やしていくことが、生きやすさにつながっていきます。私も会社を離れて、プライベートなブログで発信を続けています。
また、多様な価値観に触れられることも大きいと思います。例えば、タイの恋愛ドラマの中には、彼が出家してしまうから結婚できなくなった、というものがあります。悩むポイントが日本と全然違うことに衝撃を受けました。タイはLGBTQをカミングアウトしている方々が比較的多く 、自分と異なる考え方を知るにつれ、日本の価値観に縛られる必要はないな、と気が楽になっていくのです。日本と比較すると、のんびりしている感覚も、私には心地よかったです。今後も個人的にタイの推し活を進めていきたいと思います。
トータルな推し活の応援者として
— 多田さんご自身が推し活の最中だからなのか、御社の推し活応援ブログは、トラブルにあったとか、彼氏との両立など、本音が紹介され、読者にとって心強い存在ですね。
多田 なかなか本音は言いづらいですよね。読者と年齢が近いインターンの大学生たちが書いてくれていますので、共感を集めやすい場になっていると思います。弊社は、インターンや業務委託の方を含めても、まだ15人位の小さな組織です。だからこそ、互いの距離が近く、日々の会話を通した自然な発信ができています。お互いに好きなものを知っているのは、それぞれが大切にしている「軸」としての価値観を共有することにもつながり、心理的安全性が高まります。自然にコミュニケーションが盛んになり、ポジティブなエネルギーの交換が生まれる……そういう明るい職場にしたいですね。
— 今後はどのように推し活を広げていきたいですか。
多田 まず、「推し活という文化はOshicocoという会社があって、そのあたりから盛り上がったよね」と後に言われるような会社になりたいです。企業の方も、個人も、「推し活で困ったらOshicocoに相談しよう」と思い浮かべてもらえる存在になりたい、これが目指す場所ですね。現在は国内向けですが、今後は海外企業とのコラボレーションもあるかもしれません。もちろん会社も大きくしていきたいですが、今手掛けているプロジェクトの規模を拡大したり、まだ出会えていない企業とコラボレーションしたりして、新しい価値を生み出したいと思っています。推し活の社会的な認知は、もはやブームというより根付いていくものとなりつつあるのではないでしょうか。
そんな中で、推し活に関する課題は、弊社単独では取り組めないので、さまざまな企業の方と協力して、サステナブルにしていきたいと思います。
私自身は、20代はOshicocoという会社を大きく育てることに注力し、30代では並行して、推し活を軸にした日本のエンタメ産業の世界への発信など、より大きなスケールの取り組みに関わることができたらと考えています。
— きっと実現されると思います。今後も期待しています。