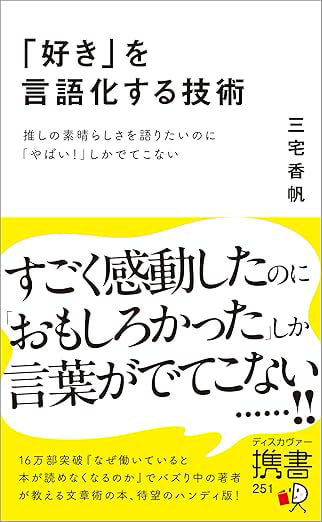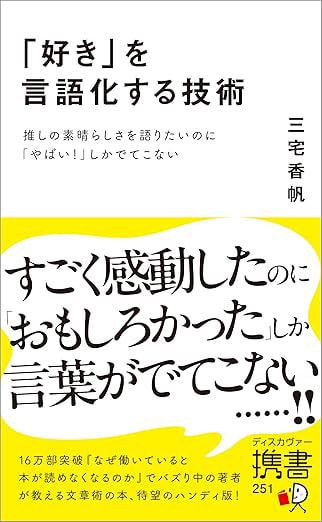「推し」と「萌え」
突然だが、あなたに「推し」はいるだろうか。
もちろん、「推し」がいないからこそこのような論文集を読んでいるのだ、という方もいらっしゃるだろう。あるいは自分にとって熱烈な「推し」がいて、それについて考えたい、という方もいらっしゃるだろう。昨今、「推し」という語彙はさまざまな対象に用いられるようになった。応援しているアイドル、歌手、俳優、VTuberが「推し」であることもあれば、本、映画、漫画といったコンテンツ、あるいは大好きなスポーツ、釣り、チェスといった趣味そのものが「推し」である場合もある。さらには、誰かに広めたい商品や習慣を指すこともあり得る。
従来も「ファン」や「贔屓」といった言葉は存在した。しかし、「推し」という言葉の特徴は、「推薦したい」、すなわち誰かに薦めたいという感情が含まれている点にある。 つまり、ただ単に好きなだけではなく、その魅力を言葉にして伝えたいという欲望を持つことが、「推し」の条件なのである。
例えば「私の推しは乃木坂46です」と言うとき。そこには「乃木坂46が好き」という感情以上に、「乃木坂46の出ている番組や配信を見る」「乃木坂46の活躍を喜ぶ」という行為が入る。あるいは「私の推しはVTuberの月ノ美兎です」と言うとき。やはりそこでは配信を楽しんだりイベントを楽しんだりする行動が意図されている。
つまり、「推し」とは以下のような構図で描きだすことができる。
推し = 好き + 行動する対象
一方で、私は「推し」について考える際、少し昔に流行した「萌え」との対比で考えるとわかりやすいのではないかと考えている。
遡ること20年前、2005年に「萌え~」がユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされたことをあなたは覚えているだろうか。あるいは、2005年に『電車男』 がドラマ化・映画化して大ヒットして「萌え」という語彙を広めたことを記憶している方もいるかもしれない。
「萌え」も「推し」も、極めて似た感情を指しているように見える。AKB48に萌えると語っていた人々と、AKB48の誰を推すかと語る人々に、あまり差異はないように見える。好きなアイドルやキャラクターに関するグッズを購買したりする行動は「萌え」も「推し」も同じで、それを「好きだから買う」か「応援のために買う」か、表面的な目的が異なるだけなのでは? と感じてしまうかもしれない。
しかしこの2つには、明確に異なる点がある。それは、「萌え」の対象は「変わる」ことが前提にある点である。批評家・哲学者の東浩紀は、「萌え」について以下のように説明する。
オタクたちの萌えの感覚は、つねにキャラクターの水準と萌え要素の水準のあいだで二重化されており、だからこそ、彼らは萌えの対象をつぎつぎと変えることができる。(東浩紀『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』(1))
つまり「萌え」とは極めて瞬間的な欲求のことを指した言葉なのである。
例えば「萌え変」とは言わない。「萌え」は一瞬の中で溢れ出す感情であるからだ。だが「推し変」という言葉は存在する。
「推し」は一瞬の感情ではなく、継続的な行為であるとされているからだ。
図式化するとこのような差異が見える。
萌え = 好き
推し = 好き + 行動する対象
そう、「推し」とは自分が行動して初めて対象化される存在なのである。
言語化という推し活
では、「推し」に対する行動とは、どのようなものがあるだろうか。
例えばライブのチケットやグッズを購入すること。応援のために何かの金額を投じること。いわゆる「課金」とも呼ばれるような、金額を推しのために投じることが、「推す」行動であるとされやすい。
もちろん、推しもビジネスであり商売であるから、それは1つの明確な応援行為だろう。しかし私は「課金」以外の方法があるのではないか、と思っている。それは、「言語化」である。そう、推しについて自分一人の中で、言葉にして、場合によっては他人に伝えること。
それによってはじめて可能になる「推し」との向き合い方もあるのではないか。私はそう信じている。
ただ単に好きなだけではなく、その魅力を言葉にして伝えたいという欲望を持つことが、「推し」の条件であるのではないか。
さらに自分は普段文芸評論家としてある意味「本」という推しについて語り続けているのだが、そのような日々を送っていると、しばしば次のような質問を受ける。
「どうすれば良い感想を書けるのか。推しについて文章を書きたいが、語彙力が足りなくてうまく言語化できない」
彼女ら彼らの切実な悩みをよく耳にし、たしかに、と私は思った。「推し」という言葉がこれほど流行しているにもかかわらず、その語り方についてはあまり誰も教えてくれない。もちろん、好きなように語ればよいという考え方もある。好きなように、好きな対象の魅力を語ればよいという人もいるだろう。しかし、一方で「どうやって推しについて語ればいいのか」と悩む人がいるのも当然である。なぜなら、日本の学校教育においては、作文の技術や言語化の技術について、案外教えられていないからである。
例えば日本の国語教育には、読書感想文というプログラムがある。しかし読書感想文について、このようにいわれたことはないだろうか。
「なんでもいいから1冊本を選んで、感想を夏休み中に書いてきてね」と。
そう、なんでもいいのだ。つまり、どうやって読書感想文を書いたらいいのか、その方法論は学校でほとんど教えないのである。
読書感想文の宿題は出されるものの、その書き方は教えられないのである。指導されるのは、原稿用紙の使い方、助詞の使い方、字数の規定など、作文の形式的なルールに関するものばかりである。しかし、それらを理解したところで、読書感想文を書けるようになるわけではない。
それでも学校が読書感想文の宿題を出し続ける理由は何か。そこには、日本の国語教育における「自分のありのままの感想を書けば、それがそのまま作文になるはずだ」という考え方に基づいているからではないか。そう私は推察している。すなわち、「本を読んで感じたままに、それを紙に書けば良い読書感想文になる」と考えられているのである。
しかし、それが必ずしも正しいとはいえない。
仮に、本を読んで感じたことをありのままに書くだけで良い読書感想文が完成するのであれば、書評家や評論家という職業は不要であるはずだ。
文章を書くことには、技術が必要なのである。技術を駆使することで、初めて良い感想を書けるようになる。―それは逆にいえば、「書く技術を理解すれば、良い感想や良い文章を書くことができるようになる」ということでもある。
読書感想文も、一種の「推し語り」であるといえるだろう。好きな本という「推し」についての感想を書くものであるからだ。そこには当然、必要とされる技術が存在する。
このような考えから、私は「推し」について言語化する技術を『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)という本にまとめた。その中では「推しの魅力を言語化する際に最も重要なのは、クリシェを避けることである、と強調した。
クリシェを避ける効用
「クリシェ」とは、フランス語で「既に乱用された概念や言葉」のことを悪い意味で指している用語である。例えば小説でよくある、ありきたりなシチュエーション。ありきたりな台詞。
ありきたりな言葉。それらをフランス語で「クリシェ」と呼ぶのである。
日本語には「クリシェ」にあたる用語がない(あえて挙げるなら「常套句」あるいは「ありきたり」)。が、私はこの「クリシェ」が、文章を書くにあたって、最も警戒すべき敵だと考えている。
それはつまり「ここでこういう言葉を出しておけば、それっぽく見えるだろう」と感じられる語彙のことだからである。
例えばあなたの推し作品が、とある漫画だと仮定する。あなたはその漫画が好きで仕方がない。その漫画の良さをみんなにどうにかして伝えたい。だからSNSにその漫画の魅力を書くことにした。
「この漫画、泣けてやばい。すごい考えさせられた」
ここでいう「泣ける」や「考えさせられる」こそがクリシェである。つまり、泣けた、や、考えさせられる、という語彙を使えば、たしかにそれらしい感想にはなる。集団の中では浮かないかもしれない。だが、何を考えさせられたのだろうか? どこに泣けたのだろうか? そうやって深掘りしていくと、もう少し自分の言語が見つかるはずではないだろうか。
クリシェ=ありきたりな表現は、個人の表現を奪う。
クリシェを禁止した先に、先述した「自分だけの感想を書くこと」が存在する。私は本気でそう思っているのだ。
ありきたりな、それっぽい表現を使わずに、自分だけの感情を、考えを、印象を、思想を、言葉にする。 それだけで、オリジナルな文章ができあがる。
私は著作の中で、そのように強調した。
なぜ私はクリシェを避けることを強調したのか。それは「推し活」という場が、想像以上に他人や世間の言葉によって支配されやすいのではないか、という懸念からである。
というのも、現代の「推し活」には、ファンダムと呼ばれるファンの集団に属することが暗黙の了解となっている場合が多いからである。もちろん推しにもよるのだが、SNSを中心として「推し」について複数人で語ることが増えると、その語りの中心ができてくる。ファン集団の意見がSNSによって可視化されやすくなったのだ。すると、ファン集団=ファンダムの総合的な意見がSNS上の空気によってできてくる、ということが起こりやすい。
これが最も可視化されやすいのが、「炎上」と呼ばれる、スキャンダルが起きたときである。
祝祭とファンダム
現代日本を「カーニヴァル」と呼んだのは、社会学者の鈴木謙介である。鈴木の『カーニヴァル化する社会』(講談社)(2)は2005年刊行なので、「推し」という言葉はまだ登場していない頃の著作である。だが同書は「推し活のファンダム」について極めて明瞭に説明した本であると私は思っている。
もともと「カーニヴァル」とは、鈴木も引用するとおり、社会学者のジグムント・バウマンの語彙だ。ジグムントは、「熱狂の中身についてはすぐに忘れてしまうにもかかわらず、大衆が気分によって瞬発的に熱狂すること」をカーニヴァルと呼んだ。
なぜそんな熱狂が大衆に求められるのか。それは現代において、人々が組織や伝統といった共同体から自由になったことで、むしろ「共同性」を求めるようになったからだという。この「共同性」とは何か。誰かとつながっている感じ、なんとなく瞬間を共にしている感覚そのもののことだ。人々は、構造を維持していく共同体に属するのではなく、他人と瞬間的につながり得ることに重きをおく共同性を感じることを求めるようになった、ということである。
昔からある「共同体」とは、固定的=ソリッドな団体だった。例えば近所付き合い、ずっといる会社の同僚、ずっと一緒に暮らす家族。そのどれもが移動不可能なものだった。しかしそこに縛られるのは耐えられないと感じるようになった現代人は、「共同性」つまり流動的=リキッドな瞬間的熱狂を求めるようになった。
「共同性」はなんとなく感じられるだけでいい。熱狂の一貫性などはなくていい。とにかくその場その場で、みんなとのつながりを持てたらいい。それが日常的に「カーニヴァル」を求める理由である、とジグムントは説明する。
鈴木の『カーニヴァル化する社会』はこのような「カーニヴァル」の例として、オリンピックやワールドカップへの熱狂、あるいは極端な有色人種排斥運動や人工妊娠中絶反対運動の増幅、そしてイラク人質バッシングや拉致被害者家族バッシングといった「祭り」を挙げる。つまり今でいうと日常茶飯事となってしまった、インターネットの「炎上」のことを述べているのである。あるいはアメリカのトランプ現象や、日本の選挙をめぐるSNSの熱狂のことを連想する人も多いだろう。
私たちは「カーニヴァル」を日常に求めている。祝祭がないと、人とのつながりを意識できない時代に生きているからだ。
昔であれば、地域の祭事や学校の行事、会社の忘年会や歓送迎会で「共同体」を感じることは充分だった。あるいは戦争やそれに至るナショナリズムなどの国家という「共同体」を自分の所属する場として感じることもまた、人々を満足させていた。しかし現代日本においては、住む地域や学校、職場も自ら選ぶことができるとされている。さらに地域や学校、職場で自分とつながり続けていると思える他人を見つけることも、少しずつ困難になってきている。どれも流動的な場―いつかはつながりがなくなってしまうかもしれない関係―だからである。「大人になると友達ができない」なんて声を聞くこともあるが、それはつまり現代においてつながり続けられる他人を見つけることの難しさを説明している。
だとすれば、私たちが求めるつながりとは、結局「カーニヴァル」の瞬間的な熱狂なのである。
祝祭はその場限りでいい。インターネットの炎上は、誰かを批判し敵とみなすことによって、「自分たちは同じ側にいる」とつながりを感じられる、容易な祝祭である。
そしてこの祝祭を起こしやすいのが、推し活なのである。
例えばアイドルの熱愛が報道される。するとファンの集団はアイドルを批判する。なぜ集団で彼らはアイドルを批判するのか。それは、批判することによって、アイドルの熱愛を許さないファンであるという「同じ側にいる」感覚を、祝祭によって共有したいからではないか。
推し活には、ファンダム―「推す人たち」、つまりファンのコミュニティが必要なのである。現代ではSNSを中心として、「推す人たち」は集まり、そして熱狂する。推しの動向をとおして、祝祭を体験する。推しがテレビに出る。推しがMVや動画を公開してくれる。推しがメッセージをくれる。推しが夢の仕事をすることになる。推しが今回の登場シーンでとても活躍している。―それらに熱狂できるのが、祝祭を見出すことができることが、「推し活」の条件である。一方で「負の祝祭」として炎上やスキャンダルが存在する。それもまた、「カーニヴァル」の一側面なのではないか。
カーニヴァルから遠く離れて
例えばアイドルへの批判は、誹謗中傷になりやすい。誹謗中傷は犯罪に転じやすい。祝祭に無自覚に参加しすぎると危険であることは、さまざまなファン集団の暴走を見ればわかるとおりではないか。
あるいは、推している対象が本や映画といったコンテンツであっても、例えば、同じものを読んだり見たりした相手に影響を受けてしまうことはあるだろう。「本当は●●の曲がすごく良いと思っていたのに、同じバンドを好きな友人が●●の曲は平凡だと言っているのを聞いて、なんとなく●●の曲が微妙だと感じてしまう……」という声を私もしばしば耳にする。しかしそれは、感想の共同性に取り込まれてしまい、一人ひとりの感想が独立しなくなってしまうのではないか。
だとすれば、私はやはり「カーニヴァル」から距離をとることを推奨したい。
そしてそのために必要なのは、「カーニヴァル」の言葉と、「自分」の言葉を、切り分けることであると思っている。
世間や他人といった共同性がインストールしてこようとする言葉に対して、「自分はほんとにその言葉でいいんだっけ」と立ち止まる。そして自分だけの感情や思考を取り戻して、言葉にする。そのためには、クリシェを避けることが重要なのである。
他人の使う語彙を利用するのではなく、自分の言語をつくりだす。その練習を、「推し活」を通して―推しの魅力を言語化することを通して―幾度となく繰り返す。
その結果として、共同性から距離を置き、自分なりの言語を紡ぎだす習慣をつけることができればいいのではないだろうか。
繰り返すが、私が強調するのは、ファンダムの共同体の意見よりも、ファンとしての自分の意見を優先しよう、という点である。
推しについて語るとき、ファンダムの感想や意見に合わせた自分の感想や意見を提示しないように気をつけるべきである。なぜならファンダムの空気を読むことは、必然的に祝祭に参加することになるからだ。もちろんそこに快楽があるのはわかりすぎるほどにわかるのだけど、それでも負の祝祭に知らず知らず参加することの恐怖を、私自身感じていた。SNSを見る前に、自分の感想をメモしようと『「好き」を言語化する技術』では書いた。それはSNSに存在する、祝祭に染まった言葉を使わないための技術である。
もちろん祝祭に染まることの楽しさは存在する。みんなと一緒に応援したり、試合の結果に全員で一喜一憂したり、そういった楽しさがあることは決して否定しない。しかし一方で、それだけが推し活の楽しさかと問われると、それだけではないのではないか、と思うのだ。
推しを推すことと、負の祝祭に参加することを、切り離す。そういうことをやりたくて、まずは「言語化」という主題を切り口にしたのである。
というわけで、私は推しと祝祭は分けることができると思っている。つまり、誰かを好きになったりあこがれを投影したりすることは、祝祭―ファンの共同体を切断しても、可能になる。そう考えているのだ。
「推し変」した後も言語化は続く
さらに、「推し変」という言葉がある、という話を冒頭にしたが、「推し」が「推し」でなくなる日はやってくる。いつか、熱が今より少しだけ冷めるときがくる。だからこそ自分の感情を言語化することは重要である。
というのも、自分の言葉で、自分の好きなものを語る―それによって私は自分が自分に対して信頼できる「好き」をつくることができる、と感じているからだ。
自分の好きなものや人のことを語ることは、結果的に、自分のことを語ることでもある。そもそも、好きなものやいいと思った人は大きな影響を与えるものだろう。もちろん嫌な経験や辛い出来事もまた自分を形づくるものではあるが、やはり好きなものやことの影響は、人生においてとても大きなものである。だとすれば、自分を構成する上で大きなパーセンテージを占めるものについて言語化することは、自分を言語化することでもあるのではないだろうか。
一方で冒頭にも書いたとおり、何が起きても絶対に変わらず好き、ということはあまりない。例えば、誰かアイドルがすごく好きでも、そのアイドルが自分の想像とは全く違う行為をしていた。そして自分の「好き」がよくわからなくなってしまうことそれ自体は、よくあるし、決して批判されることではないだろう。スキャンダルほど大きな契機でなくとも、人によっては髪型やメイクを変えるイメチェンや、あるいは意外な趣味を持っていたことすら、好きな感情が揺らぐきっかけになり得るかもしれない。または、子供の時にすごく好きだったものに対し、大人になって好きな感情が冷めてしまうこともしばしば存在する。昔すごく好きだったキャラクターが、大人になってその魅力がわからなくなる。思春期にハマっていたミュージシャンの歌詞が、社会人になってなんとなくぴんと来なくなる。これもよくある現象である。それ自体は批判されることではないのだ。
なぜならそもそも「好き」とは、揺らぐものだからである。というか、揺らがない「好き」なんて存在しない。自分も生きているし、変化するものである。だとしたら、好みが変わっていくのは当たり前だ。あるいは好きな相手が生身の人間だとしたら、相手だって変わっていく。自分の思うとおりに存在するわけがない。絶対的な「好き」なんてほぼあり得ないのだ。
そして、「好き」が揺らいだとしても、それを嘆く必要はない、とも私は考えている。むしろ揺らがない好きという感情なんて、盲目的な執着であって、本当の意味で好きなわけじゃないのではとすら思う。
しかし、たとえ感情としての「好き」が揺らいで消失したとしても、一度「好き」を言語にして残しておけば、自分の中に残り続ける。そう私は考えているのだ。
例えば、好きなアイドルがいて、ライブや新曲を追いかけて、楽しい日々を送っていた。でも、そのアイドルにスキャンダルがあり、そのことでたくさんの人から非難されて、自分もまたショックを受けた。そうするうちに、自分はそのアイドルを好きではなくなってしまった。そういう出来事があったとしよう。ここで、アイドルを好きだった時代に「好き」を言語化して、自分のメモ帳に残しておいた。スキャンダルが起きてちょっと経って落ち着いた時、そのメモを見返してみる。そしたら、もう存在しなくなった、自分だけの「好き」が、そこに保存されているのだ。
ただ、そこに好きがあったことを、思い出せる。今はもう好きじゃなくなっても、いつのまにか自分の一部になった好きな感情が保存されている。それは重要なことではないだろうか。
もちろん、例えば写真を残したり、モノを置いておいたりすることも、いいだろうけれど。でも、一番鮮明に残る「好き」は、言葉である。私はそう考えている。
「好き」は、儚いからこそ、鮮度の高いうちに、言葉で保存しておく。
いつかやって来る「好き」じゃなくなる瞬間も見据えて、自分の「好き」を言葉で保存しておく。そしてその「好き」の言語化が溜まってゆくと、それが丸ごと自分の価値観や人生になっている。
そのような効能も、言語化にはあるのではないだろうか。
SNSでさまざまな価値観が日々目に入る時代である。予期せぬうちに、自分の価値観がわからなくなっている人も多いのではないか。そんなとき、自分は何がどのように好きなのか、それがわかると大きなアドバンテージになるはずである。
自分の「好き」を言語化していけばいくほど、自分についての理解も進むのだ。
そう考えると、「推し活」の中で言語化をすることは、極めてポジティブな効用を生み出すはずである。
もちろん、言語化しきれずに悔しい思いをすることもあるだろう。あるいは推しという存在が、いなくなるときもあるだろう。だがそれでも、言語化したことは無駄にならない。私はそう考えている。
言語化とは、推し活の、金額を使うだけではない、新しい側面になり得るのではないだろうか。
〈参考文献〉
(1)東浩紀『動物化するポストモダン オタクから見た日本社会』講談社、2001年
(2)鈴木謙介『カーニヴァル化する社会』講談社、2005年