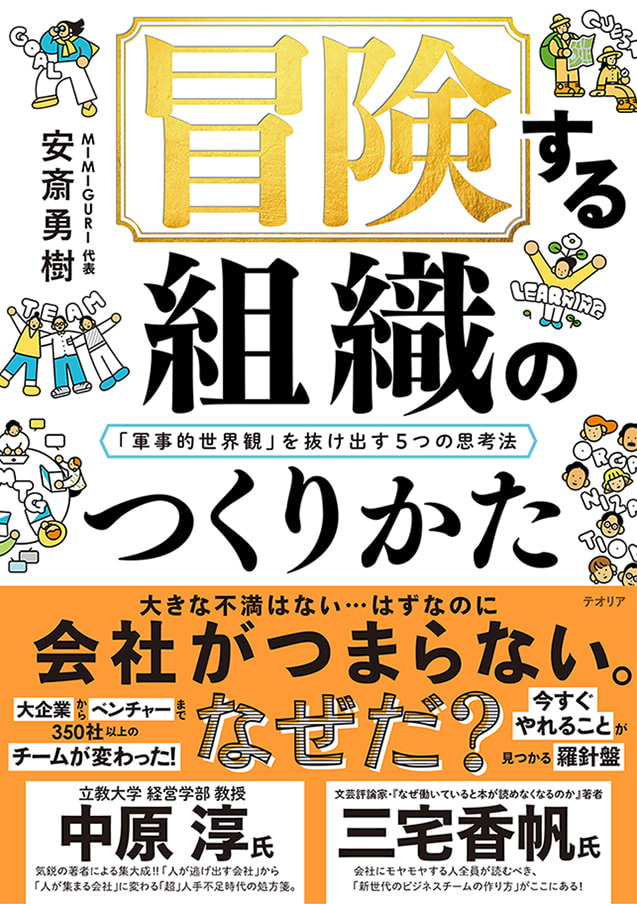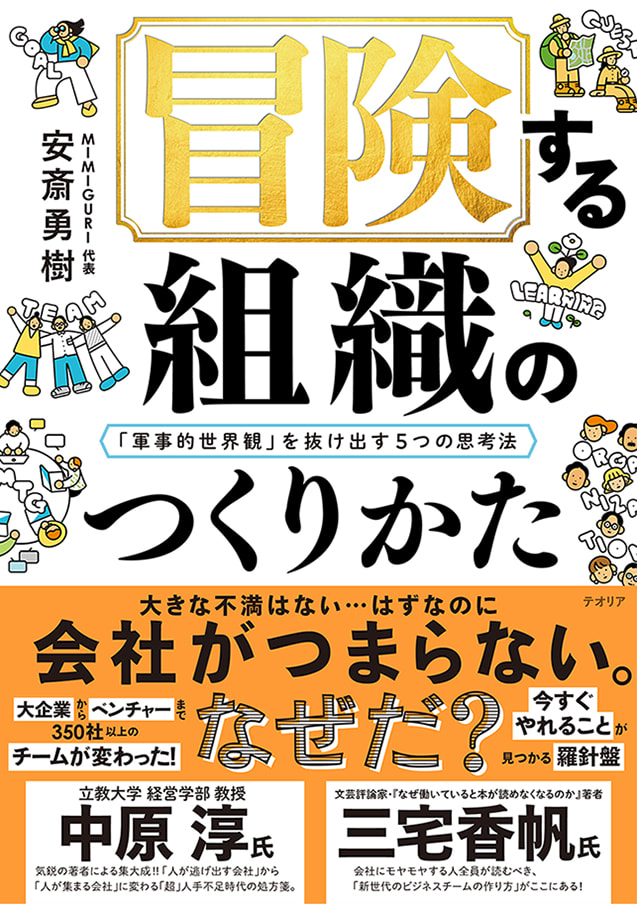個人情報の共有が「推し活」の鍵
— MIMIGURIでは、メンバー同士の「推し活」が行われていると伺っています。そうした試みをスタートした背景について、お教えいただけませんか。
安斎 まず前提からお話ししたいと思います。組織内で働く人同士の関係について、一般的な経営論やマネジメント論では、営業やエンジニアといった各人の組織上の役割や持っているリソース、得意分野に基づいて結びついていると考えます。そのような役割や能力に基づいて人間を“道具化”する管理手法を僕は「軍事的世界観のマネジメント」と呼んでいます。
人は本来、仕事だけでなく、家庭や趣味、地域との関わりなど「多様な顔」を持っています。その中に「会社員」というパートがあるにすぎません。そうした見方は今の若い世代では当たり前になっています。人間を会社での役割に押し込めて「営業A」「エンジニアB」として扱い、「営業が文句を言ってきた」など、人を個人ではなく役割で語るときは、相手の人間性についての想像力が欠けた状態です。
役職だけ見ていては、相手の本当の姿はわかりません。お互いがしっかりつながるためには、表面的なスペックの裏側を知らなければならない。そして、それを知ることから生まれるのが「推し」という感情だと、僕は考えています。
— 仲間の内面を知ることが「推し」につながると。
安斎 例えばある新規事業を任せる人を、どう選ぶか考えてみましょう。
一般の会社では「前職でベンチャービジネスを担当していたから」「この事業分野に知見があるから」といった理由で人選を行うでしょう。しかしここで、次のように語りながら手を挙げる人がいたら、どうでしょう。
「私はこれまで新規事業の経験はありませんが、最近息子が生まれまして、『この子には自分の好きなことをやってほしい』と思ったんです。でも、それでは私自身はどうなのだろう。『自分は息子に背中を見せられているだろうか』と考えたときに、『このままではいけない。もう一度全力で挑戦したい。新しい事業にゼロから』と思ったんです」
多くの人は、このように語る人を「応援したい」「この人にチャレンジさせてあげたい」と思うのではないでしょうか。
なぜなら、その人について持っている情報の量と質が違うからです。資格や肩書ではなく、ストーリーを語ってくれる人には、誰もが「がんばれ」と応援したくなるものなんです。
ポジションや経歴だけでなく、努力のプロセスや失敗の経験談など、普通なら表に出ない水面下の情報を知ることで、「この人を応援したい」という気持ちが生まれてきます。
そういう「推し」につながるようなお互いの情報をどれだけ共有できるかが、これからの企業の組織づくりの鍵になると、僕は考えています。
— MIMIGURIには情報共有のための独特な仕組みがあるようですね。
安斎 弊社はフルリモートで出社義務がないため、オンライン上でお互いを知れるよう工夫しています。各人のプロフィールはいつでも見られるよう、社内サイトにアップしていますし、「MIMIGURI ch(ミミグリチャンネル)」という専任スタッフがいる社内放送局をつくって、社員の人となりがわかる番組コンテンツを定期配信しています。
水曜日には2人のパーソナリティがゲスト1人を迎え、その人の人となりを掘り下げる番組を放送していますし、ランチタイムには生配信もやっています。「アナザーストーリー」と題して、「社内のクールなエンジニアの〇〇くんが、実はスキンケアオタクだった」などといった、仕事とはまったく関係ない情報も発信しています。ポイントは社員各人の仕事以外の一面、日常では見られない部分をお互いが知ることです。
— 皆さん、プライベートについても気軽に話してくれるものなのでしょうか?「 そういうのはちょっと」となりませんか?
安斎 弊社の社員は概して、何もしないと自分からは話してくれないタイプ。人見知りで内向的な傾向があります。でもプロデュースやインタビューの工夫をしていくと、だいたいどんな人でもいろいろ話してくれます。先日は、過去イチ人見知りな人が入社しました。40代の男性です。この方の場合は番組で、自分がどれだけ人見知りかを自慢してもらいました。「立食パーティーで壁とどれくらいお友達になれるか」といった話をしてくれたんですよ。
今の世の中ではキャリアについての価値観や、「何のために仕事をするのか」という根源的な問題が問われるようになっています。それぞれの会社だけでなく、社会全体がこの問いに向き合っているんです。そこではたとえ仕事の関係においても、人を肩書や役割で見るのではなく、全人格的な存在として対峙していくことが欠かせません。
軍事的世界観の弊害
— 安斎さんの新著『冒険する組織のつくりかた』では「軍事から冒険へ」を提唱されています。これまでの企業組織論にはどんな問題があるとお考えでしょうか?
安斎 従来の企業の組織論は戦前の軍事的世界観に根ざしていて、その弊害は「人間の道具化」にあります。人を戦略や戦術の実行手段と定義し、ネジや歯車のように扱う。そうした軍事的世界観の下では、上司は部下に対して「こいつは俺の言うことを80%やっている」「こいつは52%しか機能していない」といったように、自分の目的に対する達成率を基準に部下を評価します。これは非常に抑圧的なマネジメントといえます。
冒険的世界観では、事業における社会的価値と、個々人の自己実現の両立を重視します。漫画『ワンピース』では船長のルフィが「海賊王になる」、仲間のゾロが「世界一の剣豪になる」とそれぞれ違う夢を抱きながら、同じ船に乗って一緒にワンピースという宝を探す旅をしていますよね。冒険的組織でも同じように、事業を通して社会的価値を探求しつつも、メンバー一人ひとりの自己実現をあきらめません。
冒険的世界観では、「人は飽きるもの」「人は面白いもののほうが力を発揮する」と考えます。キャリアにしても、「どれがいいかわからない中で、迷いながら浮遊している」と捉えます。そしてわからない中、少しでもハッピーになれるよう支えることが、マネジメントであると考えています。
— 安斎さんがそのような発想に向かうことになった個人的な動機は、どこにあるのですか?
安斎 組織論を考えるようになったきっかけは、自分が会社を立ち上げて、人を雇うようになったことです。それで経営学を学ぼうと本を読んだのですが、まったく頭に入ってこなかった。「これって軍事的規範じゃないか」と感じたからです。
軍事的規範を嫌い、冒険的規範を好むようになったのには、自分の過去の出来事がいろいろな形でつながっていますね。ネガティブな経験から話すと、僕は体育のプールの授業が大嫌いでした。小さい頃に溺れかけたことがあり、顔に水がかかるだけで怖かったんです。「こんな怖い思いをするなら、泳げなくてもいいじゃないか」とずっと思っていました。
学校教育の中で、体育は最も軍事的といえます。25m泳げるかどうかでクラス分けされ、それが帽子の色でわかるようになっていました。僕は差別され、命の危険を感じながら泳いでいたんです。
ポジティブな経験としては、思春期に「仲良くなれない」と思っていた人と仲良くなったり、高校の部活のバスケットボールで膝をけがして絶望していたら、監督が「スリーポイントシューターとして復帰してみないか」と提案してくれたり、といったことがありました。
膝をけがしたことでそれまでのようには動けなくなりましたが、スリーポイントシューターを試してみたら、むしろそっちのほうがしっくりきて、「なんで今までやっていなかったんだろう」と思ったほど。もしも監督から「復帰は無理だから部活はやめて受験に専念しろ」と言われていたら、あの経験はできませんでした。
マネジメントについては多くの人が、ポジティブな経験とネガティブな経験の両方を持っていると思います。
— 一般の会社では、必ずしも自分が好きだと思える部署や仕事に配属されるわけではありません。「自分はここに合わない」と感じたとき、どうすればいいのでしょうか?
安斎 「自分はなぜこのチームで働いているのか?」という問いも、根源的な問題の一つです。ただ機械的に一緒に働いているのではなく、精神的なつながりを感じられることが、チームとして力を発揮する上で大事だと、われわれは考えています。
やりたくない仕事にアサインされたときや、強制的に編成されたチームで働かなければならないとき、「お金のために我慢するしかない」と考えるのは、旧来の軍事規範的マネジメントへの屈服です。与えられた状況をどれだけマシに変えていくかが、個人によるそれへの抵抗です。
— どうやってつまらない仕事を面白くするのでしょうか?
安斎 仕事に楽しみを見出すためのアプローチにも、レベルがあります。
レベル1は、メンバーそれぞれが自分なりに楽しみ方を考えてみること。目の前のタスクに自分なりの意味を見出し、自分の色を加える「ジョブクラフト」をするのです。
例えば大学教員には、大学受験の監督として教室に立たねばならないという仕事があります。僕は経験がありませんが、完全に心を無にしてこのような状況を耐えるより、「今年はどんな問題なのだろう?」と好奇心をもって問題文を眺めてみたら、少しは退屈も和らぐでしょう。
レベル2は職場のリーダー、一般的にはマネージャーが、メンバーのモチベーションを考えてマネジメントしていくことです。
「今期の売上◯万円を達成すべし」という指示をマネージャーが出す際も、数字だけ言うのではなく、「前年と違うやり方でやってみよう」と提案したり、「去年はよくがんばったね。今年もよろしく頼むよ」と声を掛けたり、「去年はこのやり方で売上100万円だったから、こういうやり方にしたら120万円いくんじゃないか」とアドバイスしたりといった、マネージャー個人としての工夫を行います。無機質な数字への意味付けを行うことは、個人にとっても組織にとっても効果的です。物語がないまま働くことは、組織の歯車になるのと同じですから。
レベル3はリーダーがメンバーと話し合い、職場全体で話し合える環境をつくることです。目標についてみんなで話し合い、作業の分担についても「◯◯さん、これやってみたら? 代わりに僕がこれをやるから」といったように協力し合います。これは「推しあっている」状態ともいえます。
— マネージャーの役割は大きいのですね。
安斎 マネージャーはメンバーの一人ひとりが何にやりがいを感じているか、今後どのような業務で何を成し遂げたいのかなどを細かくキャッチアップして、組織のミッションと紐づけながら支援していく役割を負っています。仕事が楽しくないと感じているメンバーに対しては、マネージャーがケアしなくてはなりません。
— 好きになれない相手がいる職場の場合は、どう対処すればいいでしょう?
安斎 「たまたま同じ職場に配属されただけの人と無理して関係を築きたくない」というのであれば、その必要はないでしょう。でも「どうせなら楽しく仕事したい。成果も出したい」と思うなら、まず相手に関心をもつことです。
僕が「文化祭理論」と勝手に呼んでいる現象があります。
「あいつとは絶対仲良くなれない」と思っていた相手と、たまたま文化祭の準備で遅くまで一緒に作業することになり、その中で相手ががんばっている姿を見て、「あいつもなかなかやるじゃないか」と思い、仲良くなってしまう。
これはハレの場、つまり非日常の場で起こる現象で、日常の人間関係が非日常の経験で覆されることがあるのです。そうしたお互いの理解が、日常の組織づくりにつながっていきます。われわれは「お互いのことをよく知らないと一緒に仕事はできない」という価値観を持っているんです。
人も組織も変化が必然
— MIMIGURIでは企業に対してそういったコンサルティングを行っているわけですね。
安斎 MIMIGURIのコンサルティングでは対象となる組織に対して名目上の課題、例えば「企業理念をつくる」「商品のブランディングをする」「新規事業を考える」といった当面のミッションが与えられますが、実際にはその作業を通じてお互いの関係性を変えていく、「推し」を発生させることが大きな目的となっています。
— 具体的なケースを教えていただけませんか?
安斎 本田技研工業株式会社(ホンダ)ではMINERVA(ミネルヴァ)という、MIMIGURIが支援した従業員向けの新価値探索プログラムが実施されました。中期的にイノベーションを推進することが目的なのですが、ホンダが世の中に提供すべき価値の探索をするため、55人のメンバーが約5カ月間、13のチームを組んで、「『自由な移動の喜び』を自ら解釈・定義し、表現する」というテーマを探求するプロジェクトです。4つのコースを設け、各コースでは社外のパートナーとともに、ホンダ社員にとってまったく未知なフィールドを経験してもらいました。
あるコースでは長野県の山奥で、鹿に罠を仕掛けるプロの猟師の方と一緒に山ごもりしてもらいました。これは一見すると、ホンダの事業にはつながっていないように思われます。しかし参加メンバーはそれを徹底してやりつつ、「自由な移動の喜び」について考えたのです。「人はなぜ移動するのだろう?」「食べるものを得るためではないか?」といった哲学的な問いがどんどん生まれてきて、最後にそれぞれが考えたことを「 から、 へ。展 -Hondaと考える自由な移動の喜び-」という展示会で発表しました。この試みは社内外で高く評価され、参加したメンバー同士もとても仲良くなりました。
お互いの関係が深まったのは、プロジェクト期間の中で互いに、「○○さんは、こういう人だったのか」という発見の連続があったからです。このようにそれぞれのイベントを通じて、メンバー間に「推し」の関係が生まれるような仕掛けをしています。
— 非日常の体験を共有することで、なぜそれほど大きな認識の転換が生まれるのでしょうか?
安斎 日常というのは実は、「これが正しい」という凝り固まった規範に包まれている状態です。例えば学生は教室では「授業中にしゃべらない」とか「前方にある黒板のほうを向く」といった、さまざまな不文律に縛られています。その不文律を外してやることで、自分を縛っていた固定観念も外れていくんです。そうした非日常の空間は工夫次第で、会社の会議室でもつくることができます。
企業にとって固定観念とは、変化を止める重い足かせです。例えば、ある自動車メーカーでカーナビを作る部署の人たちは、「どんなカーナビを作るか」という狭い前提の中で商品開発をしていました。でも問いを重ねるうちに、「カーナビを作る目的は、豊かな移動時間を提供することだ」という言葉がその人たちの中から出てきて、そこから突然、さまざまなアイデアが湧き出しました。きちんとデザインされたワークショップは、人を暗黙の前提から解放し、それがイノベーションや組織の変化につながっていくのです。
—「人も組織も変わっていくもの」という話をされていますね。
安斎 人は変化し続ける存在です。同じ仕事をしていても、それを楽しいと感じる時もあれば、飽きてしまうこともあります。どんなに好きなゲームでも「100回やれ」と言われたら辛くなるでしょう。
「これが私のこだわり」と思っていたものが、気付くと「囚われ」に変わっているということは少なくありません。僕も20代の頃にワークショップについての本を書いたところ、毎日のようにワークショップの依頼が来るようになり、「もうやりたくない」と感じたことがありました。
その人が得意だとわかっていることをやらせ続けるのは、その人を過去に引き戻すことでもあります。
— 専門にこだわらないとすると、仕事の割り振りはどうやって決めているのですか?
安斎 MIMIGURIでは基本的に、その案件を「面白い」と思う人に任せています。メンバーそれぞれが、仕事の中に楽しみを見出していくことが重要と考えているからです。 例えば今、とあるチームでは、大学のプロモーションについてのコンサルティングプロジェクトを手掛けています。テーマは「青春」。でもMIMIGURIでこの仕事を担当している人は、ブランディングの専門家でもなければ、こうした仕事の経験があるわけでもありません。「この人は以前、最近こういうことに興味があると言っていたな」と思い出して、「やってみない?」と声を掛けたという流れです。
— ただ会社側からすれば、その人の“専門”は既に価値が担保されたもので、一方で新しい技術は、それが役に立つかどうかもわからないわけですよね。
安斎 おっしゃるとおり、自分のリソースの大部分を得意なものに振り向けなければ、稼ぐことも活躍することもできないでしょう。しかし両手があるのに、得意な仕事だけにリソースを全振りしていたら、もう一方のキャリアは死んでしまいます。「今の業務で培っているスキル」と「未来に実現したいキャリア」は、つながっていることが理想ですが、実際には切り離されていたり、相反する状況に陥ったりしていることもあります。
目の前の業務以外の何が自分の未来につながっているのかは、その時点で100%わかるものではありません。それでも新たなキャリアを獲得するためには、探りながらトライしていかなければならない。自分のパフォーマンスを100としたとき、すべて使って100の価値を出している状態は、実は停滞していることなんです。得意分野へのリソース集中は8割までに抑え、残りの2割は戦略的に別の分野に振り分けていく。その意味で、「年収はあえて抑えないといけない」のです。
— 同じことは企業にも当てはまりそうですね。
安斎 ええ、変化は組織にもつきものです。「選択と集中」が事業戦略の正当な手段のようにいわれますが、もし会社が「今これが一番儲かる」という業務だけに全リソースを集中していたら、新規事業は何も生まれません。いずれその会社は死んでしまうでしょう。未成熟な組織であればもちろん、成熟した組織であっても、技術の発展や社会環境の変化があれば、それに適応するために組織を変えなければなりません。
若いときに得たスキルで一生逃げ切るというのは、誰にとっても厳しいことです。どんな会社も、今儲かっている事業にいつまでも頼ることはできず、どこかでリソースを振り分けて新しい事業にシフトしていかなければなりません。ホンダが自動車だけでなく「移動」について考えているのはそのためです。
われわれは「選択と集中」に代わる新たなキャリア戦略として、不確実性の時代の中で学習を軸にキャリアを開く探究的アプローチを「分散と修繕」と呼んでいます。
情報発信が「推し」を引き寄せる
— MIMIGURIでは企業活動以外に、CULTIBASE(カルティベース)というサイトで研究についての発信を行っていますね。こちらもすごい発信量だと思いますが、狙いはどこにあるのでしょうか?
安斎 MIMIGURIには、「自分のアイデンティティが変わっていくような学びこそ最高の学習」と考え、自らの変容を楽しむカルチャーがあります。自分の内面的変化を探求するため、日々気付いたことや小さなアウトプットをどんどん発信していくことを奨励しているのです。80人の成果をネットに上げているわけで、ある意味でカオスな状況になっていますが……。
— 何かを狙って発信しているというより、内面から湧き上がるものを皆さんが発信しているんですね。
安斎 そうです。湧き上がってきたものをそのままアウトプットしているのは、それが「暗黙知」を「形式知」へ転換していく取り組みであり、お互いを知ることにつながるからです。
社員の誰かの動画が出たら、朝会で「今度こういうのが出たよ」と紹介して、お互いを知る機会をつくっています。それを見ることで「あいつ、こんなことを考えていたのか」と知ることができます。
発信には副次的な効果もあります。MIMIGURIは広告宣伝費や営業費用が極小なんですが、それは発信したものを見た人がお客さんになってくれているからです。
発信を見ている人は、われわれとの共通言語を持ってくれます。先ほど話に出たホンダのミネルヴァプロジェクトの担当者にしても、僕の本を読み、動画を見てくれていました。あのプロジェクトには驚くほど費用がかかっていて、こちらから持ちかけて実現するのは困難だったでしょう。僕の発信を見ていた人が、僕を推してくれた結果、生まれたプロジェクトともいえます。
— 安斎さんがクライアントから「推された」わけですね。
安斎 ただこれは両面的な関係で、われわれもクライアントを推しますし、クライアントから推されるコンサルタントになりたいとも考えています。
「推し活」の「推す」は、能動態のように思われますが、実は頭で「推そう」と思っても推せないものです。一方で「推せ」と命じられても、それもできません。つまり「推し」というのは「能動態」でも「受動態」でもない、中動態的なものだと考えています。それを目的としているわけではないのに、「つい推してしまう」「気づいたら推していた」となるものです。
そして「推し」とは現状への評価ではなく、未来への期待です。推し活も、「その人がこの先どうなっていくのか」に興味があって応援する行為です。それがミュージシャンなら、まだ耳にしていない新曲を楽しみにしている状態といえるでしょう。
— 安斎さんは個人として、書籍やMIMIGURIのウェブサイトでオープンに発信しつつ、SNSやポッドキャストなどでクローズドなコミュニティも形成されています。さまざまなフェーズで発信を続けているのはなぜでしょうか?
安斎 戦略的に書き分けているわけではなく、日々考えていることを発信していかないと、自分の頭に残っていかないからです。
例えば、今日の話の中で「年収はあえて抑えないといけない」というワードが自分的に印象に残ったのですが、それを今日発信すれば、記憶に残ります。しかし仮に「今月、印象に残ったことを発信する」程度の解像度なら、このワードはおそらく記憶されないまま消えてしまうでしょう。
「推し活」についても、これまで何度か触れましたが、それは毎日発信しているからこそできたことです。もし年に数回しか発信していなかったら、推し活についてアウトプットしていなかったかもしれません。僕が考えたことが誰にも知られなければ、推されることはありません。でも「昔、水泳の授業で怖い思いをした」という話でも、発信すれば「わかる」と共感してくれる人がいます。
今日のような「推し活」についての取材は、これがまだ2回目です。でも今回の取材内容が発信されることで、それを見た人がまた話を聞きに来てくれるかもしれません。情報はお金と同じで、タンスにしまっておくと何も起きませんが、外に出すと複利で積み上がっていくんです。
— 安斎さんは今後、推したいこと、やりたいことはありますか?
安斎 先ほどお話に出た著書『冒険する組織のつくりかた』では、これまでの経営論の軍事的な世界観に対するオルタナティブを示すことができました。しかし、中には「軍事的世界観はいやだけど、“冒険”にもまだちょっと抵抗がある」という人もいるでしょう。
全員がチャレンジ精神を持って、全員が深く推しあっている組織というのも、それはそれでちょっと居心地が悪いかもしれません。「誰も知らない居酒屋」のほうが居心地がいい場合もあるし、どのクラスにも「教室の中心よりも端っこの窓際が落ち着く」という人はいるでしょう。僕自身がそういうタイプですから。
そうした人たちを含む、多様な人々に向けても、組織で生きるヒントを提供していきたい。その意味では今後、「冒険にうまくノレない人」を推していきたいですね。
— 冒険的世界観が、ここからさらに広がっていくことを期待します。