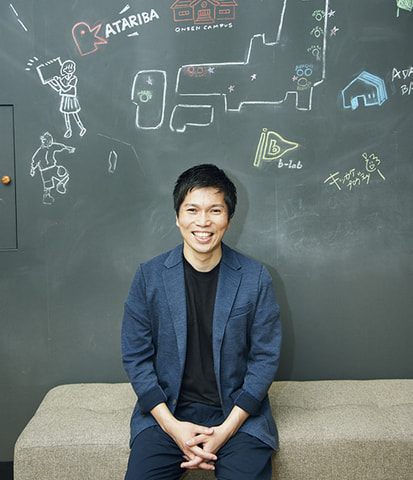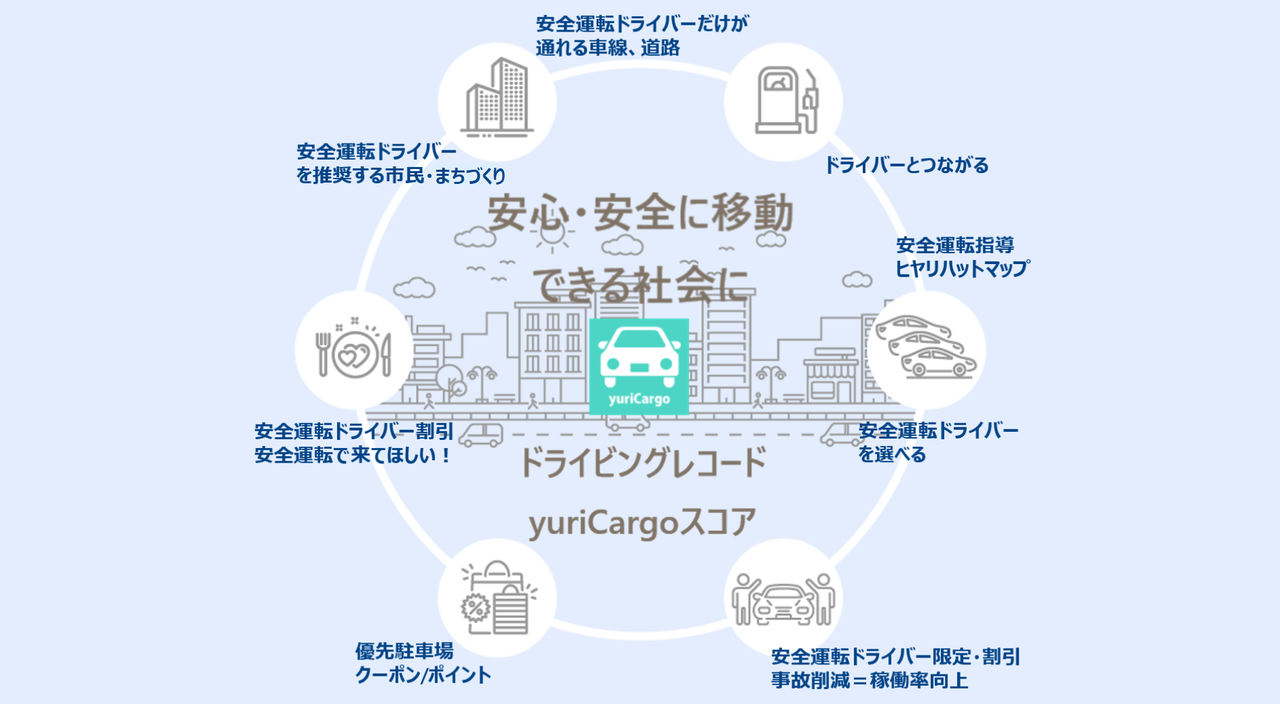NPO創設のきっかけ
―カタリバは今年設立20年。現在は専属スタッフ130名、年間活動予算12億円というスケールで活動されていますが、最初はやはり数人から始まったわけですよね。
鶴賀 おっしゃるとおりです。カタリバは代表理事である今村久美と、三箇山優花の2人が2001年に設立したNPOです。
今村は大学入学を機に上京し、大学生活は毎日が本当に楽しくて刺激的だったそうです。それまで知らなかったような語彙を駆使し、社会や未来を語る同級生と机を並べ、生まれて初めて「学ぶ喜び」を知ったといいます。しかし、成人式で地元に帰った際、久し振りの再会の場で地元の友人たちが、口を揃えて「毎日がつまらない」と言うのを聞き、社会の格差と分断というものに直面。とてもショックを受けるとともに、「どちらの世界も知っている自分だからできることがあるのではないか」と考え始めました。
自らも就職に悩んでいる年長者として、親と子、先生と生徒というタテの関係でも、友達同士というヨコの関係でもない、若者と「ナナメの関係」と「本音の対話」を軸とした学びの場を設けよう、と思い立ったようです。そこで大学生を中心としたボランティアを集め、高校に出向き、高校生たちと一緒にキャリア
について考える、ということからカタリバの活動がスタートしました。
友人のつながりで学生を集め、あちこちの高校に足を運んでみたものの、当初は「学生が何を教えるというんだ」という反応で、「来てくれ」と言ってくれた学校はほとんどなかったとのこと。それでも何年か続けていくうち、やがて年に20~30校で出張授業を行うようになっていきます。
といっても高校の側からはほとんどお金は出なかったので、大学生たちはボランティアでしたし、運営メンバーもアルバイトしながらの活動でした。
―鶴賀さんご自身がカタリバに参加したのは2008年ですね。きっかけは何だったのですか。
鶴賀 本当に偶然です。私は当時転職活動中で、たまたま駅でカタリバ代表の今村の講演告知のポスターを見たら、「NPOで稼ぐ」とあったので、興味を惹かれて聞きに行ったんです。場所は市民センターの一室で、聴衆は20〜30人でした。
テーマが「NPOで稼ぐ」だったのに、実際は「キャリア学習のNPOをやってきたけれどもずっと手弁当で、今にも潰れそうで悩んでいる」という話で(笑)。
周りの人たちは「何も考えずにやっているんだね」なんて感想を言い合っていたのですが、私はむしろ「頑張っていてすごいな」と思いました。「日本の中高生が自分のキャリアをイメージできなくて、将来が不安になっている」という今村代表の話も、まだ20代だった私には肌で実感できることでした。
講演終了後に今村に挨拶したら、「一度事務所に遊びに来てください」となって、行ってみたら、「何でもいいから手伝ってほしい」と言われまして。社交辞令を並べてやり過ごすこともできたと思うんですが、「何もしなければこの活動は終わってしまうかもしれない」と感じ、飛び込むことにしたんです。
―参加してみて、いかがでしたか。
鶴賀 事業は主に都内での学生ボランティアによるキャリア学習の出張授業。代表のほか、学生のときからカタリバに関わってきた数人が職員として、アルバイト同然の報酬で働いている状況でした。NPOとしての収入は年間4,000万円程度。半分以上は経費で消え、いつも「来月の給料をどうしようか」と悩み、半年おきぐらいに「いつまで続けられるのか」と思いながら活動していました。
そんな状態でも活動が続けられていたのは、学生ボランティアたちが頑張ってくれていたからです。ほぼ無償で、事務所に泊まり込むなどして企画を作り、熱心に活動していました。そのエネルギーを糧に、立ち止まることなく続けることができていたから、今のカタリバがあると思います。
転機となった震災支援
―財務状況が不安定だったNPOが、今では予算12億円。何か転機があったのですか。
鶴賀 転機は2011年3月の東日本大震災です。
その頃は私たちも日々の業務で手一杯だったので、自分たちに何ができるのか悩みました。最初に、ボランティアの卒業生たちが街頭で募金を集め、そのお金を手渡すために、まず代表の今村が被災地に行き、私も5月に現地に向かいました。
震災直後の被災地は、食べるものも着るものも十分にない状況で混乱しており、とりわけ「被災した子どもたちに居場所がない」ことがはっきりとわかりました。
災害が起きると、大人たちも生きるのに必死です。家を失い、避難所や仮設住宅に入っている中で、子どもたちの教育やケアはどうしても後回しになります。その意味では私たちが普段見ていた、自分たちの居場所がない東京の高校生たちと共通するものがあると気づいたんです。
「被災地の子どもたちには、日常の居場所が要る。何かやらないと」と考え、そのためのお手伝いをしようと決意。それまでは高校で出張授業をするというワンショット(1回限り)の活動をしていましたが、ここで、カタリバ創設以来初となる常設の支援施設を設立して、子どもたちの日常の居場所を作り、そこで学習支援をするという活動に乗り出したのです。
私がその責任者となって現地に赴任し、被災地の教育委員会や学校を訪ねて、「子どもたちの日常の場所を作りませんか」と呼びかけました。私たちが活動を始めたときには、授業自体はもう再開していました。ただ、グラウンドにも仮設住宅が立ち並んでいる状態で、放課後学習もクラブ活動もできない。子どもたちの放課後の居場所がなかったんです。
避難所の一角に住み、お風呂もない中での活動です。幸い、教育委員会に力を貸してくださる人たちがいて、活動を始めることができました。それが、子どもたちのための放課後学校、コラボ・スクールの「女川向学館」と「大槌臨学舎」です。
このとき、震災前まで現地で塾の先生をしていた人たちに「手伝ってほしい」と声をかけました。
女川町でいうと、それまで10以上あった私塾のほとんどが津波で流されてしまっており、先生たちも「なんとか再開できないか」と思っていました。その人たちに声をかけたわけです。11人と雇用契約を結び、コラボ・スクールで働いていただきました。
コラボ・スクールの運営も、最初は苦労しました。NPOのメンバーは私も含めて基本的に若手で、首都圏の出身です。塾の先生たちは平均年齢が40歳ほど。それまでは自宅で教えていらっしゃって、一国一城の主だったわけです。皆さん年上ですし、被災者でもあったので、仲間と認めてもらえるかどうか、不安でした。このときはまだ、お互いに距離をとっていましたね。
また、NPO活動そのものにも、まだ理解がありませんでした。首都圏は別として、日本全国でNPOが認知されるようになったのは、東日本大震災以降のことだと思います。
震災当時は「NPOって何だ」「東京から来た者が、ここでいったい何をするのか」という雰囲気でした。教育委員会はウェルカムでも、「学校の外に学びの場を作る」ということに対して、学校の先生たちからは警戒心を持たれていたようです。
私たちは「町の大人全員で、子どもたちを支えていきましょう」と訴え、「それはカタリバだけではできません。みんなでやらないとできないんです」とお願いし続けました。
幸い、カタリバは対話活動がメインのNPOです。話し合うことを大事にするカルチャーがあったので、いろいろなことを率直に話す中で、段々と距離が縮まっていきました。
例えば先生たちとの間では、子どもたちの情報を共有することが、パートナーシップのきっかけになりました。
子どもたちは皆、幾つもの面を持っています。学校での姿、コラボ・スクールでの姿、仮設住宅での姿、みな違います。学校の先生や私たちや親御さんたちで、それぞれ見ている面が違うんです。子どもたちの情報を伝えられて嫌がる先生はいません。
「あの子はコラボ・スクールではこんな表情をしている」「あの子は数学のこんなところに困っている」といった、自分が見た子どもたちの姿を伝えて、共有していくと、今度は先生方から「あの子の親御さんはこうで、家庭環境はこうで」といったことを教えてくれるようになり、その積み重ねでチームになっていったと思います。
活動にあたり、一つ大きな問題がありました。子どもたちにコラボ・スクールに来てもらうには送迎が必要ですが、交通機関が機能していなかったんです。私たちは教育委員会や学校の先生たちとも相談して、そのためにバス路線を開設することにしました。全部で3ルート設定したのですが、それだけで年間1,000万円ほどかかります。なんとか資金調達して運営を始めたら、これがすごく喜ばれました。
また、親御さんたちも、自分が大変で、子どもの送迎までできない状況でしたが、子どもを預けたいという気持ちはあったんです。ただ最初は「東京のNPOが子どもを守れるのか」という雰囲気でした。そこで「教育委員会と連携してやっています」「地元の人がメンバーとして働いてくれています」と伝えました。
そうして「地域のみんなでやっている活動」と理解してもらえてからは、親御さんたちも「それじゃあバス停まではこちらが送ろう」というように、連携して動いていただけるようになりました。
コラボ・スクールには最盛期には小学1年から中学3年まで200人ぐらい、実に町の子どもたちの3~4割が来てくれるようになりました。
地元の要望もあって、スクールは今も活動中です。今後は、地域に法人を設立し、地域に合った持続可能な形で運営を継続することに挑戦していく予定です。
―その後、被災地での支援活動を続けてこられたんですね。
鶴賀 熊本震災のあった2016年4月から、熊本でも支援活動を始めました。
きっかけはコラボ・スクールに通っていた高校生の一人が、熊本震災のとき、「東日本大震災では私たちも支援をもらったから、今度はこちらが物資を送りたい」と言ってきたことです。
ただSNSを見ると「モノは足りている」という書き込みが多かった。でもその子にそう伝えたら、「全部足りているとか絶対にない。僕は被災者だったからわかる」と言う。伝手を辿って調べてみると、やはり物資が届いていない所もあることがわかり、トイレットペーパーなどを送りました。
現地で活動するかどうかについては、カタリバは元々災害支援を目的として創られたNPOではないので、いろいろ議論もあったのですが、東北での支援活動を始めて5年が経ち、居場所づくりのノウハウもできており、きっとお役に立てるだろうということで、女川町で活動していたメンバーに行ってもらうことになりました。私自身も立ち上げの3週間は現地でお手伝いをしました。
実際に行ってみると、行政の皆さんも「実績をお持ちなんですね」と歓迎してくれ、東北での経験がすごく生きて、スムーズに活動を始めることができたと思います。
熊本ではカタリバとして2年間活動し、その後は現地で移管先を探して、今では地元の大学に運営を移管しています。また、熊本で活動を始める際、九州出身のスタッフを採用したのですが、「ずっとここで活動を続けたい」という希望があったので、そのスタッフには今も残ってサポートを続けてもらっています。
東日本大震災と熊本震災での経験から、こうした子どもたちへの支援活動が被災地で求められていることがわかり、その後は被災地支援がカタリバの活動の柱の一つとなりました。長野県や、岡山県真備町での水害、また熊本豪雨での水害でも支援を行っています。
災害が起きると、どうしても子どもたちは優先されなくなり、居場所がなくなるんです。それを助ける活動はこれからも続けていきたいと思っています
NPOのファイナンスモデル
―最近は社会課題の解決を目指すソーシャル・ビジネスのベンチャー企業も増えています。そうした企業とNPOの違い、「NPO法人だからこそできること」とは何だと思われますか。
鶴賀 NPOの強みは「困っている人たちに直球でサービスを届けられること」だと思っています。
ビジネスとしてやるのとNPO 活動とでは、サービスの作り方や受益者の層が違います。ソーシャル・ビジネスでは、受益者からお金を頂くのが基本です。でもそれだと、お金を払えない人たちをどうするのかという問題が出てくる。NPOは対価を受け取る必要はないので、災害の被災者など、サービスの対価としてお金を支払えない(経済的に余裕のない)人にもサービスを提供できます。
逆にカタリバでは、マーケットソリューションが利く事業は手がけません。儲からないところ、誰もやらないところに絞って活動しています。
ただ、本当に困っている人、支援を必要としている人に支援を届けるのは、実は難しいことなんです。
例えばカタリバでは、コロナ禍以後、オンラインでの教育支援を始めており、支援先をオンラインで募集しています。対象は、生活困窮世帯のご家庭です。しかしスマホを使い、ネットで教育支援について調べて応募してくるのは、一定のITリテラシーを備えていることが前提になります。
しかし日々の生活に困窮している家庭の中で、たとえスマホは持っていたとしても、子どもの教育にそこまで気が回らない人たちがいます。そういう人はわざわざネットで検索してまで子どもの教育支援制度に応募はしないし、子ども自身もそういった制度があることに気づかない。そこには情報の格差があり、別のアプローチが必要です。すべての子どもたちに学びを届けるために、NPOとして、そういった問題を追求していく責任があると思っています。
―ソーシャル・ビジネス全般に共通する課題として、ファイナンスがあると思います。カタリバのファイナンスの指針について教えていただけますか。
鶴賀 2010年までのカタリバは、「事業で収入を得て回していこう」というスタンスでした。出張授業でも、出張先の高校からお金をもらおうとしていて、その意味では受益者負担のソーシャル・ビジネスを志向していました。
ただそれでは、なかなかうまくいきませんでした。それは一つには、自分たちの活動の意義について、私たちに訴える力がなかったためでもあります。
NPOの外の人たちに我々の活動が理解されるようになったのは、震災支援がきっかけでした。それまでの「中高生のキャリア教育」だとわかってもらえなかったものが、「震災で居場所をなくした子どもたちの支援」というと理解が得られ、寄付を集められるようになっていったんです。
この場合の受益者は被災者の子どもたちなので、費用を負担する力がないことははっきりしています。そういうケースだと理解を得やすいんですね。震災をきっかけに、企業からも個人からも寄付が増えていきました。
私たちは皆、若かったということもあって、最初は「寄付」という形でお金を頂くことに対して、後ろめたい気持ちがありました。
お金を得れば寄付する人が自分たちの上に立つことになり、お金の使い方も制限されて、事業の自由度が失われるのではないかと感じていたんです。
でも実際に寄付を頂いて活動し、きちんと成果を出せば、「もっとやってほしい。もっと社会を変えてほしい」と言われるし、逆に「子どもたちへの支援は、3年では終わらないでしょう」と先方から言われて、支援を託されることもあります。
そうした経験を通じて、「寄付とは、支援というニーズへの対応を、寄付者が私たちに託す行為なのだ」と感じるようになりました。つまり私たちは、自分では社会的な活動が難しい人たちに代わって活動しているのです。
今は「寄付する人たちとその資金で活動する私たちは、どちらが上でも下でもなくて、対等なパートナー」という理念の下、寄付を募るにも、「寄付はパートナーシップを築くきっかけ」「仲間を増やす」「仲間であり続けてもらう」という感覚でやっています。
今の寄付者の内訳は、企業と個人が半々ぐらい。1度でも寄付してくれた方を数えると、3万人以上になります。それだけの数のサポーターとともに仕事しているのだ、という気持ちでいます。
社会とのコミュニケーション
―社会課題の解決が目的となるNPOでは、一般企業以上に、社会とのコミュニケーションが求められそうですね。
鶴賀 社会とのコミュニケーションは、NPOにとって非常に重要な問題と思っています。
カタリバの広報の基本は、自分たちの活動を通じて社会を変えていくストーリーを説明し、仲間を増やしていくことです。とりわけ震災のような危機に素早く動くには、普段からカタリバのサポーターとして継続的に支援してくれる人や企業がいるかどうかが、大きな違いになってきます。
私たちが寄付を集め、活動し、成果を出して、それを寄付者に還元していく。そうした成果を広報を通じて伝え、カタリバの活動内容と存在意義への理解が深まっていったことが、寄付が増えていった根本にあります。
NPOがWebやSNSでデジタル広告を配信し、賛同する人を募って大きく寄付を集めようとすることには反対意見もあります。しかし、あえて発信してきました。批判されるリスクを背負ってでも、世の中を変えていきたいと思っているからです。
伝えるべき成果とは、一つは「ボリューム(量)」で、教育でいえば何人の子どもたちに届けられたか、それはどんな子たちだったのか、そこに何を届けたのかといったことです。カタリバの年次報告でも、「2,281人のボランティアキャストが45校9,141人の生徒へ『ナナメの関係による本音の対話』を届けた」「豪雨で被災した659人の子どもたちに『安心して過ごせる居場所や学習支援』を届けた」というように、数字を挙げて報告しています。
そしてもう一つは、私たちの活動によって子どもたちがどう成長したのかという「質」の部分です。
学びへの意欲や探究心、自己肯定感を高めていくことが、成長の軸。その結果として、ソーシャルアクションを起こす中高生が生まれたり、希望の高校や大学に進学したりする結果につながっていきます。
東日本大震災以後、宮城県女川町、岩手県大槌町、福島県広野町で、10年間活動を続けてきました。東北の田舎町に、「ナナメの関係」を持ち込んだことで、ロールモデルや新しい学びとの出会いが生まれ、生徒たちの進路やキャリアがいっそう多様化されたと思います。大学進学に興味がなかった生徒が東京の大学に進学したり、地元に残って地域の活性化に取り組んだりする卒業生もいます。「今度は、自分が支援する側に回りたい」と、カタリバに入社して、地元の高校の魅力向上に取り組む新卒社会人も、生まれ始めています。
社会課題の解決を目指すNPOであるからには、できれば子どもたちの能力が具体的にどう伸び、それにより地域がどう変わったかという、社会に対するアウトカムの部分までつなげて成果を報告していきたいところです。残念ながら、それについてはまだエビデンスをもって語れておらず、十分な報告ができていません。これは今後の課題だと思っています。
またNPOとして「世の中には解決すべきこんな課題があります」と訴え続けていくことも、大事な活動と考えています。
多くの社会課題は、一時の活動だけでは解決できません。東日本大震災での支援も、当初は1年ぐらいで終わるだろうと思っていたのですが、現実には今も活動を続けています。
本当に解決すべき社会課題は、解決まで10年単位で時間がかかる。ということは、それだけの期間、お金を集め続けなければならず、そのためには社会課題を適切に表現し、人々に関心を持ってもらう必要があるということです。
今はコロナ禍もあって、カタリバとしても新たに寄付を募るルートとしては自社WebやSNSという、オンライン経由が多くを占めています。ただ、まだ効率的に発信ができているとはいえず、今後は企業のデジタルマーケティングのノウハウを、ファンドレイジングの分野に応用していきたいと思っています。
広告で気をつけているのは、カタリバの支援の対象である人たちがそれを見たとき、嫌な思いをしないかという点です。受益者の尊厳を守ることは、何にも増して大事なことですから。
今は企業も世の中の反応をすごく気にしています。その意味では寄付する側のリテラシーも上がっています。
私が中学生ぐらいだった頃、寄付といえば、路上で募金箱にお金を入れるものでした。中には実態がよくわからない、「この
募金先に本当にお金が届くのですか」とつい疑いたくなるものもあった気がします。NPOはそれではだめなんです。資金の
使い途や成果についてきちんと報告し、「どんな課題を解決しているのか」をわかりやすく伝えないといけません。
人材のマネジメント
―NPOの場合、組織のパーパスに共感した人々が集まっている一方、個人の考え方の違いなどから、マネジメントが難しそうなイメージがあります。
鶴賀 マネジメントは日々悩んでいます。NPOとして特徴的なのは、ボランティアのマネジメントですね。皆それぞれボランタリーの精神を持って来てくれるので、それを生かして、やりがいを持ってカタリバの活動に関われるようにしていかなくてはならない。単発で終わらせず、「もう一度やりたい」と思ってもらえることが大事なんです。
そのためには、各参加者のモチベーションと団体としての目的をすり合わせる必要があります。その人がやりたいことと、こちらで用意した活動をマッチングさせないと不満が残ってしまう。対話、コミュニケーションを繰り返し、すり合わせていくしかない。
活動を継続していくためにはバックオフィス業務をする人も必要ですが、資金調達や総務などの仕事は、業務内容としては一般の企業と大きな違いはありません。その分、働く人にとっての意味付けが大事になってきます。「あなたの仕事がカタリバの活動にどう役に立っているか」「子どもたちの支援をどれほど支えているのか」を実感してもらう必要があるんです。
企業とNPOでは同じ仕事でも意味合いが違う。それを理解してもらうためのコミュニケーションには時間をかけています。
コロナ禍以前には全社会議と称して、島根などのカタリバの地方拠点に全メンバーが集まって喧々諤々議論し、自分たちの存在意義を問う、といったことをやっていました。今はリアルで集まることが難しくなっていますが、とにかく対話を重ねて、それぞれの人にとっての活動の意義を見出してもらうことがマネジメントの基本です。
今後取り組むべき課題
―今後はどういった活動を計画されていますか。
鶴賀 「どんな環境に育っても、日本の10代の子どもたちが自分の意思で自分の未来を創っていけるようにする」というカタリバのビジョンは変わりません。ただ、これからやらなくてはいけない活動については、計画に基づいて活動するというより、その時々に起こる社会課題を解決するべくプロジェクトがどんどん生まれていっている、というのが実情ですね。
例えば子どもの貧困の問題があります。日本の場合、相対的貧困と呼ばれ、「見えない貧困」ともいわれてきました。普通に食事して、服も着ていて、住んでいる場所もある。でもよく観察すると、3食の食生活が不安定だったり、給食費を納める財力が家庭に不足していたり、家の中で勉強するスペースがなかったりします。また、親の介護が必要で子どもがそれにあたっている「ヤングケアラー」という問題も認識され始めました。コロナ禍ではそうした子どもたちの間の格差や分断が、表に出てきた面があると感じています。
また、外国がルーツの子どもたちの支援も始めました。学校に通っていても、日本語を話せないと取り残されてしまうなど、いろいろな課題があります。ここでも外国ルーツの子どもたちと、少し先を行く外国ルーツの社会人の先輩が「ナナメの関係」で本音を話し合うことで、日々の生活で困っていることを解決したり、将来の夢を見つけたりという支援活動を行っています。
2020年には、新型コロナウイルス感染拡大による全国一斉休校を受け、学校という居場所を失くした子どもたちに、オンラインで居場所とストレスケア、意欲と創造性を育む機会を提供する「カタリバオンライン」を始めました。
ほかにも経済的な問題を抱える家庭を対象にオンラインでの学習支援を行う「キッカケプログラム」や、カタリバオンラインを使いたくても使えない就学援助受給世帯向けに、パソコンとWi-Fi機器の無償貸与も行っています。
こうした社会課題の解決は、我々だけではできません。
行政やほかのNPOと連携して対処していく、また新たな若いNPOを育てていく。そんなインキュベーションの機能も果たしていきたいと考えています。
カタリバが推進している、中高生が自ら地域課題をテーマとして設定し、それを解決する実践型探究学習「マイプロジェクト」というものがありますが、これは元々、東北の被災地で、自らも被災者である高校生が地域を変える活動を始めたことからスタートしました。その活動の中で、生徒たちが自分のマイプロジェクトを発表する全国コンテストを行っているのですが、8年前に始めたときは全国で18人の参加者だったのが、今年は1.3万人という規模まで拡大しました。これを実現できたのは、行政、学校、NPO、地域団体と連携できてきたことが理由の一つだと考えています。
マイプロジェクトは一例ですが、「地域の若者を応援したい」「子どもの未来につながる何かをしたい」と考えている団体、個
人は全国各地に存在します。そういった方々と連携して、カタリバだけではリーチできない子どもたちに対して支援を広げていくことで、一人でも多くの子どもたちの未来につながる活動をこれからも続けていきたいです。